【社会人が司法試験合格を目指す方法】ロースクールと予備試験の判断基準
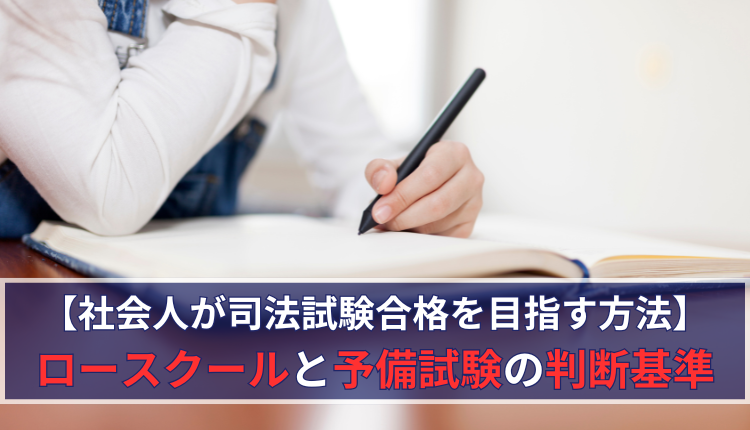
目次
この記事を読んで理解できること
- 社会人がロースクールと予備試験を選ぶ判断基準
- 予備試験ルートが社会人に最適な5つの根拠
- 夜間ロースクールを選ぶべき社会人の特徴
- 社会人の効率的な司法試験対策戦略
あなたは、
- 社会人として働きながら、効率的に学習して司法試験合格を目指したい
- ロースクール進学か、それとも予備試験を目指すか、どちらがいいか分からない
そんな悩みを抱えていませんか。
「社会人が司法試験を目指す」と決めた時、多くの方が不安に感じるのが、学習時間の確保や経済的な負担、そして何より「本当に自分にできるのか?」という迷いです。
しかし、自分に合ったルートを選択し、明確な戦略のもとに学習を進めることで、働きながらでも夢を実現することは十分に可能です。
そこで、本記事では、ロースクールと予備試験のそれぞれの特徴を比較しながら、社会人がルートを選択する際の判断基準を明確にして、さらに社会人受験生にとって予備試験ルートを選択することのメリットや、夜間ロースクールが向いているタイプまで具体的に紹介します。
また、合格を現実にするための勉強戦略も、実践的な視点から詳しく解説していきます。
具体的には、
1章で、社会人がロースクールと予備試験を選ぶ判断基準
2章で、予備試験ルートが社会人に最適な5つの根拠
3章で、夜間ロースクールを選ぶべき社会人の特徴
4章で、社会人の効率的な司法試験対策戦略
を紹介していきます。
あなたの夢を「現実」に変えるための第一歩を、この記事とともに踏み出しましょう。
1章:社会人がロースクールと予備試験を選ぶ判断基準
司法試験の受験資格を得るには、
- 法科大学院(ロースクール)ルート
- 予備試験ルート
いずれかのルートを辿る必要があります。
どちらのルートを選ぶかは、学習スタイル、経済的負担、キャリア設計などにも大きな影響を与えるため、社会人受験生にとって、非常に重要な判断ポイントとなります。
そこで、本章では、社会人ならではの視点から、ロースクールと予備試験、それぞれのメリット・デメリットを整理し、自分に合った選択肢を導くための判断基準を解説します。
1-1:時間的制約から見た両者のメリット・デメリット
社会人にとって司法試験を目指す上で、最も大きな障壁のひとつが「時間の制約」です。
限られた1日の中で、どれだけ学習に集中できるかが、合格への成否を分ける鍵となります。
ロースクールの場合、昼間部であれば平日の昼間に通学して講義を受ける必要があり、原則としてフルタイムの学生生活を送ることが前提となります。
期間は最低でも2年間に及び、法律の学習に専念することになります。
これは、社会人が現在の仕事を継続したままでは対応が難しく、退職や長期休職を視野に入れる必要があるという点で大きなハードルです。
その代替として、夜間ロースクールという選択肢もあります。
平日の夜間や土日に講義が設定されており、働きながら通学することも一応は可能です。
ただ、夜間ロースクールの設置校は限られており、地域によっては通学自体が難しいこともあります。
さらに、実際には、通学や授業の拘束時間を含めると、平日夜は数時間集中して講義に出席し、復習や課題にも取り組む必要があります。
土日も終日講義が組まれていることが多いため、体力的・精神的な負担は想像以上に重くなります。
一方で、ロースクールに通学せず予備試験を受験するルートでは、独学や通信講座をベースとした学習スタイルが主流であり、学ぶ時間や場所を比較的自由に設定できるのが最大のメリットです。
早朝の出勤前、通勤電車の中、昼休み、仕事終わりの夜間、あるいは週末のまとまった時間など、ライフスタイルに応じて柔軟に学習計画を立てることができます。
特に、スマートフォンやタブレットを使ったオンライン講義、音声教材などの発展により学習環境は非常に多様化しています。
具体的には、運転中に講義音声を流したり、休憩時間などで演習問題を解くといった工夫ができるため「いつでも、どこでも」学べる環境が整います。
このような学習スタイルは、多忙な社会人にとって、生活リズムに合わせて学習を進めやすく、現実的な選択肢といえるでしょう。
とはいえ、予備試験ルートが「楽な道」だというわけでは決してありません。
なぜなら、時間的な自由度が高いぶん、学習を自己管理できる能力が求められるからです。
例えば、ロースクールのようにカリキュラムが組まれていたり、定期的な試験・課題が課されるわけではないため、自ら計画を立てて淡々と勉強を継続する姿勢が不可欠です。
また、予備試験の学習範囲は広く、かつ論文試験も含まれるため、単なる暗記では単なる暗記だけでは太刀打ちできません。
計画的に学習を進めなければ、内容の抜けや偏りが生じやすく、結果的に学習期間の長期化や不合格の要因となる可能性があります。
1-2:経済的負担の具体的な比較
ロースクールに進学する場合、まず学費として年間100〜150万円、2〜3年間通えば総額で300〜450万円程度の出費が必要です。
これはあくまで授業料のみであり、入学金や教材費を加えると、さらに高額になります。
また、ロースクール通学期間中は、平日昼間の講義に対応する必要があるため、仕事を辞めるか、勤務時間を減らすといった対応を取らざるを得ないケースも少なくありません。
その結果、収入が減少し、通学期間中の生活費の確保に不安を感じる人も多くいます。
もちろん、奨学金制度や教育ローンといった金銭的支援制度も整備されていますが、数百万円単位の新たな借金を背負うことに心理的なハードルを感じることは否めません。
一方、予備試験ルートであれば、独学で学ぶ場合は市販の基本書・過去問などにかかる費用のみ、通信講座や予備校を活用する場合でも、総額で50万~60万円程度に収めることは可能です(ただ講座の受講の数などによって影響されることがあり、場合によっては、100万円を超えてしまうなど、もう少し高額になる場合もあります)。
比較的低コストで挑戦できるため、生活費や家庭の支出とのバランスが取りやすい点も、大きな魅力の一つです。
1-3:合格率から見る現実的な成功確率
令和6年度の法科大学院の在学中の受験者の合格率は約55%で、法科大学院の修了者の合格率は約22%となっています。
一方、予備試験を経由して司法試験に臨む受験者の合格率は非常に高く、90%を超えており、他のルートと比較しても、圧倒的な合格実績を誇っています。
これは、予備試験そのものが極めて難関であるため、合格者はすでに司法試験合格レベルに達するだけの知識と実力を備えていることを示しています。
いわば、「司法試験を受ける前に一度厳しい選抜を経ている」状態であり、最終試験での成功確率が高くなるのは当然ともいえるでしょう。
とはいえ、予備試験自体の合格率はわずか3~4%程度とされ、依然として極めて難関であることに変わりはありません。
このような中では、特に社会人の場合は学習時間に制約があるため、「いかに効率よく学習を進めるか」「どれだけ継続的に学習を続けられるか」が、最終的な合否を大きく左右することになります。
単に「長時間学習」を重ねるのではなく、「質の高い学習」と「一貫した計画」が不可欠です。
ロースクールでは中間試験やゼミ、指導教員による面談など、段階的に学力を確認しつつ学習を進められる、体系的な教育体制が整っており、学習の進捗や理解度を客観的に把握しやすく、修正が必要なタイミングも見極めやすいメリットがあります。
特に学習習慣に不安がある人や、自分ひとりではモチベーションの維持が難しい人にとっては、こうしたサポート体制は心強い要素となるでしょう。
それに対して、予備試験ルートでは、学習の進捗管理もモチベーション維持も、すべてが自己管理と自己責任に委ねられています。
誰かに強制されることなく、自ら目標を設定し、計画を立てて学び続けなければなりません。
自由度が高い反面、孤独感や焦りを感じる場面も少なくなく、途中で挫折してしまうリスクも存在します。
社会人にとっては、「どの程度の自己管理能力があるか」「孤独な学習に耐えられるか」といった点も、現実的な成功確率を左右する重要な判断材料となるのです。
2章:予備試験ルートが社会人に最適な5つの根拠
ロースクールと比較すると、予備試験ルートについては「合格率の低さ」や「学習管理の難しさ」がよく指摘されます。
確かに、予備試験は一筋縄ではいかない難関試験であり、万人向けのルートとは言えないかもしれません。
しかし、実際には多くの社会人がこのルートを選び、限られた時間と環境のなかで、合格を実現しています。
では、なぜここまで困難なルートが社会人にとって「最適」だと言われるのでしょうか?
その背景には、社会人の特性や強みを活かせる5つの合理的な理由が存在します。
以下では、それぞれの理由を具体的に見ていきましょう。
2-1:合格率3.6%でも、司法試験合格率は90%以上
予備試験の合格率は毎年おおむね3~4%と非常に低く、最難関試験のひとつに数えられています。
この数字を見ると、挑戦をためらうかもしれません。
しかし注目すべきは、その次のステージである司法試験の合格率です。
予備試験経由で司法試験を受験した人の合格率は、実に90%を超えています。
これは、予備試験がすでに司法試験と同等かそれ以上のレベルの実力を求めており、「予備試験に合格する時点で、ほぼ司法試験合格圏内に到達している」とも言えるからです。
つまり、社会人が「予備試験→司法試験」という2段階の挑戦を選ぶことは確かに険しい道ではあるものの、長期的に見れば非常に効率のよいルートともいえるのです。
初期段階でのハードルは高くても、司法試験合格への最短距離を突き進める、それが予備試験ルートの最大の魅力なのです。
2-2:仕事を継続し収入を確保しながら挑戦可能
ロースクールに進学する場合、平日昼間の通学が必要になることが多く、会社勤めをしながら通うのは困難です。
夜間ロースクールという選択肢もあるものの、時間的な制約や通学の負担は依然として依然として大きな障害となります。
その点、予備試験ルートであれば、働きながらでも十分に挑戦可能です。
最近では、動画講義や音声教材などを活用した「ながら学習」も普及しており、通勤時間や昼休み、帰宅後の数十分といった「スキマ時間」を有効に使う社会人が増えています。
スマートフォン1台で講義を視聴し、問題演習も可能な環境は、まさに現代社会人のライフスタイルに合致した学習スタイルです。
また、フルタイムで働き続けられるということは、生活費や家族の教育費などを確保しながら挑戦できることを意味します。
キャリアや経済的基盤を大きく崩さずに済むことは、社会人にとって非常に大きな利点です。
2-3:年齢制限なしで何度でもチャレンジできる
予備試験には、ロースクール修了者と同等の学識と法律に関する実務の基礎的素養があるかを判定する試験ですが、年齢制限や受験回数制限が一切ありません。
この点は、社会人にとって大きな魅力のひとつです。
例えば、思うように学習が進まなかった、仕事と学習の両立が難しく一時中断せざるを得なかったというような場合にも、状況が整った段階でいつでも再スタートを切ることができます。
社会人の場合、勉強を再開するのが30代・40代ということも珍しくなく、「自分はもう遅いのでは…」と不安を抱く人も多いかもしれません。
しかし、実際には40代で予備試験に合格し、その後、司法試験にもパスして活躍している法曹も少なくありません。
中には50代での合格を果たし、第二の人生を歩み始めた人もいます。
今の年齢やキャリアだからこそ、「本当にやりたい仕事に就きたい」「社会に貢献したい」という思いが明確になり、強いモチベーションと覚悟を持って、取り組むこともできます。
受験におけるチャンスが何度でもあるというのは、人生の再挑戦を目指す社会人にとって、非常に心強い制度設計といえるでしょう。
2-4:実務経験が試験対策で有利に働く
法律の学習は、単なる暗記科目ではなく、「条文をどう適用するか」「どのように論理を構築するか」といった思考力が重視されます。
この点で、社会人がこれまで培ってきた実務経験や問題解決能力は、大いに試験対策に活かされます。
例えば、会社で契約書に携わった経験があれば民法・商法の理解が進みやすく、行政機関と関わった経験があれば行政法にも親しみやすくなります。
また、日常的に文章を書いたり、報告書を作成している人は、論文試験で求められる論理的な構成力をすでに備えているケースも多いです。
つまり、社会人が試験に挑む際には、知識だけでなく、社会人としての経験も大きな武器になります。
これは学生にはない大きなアドバンテージといえるでしょう。
2-5:独学・通信講座で柔軟な学習スタイルが実現可能
予備試験ルートの最大の強みのひとつが、「多様な学習スタイルに対応できる」点です。
市販の教材や動画配信による通信講座が多数あり、現在では法学の学習経験がなくても、合格を目指せる体制が整っています。
さらに、大手予備校や通信講座では、基礎から応用まで段階的に学べるカリキュラムが用意されており、スマホ1台でスキマ時間に学習を進めることも可能です。
また、学習進捗を可視化できるアプリや、質問対応機能付きの講座もあるため、「一人でも安心して学び続けられる環境」が整ってきています。
最近では、答案練習や模試をオンラインで受けられる講座もあり、地方在住者や忙しい社会人でも本格的な受験対策を進められるようになっています。
こういう状況を踏まえると、学習の場所・時間・手段を自由に選べる予備試験は、「自分の生活スタイルに合わせて戦略的に学べる」社会人にとって最適な選択肢といえます。
以上の5つの理由から、予備試験ルートは決して「難しすぎて無理な道」ではなく、むしろ社会人だからこそ活かせる強みを最大限に引き出せるルートであることがわかります。
3章:夜間ロースクールを選ぶべき社会人の特徴
これまで予備試験ルートのメリットを紹介してきましたが、すべての社会人にとって、それが最適とは限りません。
この章では、社会人にとってのもう一つの選択肢をご紹介します。
それは、夜間ロースクールです。
夜間ロースクールは、働きながら法曹を目指す社会人のために設計された制度です。
特定の条件に当てはまる人にとっては、予備試験より適した学習環境となることがあります。
ここでは、夜間ロースクールに向いている社会人の特徴を3つ紹介します。
3-1:体系的な法学教育を基礎から学びたい人
法学未経験の社会人がいきなり予備試験の合格を独学で目指すのは、非常に高いハードルがあります。
憲法、民法、刑法をはじめとする難解な科目を、理解するのは容易ではなく、独学では行き詰まりやすく、途中で挫折するケースも少なくありません。
この点、夜間ロースクールでは、体系的に設計されたカリキュラムの中で、基礎から段階的に法学を学ぶことができます。
講義では教員による直接指導を受けられ、分からない点をその場で質問できたり、仲間とディスカッションを重ねたりしながら理解を深めていける点が大きな魅力です。
「まずは法律の基礎をしっかり固めたい」「自分ひとりでは不安がある」という方にとって、夜間ロースクールは心強い学びの場となるでしょう。
3-2:仲間との切磋琢磨でモチベーションを維持したい人
予備試験ルートは、どうしても孤独な学習になりがちです。
特に社会人の場合、周囲に同じ目標を持つ仲間がいないと、モチベーションの維持が困難になることもあります。
その点、夜間ロースクールでは、同じ志を持つ仲間と出会える環境があります。
授業やゼミ、模擬裁判などを通して刺激し合い、互いに高め合いながら勉強できるのは大きな利点です。
社会人学生同士であれば、仕事との両立の悩みや勉強時間の確保について情報交換することもでき、孤独を感じることが少なくなります。
そのような人にとって、夜間ロースクールのコミュニティは大きな価値を持つでしょう
3-3:実務研修で実践的スキルを身につけたい人
ロースクールのカリキュラムでは、講義に加えて法律事務所での実務研修や模擬裁判などが制度的に組み込まれています。
これにより、座学だけでなく、法曹として求められる実践的なスキルを在学中から身につけることが可能です。
予備試験ルートでは実務経験を得る機会を自ら作る必要がありますが、ロースクールでは制度として実務研修が用意されているため、より効率的に実務感覚を養えます。
将来、弁護士として着実にキャリアを築きたいと考える社会人にとって、実務のイメージを早期から持てるという点は大きなアドバンテージになります。
4章:社会人の効率的な司法試験対策戦略
最大の資源は『時間』と『体力』に他なりません。
社会人としてさまざまな制約がある中で司法試験に挑むには、極限まで効率を高めた学習戦略が不可欠です。
そこで、この章では、限られたリソースで合格にたどり着くための具体的な学習ステップを紹介します。
4-1:1年目は基礎固め、2年目は過去問演習に集中
多くの社会人合格者は、2〜3年という長期計画で司法試験に挑戦しています。
1年目の最重要課題は「基礎知識の定着」です。
特に法律初学者であれば、まずは条文・判例・基本書を通じて、法的思考のベースを築くことが重要です。
講義やテキストを活用し、体系的に各科目の全体像をつかむことが、実力の底上げにつながります。
1年目の学習では、焦らず丁寧に理解していくことが重要で、常に自分の学習の方向性が合っているかを確認する必要があります。
理解が中途半端なまま学習を進めていたり、方向性の間違った学習を進めてしまうと、直前になって「問題が解けない」「論文が書けない」「点数が伸びない」という事態になりかねません。
2年目からは、過去問演習に集中して、重点を「アウトプット」に移します。
過去問や答案練習、模試を中心に取り組むことで、知識を実践的に使いこなす力を磨いていきましょう。
解答を読むだけでなく、実際に書くことで論文式試験への耐性が養われます。
「インプットが完全に終わらないとアウトプットしない」という過度な考えは合格までの距離を伸ばしてしまうことになります。
例えば、問題演習の中で間違いに気づいたり、理解が不十分であったことを発見したりすることもあります。
アウトプットと並行してインプットを続けることも重要です。
インプットばかりに偏らず、適度な段階でアウトプットへ移行しましょう。
4-2:論文対策は早期開始で差をつける
司法試験では論文試験の比重が非常に高く、ここでの得点が合否を大きく左右します。
しかし、社会人の場合は「論文試験の学習に着手が遅れる」傾向があるため、早期の対策が合格の鍵となります。
最初から完璧な答案を書く必要はありません。
むしろ重要なのは「答案の型」を身につけることです。
典型論点を把握し、どのような構成・表現で書けば合格答案となるのかを体で覚えることを優先しましょう。
例えば、本サイトで紹介しているヨビロンは、実際に予備試験合格者が100%作成した業界唯一の論証集で、「答案の型」を身につけるには最適な教材の1つです。
また、添削付きの論文講座を利用することで、客観的なフィードバックを受けられ、自己流のクセや弱点を早期に修正できます。
自分の答案を第三者に見てもらうことは、成長速度を大きく引き上げる効果があります。
4-3:模試活用で本番レベルの実力測定
模擬試験(模試)は、単なる「試験慣れ」のためだけでなく、実力を客観的に測るための重要なツールで、特に社会人にとっては、模試をペースメーカーとして活用することが効果的です。
模試の活用には、主に以下の3つのメリットがあります。
- 時間配分と集中力の確認
- 記憶の定着と知識の抜け漏れの発見
- 学習継続へのモチベーション維持
模試を受験することで、本番を想定した時間内でどこまで書けるかを実戦形式で体感でき、忘れていた論点や理解不足の分野が可視化されます。
また、スコアの推移や偏差値の変化が、日々の努力の指標になりモチベーションの維持にもつながります。
例えば、月1回程度のペースで模試を受け、その結果をもとに学習の軌道修正を行うことで、効率的に弱点を克服しながら実力を高めていけます。
まとめ:自分の状況に合わせて最適なルートを選択しよう
社会人が司法試験を目指すうえで、「予備試験」か「ロースクール」かを選択するのは、単なる進路選びを超えて、人生設計に大きな影響を与える重要な判断です。
キャリアの段階、年齢、家庭環境、金銭的な余裕、さらには学習にかけられる時間帯やスタイルまで検討すべきポイントは多岐にわたります。
本記事では、予備試験とロースクールの違いや、社会人に予備試験が向いている理由、夜間ロースクールのメリット、効率的な試験対策まで、多角的に丁寧に解説してきました。
中でも、時間やお金に制約のある社会人にとって、「働きながら受験資格が得られる」予備試験ルートは、きわめて合理的で、魅力にも富んだ選択肢です。
そして、予備試験に本気で受かりたいなら、司法試験対策とは異なる、予備試験に特化した内容である必要があります。
その点、本サイトでご紹介している予備試験合格者が完全監修したヨビロンは、社会人受験生にとって心強い味方となるでしょう。
今この瞬間も、「やっぱり法曹の道を諦めきれない」「でも仕事や家庭を優先しながら勉強できるだろうか」と葛藤している方がいるはずです。
そんな方にこそ、予備試験合格という夢を無理なく現実に変えるための学習環境を、ぜひ手にしていただきたいです。
もちろん、ロースクールにも、体系的な教育や仲間との切磋琢磨といった大きな価値があります。
夜間部であれば社会人も受け入れており、法学未経験者でも段階的にスキルを積み上げていける安心感があるのも事実です。
どんな環境で、どんな学び方が自分にフィットするのか、じっくりと向き合い、自分だけのルートを見出しましょう。
予備試験でもロースクールでも、「本気で合格したい」という強い意志と継続力があれば、必ずチャンスはつかめます。
大切なのは、「今、動き出すこと」です。
本記事が、あなたの第一歩を後押しするきっかけになれば幸いです。
そして、あなたの挑戦が、新しい人生を切り拓くスタートとなることを、心から応援しています。






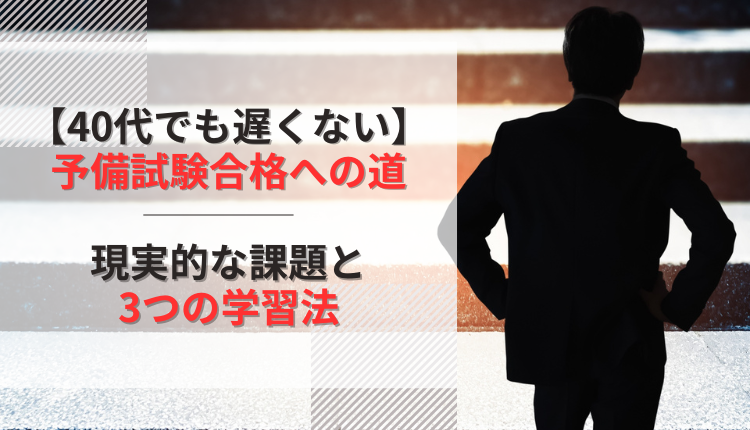
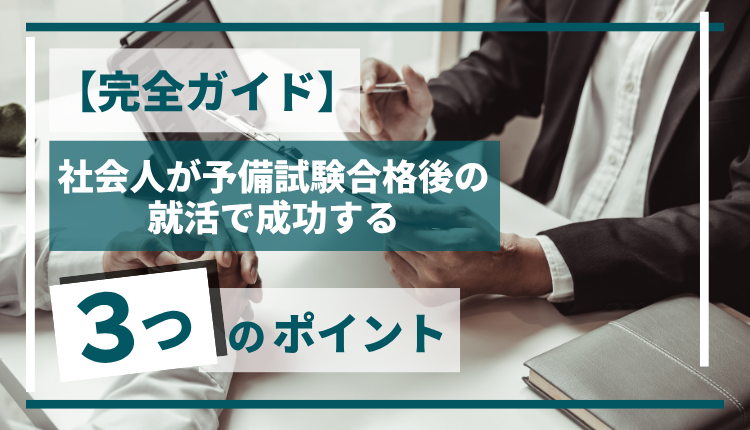
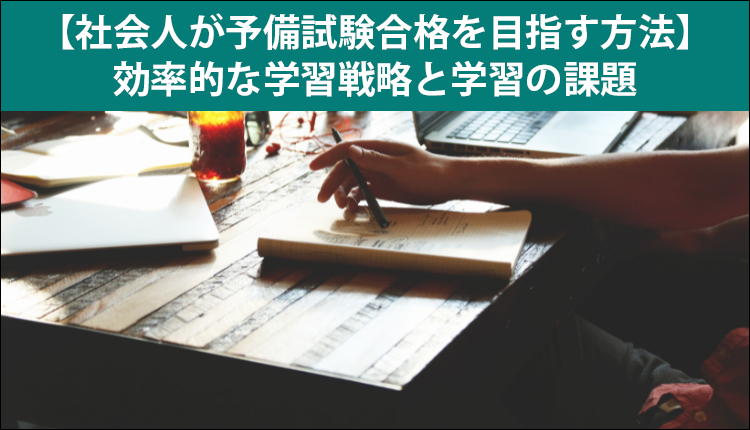
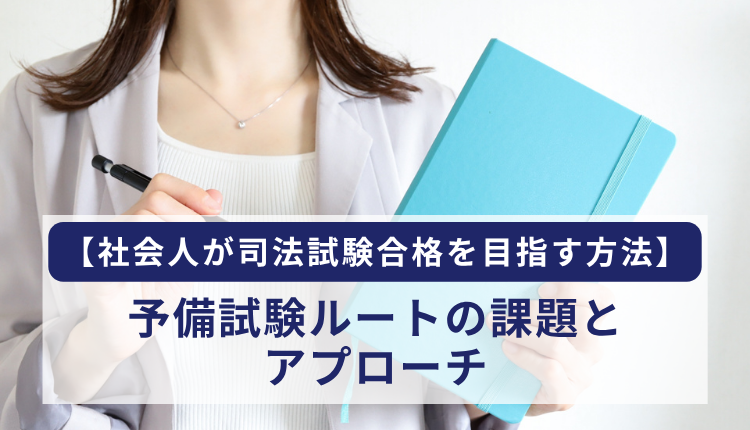
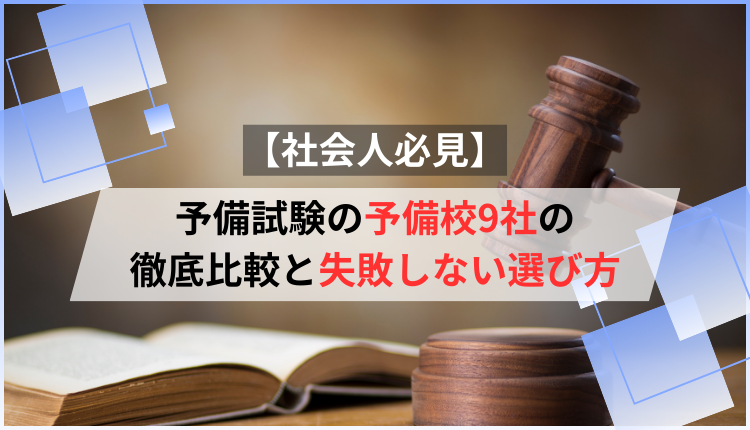
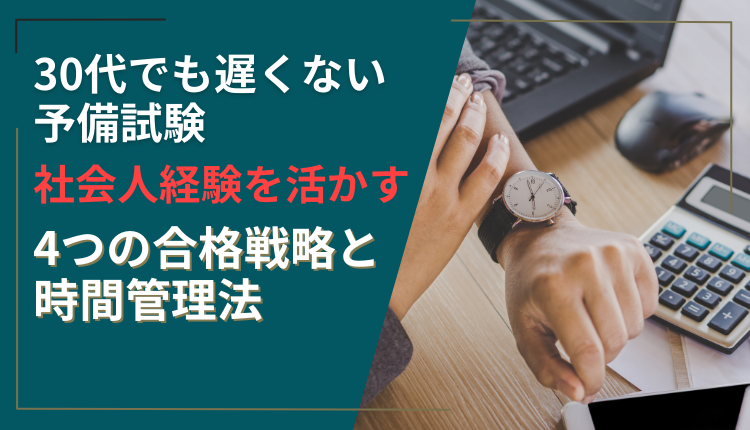

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。