【予備試験合格】勉強スケジュールの立て方を1年・3年に分けて解説!
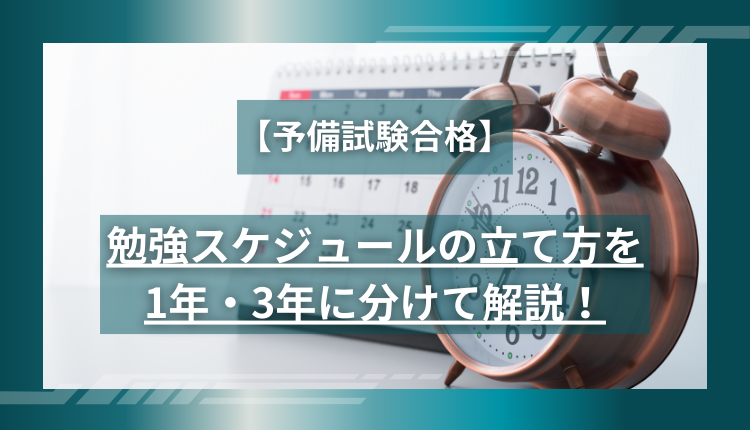
目次
この記事を読んで理解できること
- 予備試験の難易度と必要な勉強時間(最低3,000時間)
- 短期集中で予備試験1年合格を目指す勉強スケジュール
- 予備試験3年合格を目指す勉強スケジュール
- 効率的な勉強スケジュール管理の3つのコツ
あなたは、
- 司法試験予備試験に合格するために必要な勉強時間を知りたい
- 司法試験予備試験合格を狙える勉強スケジュールの立て方を知りたい
- 効率的に勉強スケジュールを管理するコツがあれば掴みたい
とお考えではありませんか?
予備試験は、最短1年で合格することも夢ではありません。
ただし法学既修者で、専攻していた法律の条文や重要な判例が頭に入っている方に限ります。
一方で、3年の月日をかけて、しっかり勉強してきた方でも思うような結果を得られないほど、予備試験が難関であることも事実なのです。
しかし、本記事を読めば、1年での最短合格を目指す方、3年間、腰を据えて勉強していく方がともに、どのような勉強スケジュールを立てればいいかがわかります。
具体的には、
1章で予備試験の難易度と必要な勉強時間
2章で予備試験1年合格を目指す方向けの勉強スケジュール
3章で予備試験3年合格を目指す方向けの勉強スケジュール
4章で効率的な勉強スケジュールの管理のコツ
について、詳しく説明します。
1章:予備試験の難易度と必要な勉強時間(最低3,000時間)
これから予備試験の合格を目指し、勉強スケジュールを立てていく前に、最初に予備試験の難易度と、予備試験を突破するために必要といわれている勉強時間(最低ライン)について、本章で説明します。
1-1:予備試験は合格率約3~4%の超難関
令和6年司法試験予備試験では、受験者12,569人中合格できたのは449人で、合格率3.57%という厳しい結果が出ています。
このように予備試験は合格率約3~4%で、100人受けて3~4人しか突破できない難しい試験なのです。
講義・アルバイトの時間以外は比較的、時間の融通が利く大学生の合格率は約6.58%で、朝から夜まで会社に拘束され働き、家事、家庭サービスもこなしつつスキマ時間を縫うように勉強していく方が多い社会人の合格率は、約1.27%と狭き門となっています。
しかしながら、法務省の資料(令和6年司法試験法科大学院等別合格者数等)によると、法科大学院ルートの司法試験合格率は34.84%(修了者22.73%、在学中55.19%)に対し、予備試験ルートの司法試験合格率は92.84%と驚異の数値を叩き出しています。
法科大学院ルートでの司法試験合格者が伸び悩む一方で、予備試験を突破した多くの方が、司法試験合格を果たしていることから、予備試験ルートでの合格を目指そうと思案中の方は少なくないでしょう。
1-2:予備試験合格に必要な年数は3~4年程度が目安
予備試験を制することが可能な勉強量は、3,000~10,000時間といわれています。
勉強に超集中できる方なら、2年弱で3,000時間を超えることができると思いますが、働きながら目指していく方は、週22時間の勉強をコンスタントに確保していくことができてはじめて、3年弱でちょうど3,000時間学べる算段となっています。
ただし法学未修者の方は、法律の知識が何もないところから始め、予備試験の会場に足を運ぶ頃には「法的思考力」と「答案構成力」を身に着けて、論文を書ける状態になっておく必要がありますので、予備校に通うことをおすすめします。
ちなみに法科大学院では、法学未修者コースと法学既修者コースがあり、それぞれ3年、2年の教育を受けることになります。
法科大学院ルートでは、法科大学院への入試対策を含め、司法試験まで3~4年、学習に費やすことになるのですが、同様に予備試験ルートで司法試験合格を目指す方も、司法予備試験まで3~4年が目安となっています。
先述したように司法試験突破率は、法科大学院ルートよりも予備試験ルートのほうが圧倒的に高いため、予備試験合格を目指すために3~4年の時間を費やす価値は十二分にあるのです。
なお、社会人の方で働きながら学習を進めていくつもりであれば、こちらも参考になります。
社会人は予備試験合格に何年かかる?スケジュールや学習法、最適な学習スタイルについて解説
社会人が予備試験に独学で合格する方法!科目別の勉強法も徹底解説
2章:短期集中で予備試験1年合格を目指す勉強スケジュール
法学部卒業、公務員試験合格者、公務員、法律事務所勤務(パラリーガル)、仕事で法務に携わっている人などは、1年で予備試験を突破できる素養があるといえます。
現在、予備試験の短答式試験は7月、論文式試験は9月、口述試験は翌年の1月に実施されているため、7月を起点とし、次に示す約1年間、集中して学習していきます。
- 前半(7月〜12月)基礎知識+論文式試験対策+インプット重視
- 後半(1月〜5月)過去問演習、模試、復習中心
- 直前期(6月〜7月)短答式試験対策に集中(肢別対策+条文反復)
以下、詳細を解説します。
2-1:前半(7月〜12月)基礎知識+論文式試験対策+インプット重視
法学既修者であれば基礎知識や学習のポイントは、ある程度身に付いていると思いますので、夏~年内は、短答式試験を意識し、基礎知識の再確認を行っていきます。
わかっている部分はスピーディに、専攻分野ではなかった法律条文・判例の読み込みは丁寧に行い、暗記していきましょう。
最初の1カ月ほどで、うまくエンジンがかかりはじめ、まだ読み込んでおくべき法律条文や判例が残っていると思いますが、勉強したことを定期的に復習する分散学習法略を取り入れつつ、並行して論文式試験対策もスタートさせます。
予備試験の短答式試験に受かっても、論文式試験をクリアできなければ不合格となるため、論文試験突破に必要不可欠な「答案構成力」と「法的思考力」「法的三段論法」を鍛えるために、実際に多くの論文式試験問題に触れ答案を作成していくのです。
短答式試験とは異なり、出題範囲に選択科目※と法律実務基礎科目(民事訴訟実務・刑事訴訟実務)が加わります。
※倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際公法、国際私法の8科目
法務省の資料「令和6年司法試験予備試験の出願状況について」によると、労働法(全体の37.08%)や倒産法(18.77%)、経済法(13.67%)を選んだ方が多いです。
初期の段階で選択科目を絞り込めば、効率よく学習できるのも確かです。
すべての法律条文や判例のインプットと定着に注力しつつ、論文試験対策でのアウトプットも行い、基礎を固めます。
大晦日までに、予備試験合格に必要な法律条文・条例のインプットを終え、及第点を獲得できる答案を書けるレベルにまで押し上げます。
2-2:後半(1月〜5月)過去問演習、答練、模試、復習中心
年が明けたタイミングで、いよいよ本格的に過去問を解き始める段階となります。
正答できる箇所と正答できない箇所を冷静に仕分けし、後者については今一度、関連する条文や判例を読み込んだり、なぜ間違えたのかを分析したりし、正しい知識の再定着を図っていきます。
論文式試験を突破するために必要性を感じたなら、予備校が実施する答練や模試に参加するといいです。
特に論文は正解がなく、独学では法的思考力や答案構成力が正しく身に付いているかのセルフチェックが難しいため、予備校の添削を受けることで、客観的に論文式試験に耐えられる実力かどうかを評価してもらえます。
また、過去問・答練・模試に終始するのではなく、これまでインプットしてきた法律条文や判例を忘れてしまうことがないように、引き続きスキマ時間などを使って基本書などを読んだりノートに書き記したりするようにします。
2-3:直前期(6月〜7月)短答式試験対策に集中(肢別対策+条文反復)
短答式試験に合格できなければ、次の論文式試験に駒を進めることが不可となりますので、最後の約50日間は短答対策を行い、ベストを尽くしましょう。
短答式試験では、憲法・行政法民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法・一般教養科目が出題範囲となりますので、これらに絞り「肢別対策」と「条文反復」を行っていきます。
過去問を繰り返し解いた受験生だからこそ出てくる悩みが「答えを覚えてしまった」なのですが(もちろんそのレベルに達しておく必要があります)、その悩みを逆手にとって編み出されたといえるのが、肢別対策です。
肢別対策は、過去問などの選択肢一つひとつを隈なくチェックしていく勉強方法で、なぜその選択肢を選ぶべきではなかったのか、その理由を自問自答していくものです。
ただし、肢別対策を行うのは7月ではなく6月で、7月は本番同様、時間配分を考え、速く正答を導くことを意識して解く練習を行っていきます。
誤解が生じないようにお伝えしておくべきは、肢別対策は6月の1か月間だけ行えばよいものではなく、1月からスタートさせる過去問演習でも選択肢一つひとつをチェックしていきます。
条文反復は、文字通り全ての条文を繰り返し読み込むことです。
特に苦手とする法律も逃げずに読み込んでいきます。
正直、1年という予備試験対策期間は短すぎます。
試験前日まで1日1分たりとも無駄にせず、最後まで諦めることなく勉強をしていくと覚悟できれば、きっと合格を勝ち取れるでしょう。
3章:予備試験3年合格を目指す勉強スケジュール
3~4年の予備試験合格を目指して約3年、勉強していく場合は、
- 1年目 基礎固めと学習習慣の確立
- 2年目 過去問中心の実践演習と弱点克服
- 3年目 本試験対策の総仕上げ
といった流れを意識して勉強スケジュールを計画・実行していくと、うまくいくはずです。
以下、1年単位で見ていくことにします。なお、本章のスケジュールの区切りは短答式試験に合わせ、7月はじまりで考えてください。
3-1:1年目|基礎固めと学習習慣の確立
1年目は、法学知識の基礎固めと学習習慣の確立を目指します。
学生は自宅で平日4時間・休日8時間、社会人は平日2時間・休日6時間程度の学習を習慣化させることを目標とします。
もっとも簡単な習慣化は、時間と場所を固定してテキストやノートを広げ、勉強していく方法です。
まず憲法・民法・刑法・行政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法のテキストに書かれている内容をインプットしていきます。
なかでも条文が少なく、初歩の初歩といえる憲法が最も入りやすいでしょう。
具体的には、あまり分厚くない薄めの入門書で、全体像を把握したのち、基本書を通読して条文の解釈を学びつつ、関連する法律条文も素読していきます。
また、重要と感じた箇所はノートに書き写し、暗記するようにします。
その際、意識すべきことは「知識の定着」で、法律条文や判例を小説のようにひととおり読み進めるのではなく、翌日・1週間後・2週間後などと時間を置いて定期的に復習を行っていくことが有効です(分散学習法略)。
そして、法律条文と同じくらい大切なのが判例です。
条文は法律の本質を示し、判例は問題解決のためにどう法律を適用したかを示したものです。
1年目は予備試験において重要と目される判例から覚えていきます。
また10月に入り、法学の知識が頭に入ってきたと実感できたところで、論文の答案を構成する際に役立つ基本パターンを習得し、身に着けていきます。
4~6カ月経つと、基本書のほか予備試験の出題範囲となっている法律条文や、判例などをひととおり通読・素読を終えると思いますが、予備試験を受ける日まで引き続き、何度も何度も読み込みます。
3-2:2年目|過去問中心の実践演習と弱点克服
2年目は、過去問を解き始め、論文式試験の選択科目と実務基礎科目の勉強を開始すべきフェーズとなります。
1年目に行ったインプットを、過去問演習を通じてアウトプットしていくことで、正しく理解できている箇所と正確に覚えていない箇所がわかり、苦手や弱点が可視化されていきます。
間違いが判明した時点で即座に学び直し、定期的に復習して、知識定着を図り、弱点を潰し、克服していきます。
7月~10月は、短答式試験と論文式試験(法律基本科目)を中心に過去問を解いていきます。
また並行して、論文式試験の選択科目と実務基礎科目の勉強と判例集の読み込みもスタートさせます。
選択科目は、倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際公法、国際私法の8科目のなかから、理解できそう、相性がよさそうなどの基準で一つ選ぶようにしましょう。
11月以降は、選択科目と実務基礎科目の論文式試験の過去問にも取り組み始め、答案構成力の強化を図っていきます。
また、必要に応じて予備校の答練や、添削を受けるようにしましょう。
ちなみに2年目の目標である弱点克服とは、合格レベルに達する知識のインプットとアウトプットができる状態になることを指しています。
一発合格を目指している方もいるかもしれませんが、可能であればリハーサル・試験慣れを目的に、丸2年目を終えた3年目の7月に、実施される予備試験を受験されるのをおすすめします。
3-3:3年目|本試験対策の総仕上げ
3年目は、ラストイヤーであり、翌年7月に実施される予備試験に向けて、本試験対策を行っていきます。
前半にやるべきことは、短答・論文両方の過去問を選択肢一つひとつも余すところなく徹底的に解きます。
後半は、制限時間内での答案作成を意識して、その練習を行い、本番で途中答案を出さないように対策していきます。
また、必要に応じて予備校の答練や、添削を受けるようにしましょう。
4章:効率的な勉強スケジュール管理の3つのコツ
最後に、1~3章を踏まえ、効率的な勉強スケジュール管理の3つのコツを解説します。
4-1:月間・週間・日間の計画立案方法
年間スケジュールについては2・3章でお伝えしましたので、それを基にして月間・週間・日間の計画を立案していきます。
計画立案時、まずはゴールを決めて、そこから逆算しながらざっくりと、そして細かく作成していく手法が適切です。
3年後に自分自身がどのような状態になっているべきかを考え、そのためにはどのように学習を進めておくべきか3分割し、さらに12分割して割り当てていけば月間計画ができあがります。
月間計画をさらに4分割すれば週間計画ができあがります。
週間計画は「テキスト30Pまで進める」「過去問15問を解く」など最も具体的に立てます。
そして、週間計画はこれ以上、細分せず、週の最後までに週間計画を達成すればよしと考えるようにしましょう。
また、計画の調整は週の最終日に行い、できる限り翌週で遅れを取り戻せるように動きます。
日間計画については、仕事や家庭の都合で変動しやすく、自分の意思とは関係なく思うとおりに進まない日も必ず出てきますので、勉強可能な時間帯を書き記しておく程度が、精神衛生上ちょうどいいのです。
4-2:仕事の繁忙期を考慮した調整術
社会人は「仕事の繁忙期」が必ず一定期間出てくると思いますので、繁忙期を考慮して計画を立てるようにします。
同僚の欠勤や残業の発生により忙しくなったときに学習を先送りとするのは仕方ありませんが、翌日や週末など、できる限り早期に遅れた分を取り戻すべきです。
事前に判明している繁忙期については、学習の前倒しを基本とし、できる限り後回しにしないように心がけてください。
ただし、繁忙期は勉強をしなくてよい期間ではありません。
今までインプットした法律条文や判例を忘れないように、スキマ時間を見つけて復習を行う分散学習法略だけは継続していくことが大切です。
4-3:モチベーション維持のための目標設定
学生時代、テストの答案用紙や美術などの課題を、クラスメイトの前で1番に先生に出して、誇らしく思いながら席に戻ったことはありませんか?
誰よりも速く、予定よりも早く、物事が進むと、心に余裕ができたり、優越感が芽生えたりします。
計画どおり勉強が進むと、それが成功体験として認識され、自信がつき、集中力の向上にもつながり、いいことだらけなのです。
一方で、計画に遅れが生じると、自己評価が下がり、嫌悪感が芽生え、モチベーションも下がりやすくなります。
そのため、敢えて緩やかな勉強スケジュールを立てておいて、実際にはペースを飛ばし、先に先に進めていく勉強方法は、モチベーションの維持に有効なのです。
まとめ:予備試験合格を目指す勉強スケジュール
1年で予備試験合格を目指すと決めた方は、下表のようなスケジュールを立てます。
|
前半(7月〜12月) |
基礎知識+論文式試験対策+インプット重視 |
|
後半(1月〜5月) |
過去問演習、模試、復習中心 |
|
直前期(6月〜7月) |
短答式試験対策に集中(肢別対策+条文反復) |
3年かけて、勉強していくと決めた方は、司法試験予備試験短答式試験が実施される7月に合わせて、7月はじまりとし、下表のようなスケジュールを立てます!
|
1年目 |
基礎固めと学習習慣の確立 |
|
2年目 |
過去問中心の実践演習と弱点克服 |
|
3年目 |
本試験対策の総仕上げ |
特に1年という短期で予備試験合格を目指すなら、時間がありませんので、すぐに勉強を始めましょう。
また、3年かけて勉強していく場合、大切なのは習慣化です。
1年とは言わず3カ月、いえ、1カ月で習慣化できるように今日からでも勉強をスタートさせるようにしてください。
短期集中で予備試験1年合格を目指す方、予備試験3年合格を目指す方、全員におすすめしたい教材が東大式予備試験論証集『ヨビロン』です!
特に法学未修者が最初に学ぶべき憲法について、条文や判例を覚えれば、短答式試験は難なくクリアできるかもしれませんが、論文式試験はそう甘くはありません。
予備試験論文式試験を突破するには、特化した解き方、人権・判例ごとの主張反論パターンをマスターしなければならないのです。
ヨビロンなら、1桁合格者の編み出した解き方や主張反論パターンを手に入れることが可能です。
弁論主義・争点効・複雑当事者訴訟など民事訴訟法の問題を解く際に、理解しておくべき項目は少なくありません。
上記を理解するためには、まず「訴訟物」「要件事実」を正しく把握しておく必要があるのですが、上記2点を理解しないまま論証を覚え、試験に臨み、不合格となっている方が後を絶ちません。
ヨビロンなら「訴訟物」「要件事実」をベースに33年分の過去問に触れ、業界最多257の論証を自分のものにできます。
ヨビロンは、暗記できていても理解できていないため答案を書けない状態から、理解できているから暗記せずともスラスラと答案を書ける状態に持っていくことが可能です!
ヨビロンを手に入れて、合格も勝ち取りましょう!






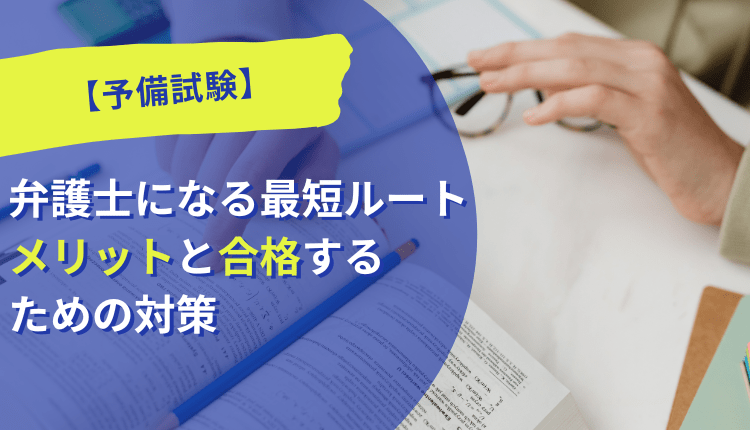

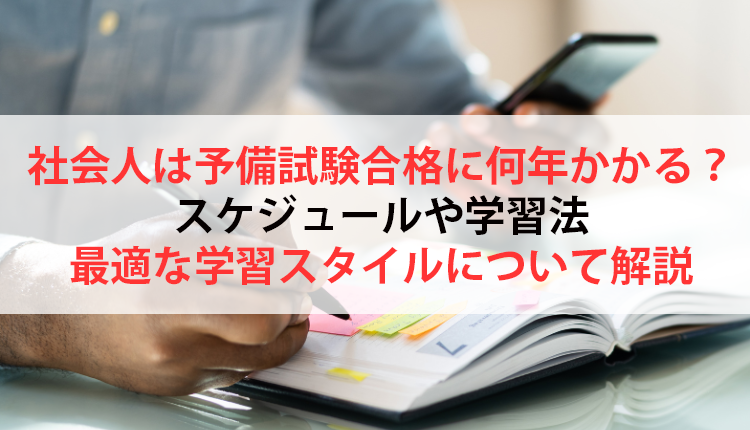
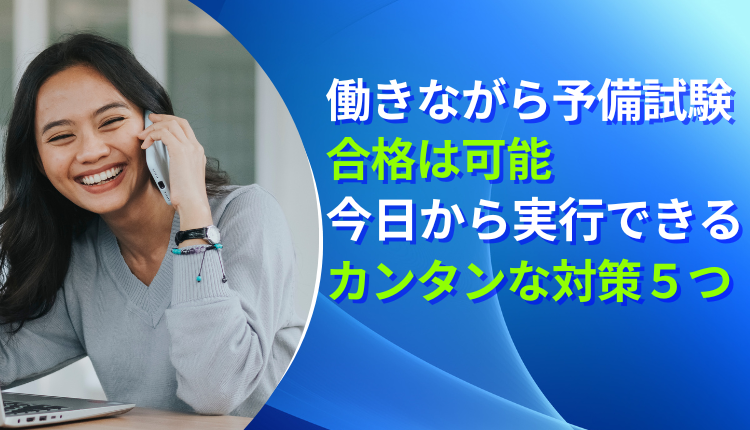
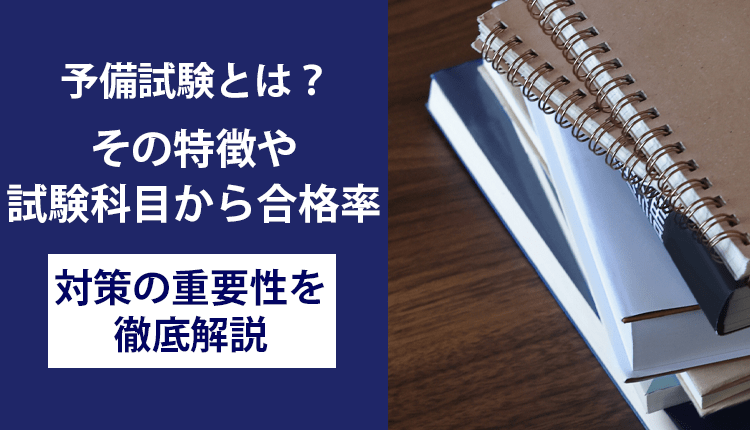
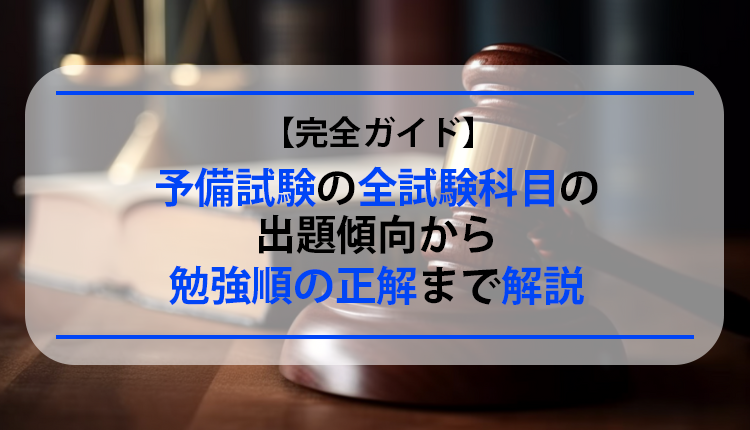

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。