【完全ガイド】予備試験短答対策|初学者のための3つの基本事項と最短合格法
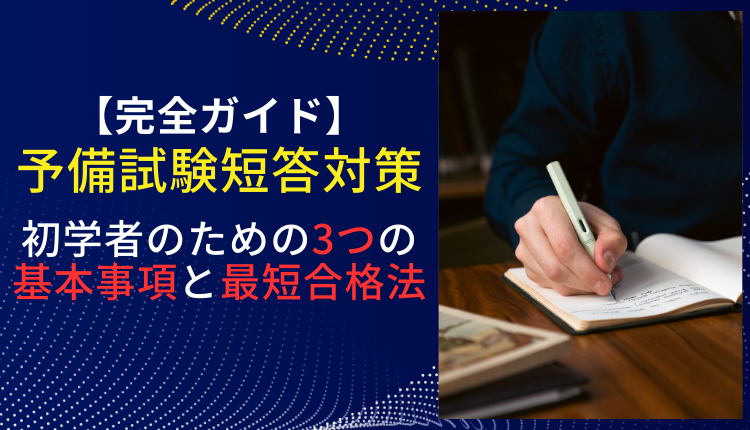
目次
この記事を読んで理解できること
- 予備試験短答対策|初学者が知るべき3つの基本事項
- 初学者におすすめ|過去問演習中心の学習法
- 初学者の学習設計|最短合格のリアルプラン
- 予備試験特有の対策は「ヨビロン」で学べる
あなたは、
「予備試験に初挑戦するけれど、何から始めればいいか不安…」
「予備試験短答式の効果的な学習方法を知りたい」
と悩んではいませんか。
予備試験の短答式試験は、合格率約22%という超難関です。
初学者にとっては「どこから手をつければいいのか」「何を優先すべきなのか」が見えにくく、時間や労力をムダにしてしまうケースも少なくありません。
しかし、正しい順序で効率的に学べば、基礎知識ゼロからでも短期間で合格レベルに到達することは可能です。
本記事では、短答式試験の全体像と戦略、過去問中心の学習法、時間の捻出方法、そして予備試験特化教材「ヨビロン」の活用法まで、具体的な手順を完全解説します。
具体的には、
1章では、予備試験短答対策として初学者が知るべき3つの基本事項
2章では、初学者におすすめな過去問演習中心の学習法
3章では、最短合格のリアルプラン
4章では、予備試験特有の対策は「ヨビロン」で学べる理由
を紹介していきます。
ぜひ、合格者の実体験と最新データに基づいた最短合格ルートを知って、短答突破への第一歩を踏み出してください。
第1章:予備試験短答対策|初学者が知るべき3つの基本事項
まずは、予備試験の短答式試験がどのような形式・難易度なのかを正しく理解することが、効率的学習の第一歩です。
ここでは、出題科目と配点、合格率の現実、そして論文対策との両立の必要性について整理します。
1-1:短答式試験の出題科目と配点の詳細
予備試験の短答式試験は、司法試験の短答式試験に比べて科目数が多く受験者も多いため、過去7年間の合格率は20%台前半で推移している大変難しい試験です。
予備試験の短答式試験の出題科目は、具体的には以下の通りです。
- 憲法
- 民法
- 刑法
- 民事訴訟法
- 刑事訴訟法
- 商法
- 行政法
- 一般教養(時事・歴史・経済・自然科学など)
短答式試験の出題科目は、司法試験法第5条第2項において、法律基礎科目である憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の7科目、及び一般教養科目について行うとされています。
配点の内訳は、法律科目が約210点(約8割)・一般教養が約60点(約2割)とされ、法律科目の比重が圧倒的に高いのが特徴です。

このため、初学者は法律科目の基礎固めを最優先に取り組む必要があります。
しかし、一般教養も決して軽視していいということではありません。
法律科目で多少失点しても、一般教養で確実に点数を稼げれば、合格圏に踏みとどまれるケースがあるからです。
例えば、特に社会人受験生の場合、一般教養の時事問題や文章理解は日常の読書やニュース視聴で鍛えやすいため、短期間で得点源に変えられる可能性があります。
また、短答式試験はマークシート形式ですが、単なる暗記ではなく正確な知識の運用力が問われます。
条文や判例知識を単に覚えるのではなく、「事例に即して適用できる力」を鍛える必要があります。
試験時間については、憲法・行政法が合わせて60分、民法・商法・民事訴訟法が合わせて90分、刑法・刑事訴訟法が合わせて60分、一般教養が90分です。
長時間に思われますが、単純計算で1問あたりにかけられる時間は約2分~3分しかありません。
そのため、知識だけでなく、瞬時の判断力と時間配分も合否に直結します。
さらに、出題範囲の広さも短答式試験の大きな特徴です。
そこで、過去問演習を通じて重要論点の出題パターンを押さえることが、効率的な得点アップにつながります。
初学者のうちは、まず「どの科目が何点配分されているか」「どの分野が毎年の頻出論点か」を把握することが、学習計画を立てる第一歩となります。
短答式試験の詳細はこちらの記事もご確認ください。
予備試験の短答式試験の概要と合格率、令和6年最新結果から傾向まで
1-2:合格率約22%の難関|上位2割に入る戦略
予備試験の短答式試験は、合格率が例年約22%前後とされています。
つまり、受験者のうち上位約2割しか突破できない非常に厳しい関門です。
この数字は一見そこまで低く感じないかもしれませんが、実際には短答式試験の突破者のほとんどが論文試験も見据えて高度な学習を積み重ねており、初学者がいきなり入り込むのは容易ではありません。
合格するためには、「上位2割に入る」ことを明確に意識した計画的な学習戦略が必要です。
単なる基礎固めや漫然とした過去問演習では、平均点付近で足踏みする可能性が高くなります。
短答式試験で結果を出す人の多くは、「頻出分野の深掘り」+「確実な得点源の確保」+「失点を最小限に抑える工夫」を徹底しています。
また、合格基準点は毎年変動しますが、おおむね総合得点の60~65%程度が目安となります。
つまり「満点を目指す必要はなく、他の受験者より効率的に点を積み上げれば良い」という発想が重要です。
この事実を理解しておくと、学習の優先順位付けがしやすくなります。
たとえば、予備試験全体で見た際に、出題頻度が高く得点効率の良い「憲法」「民法」「刑法」などの基本三科目の基本的な論点をまず重点的に固めるのが王道です。
これらは短答でも論文でも必須となるため、二重の意味で学習効果が高い分野です。
一方、出題比率の低い分野や過去数年で出題頻度が低下している分野は、試験直前期に軽く確認する程度にとどめ、序盤は深入りしない戦略が有効です。
さらに、短答式試験は一度の試験で大量の情報処理を要求されるため、知識の即時想起スピードも重要です。
同じ正答でも、制限時間内に答えられるかどうかで合否は分かれます。
そこで、知識を「引き出しやすい形」で整理しておくことが、得点力アップのカギになります。
このような「勝ち筋」を意識した学習を続ければ、初学者でも2〜3年計画で十分に合格圏に到達できます。
重要なのは、学習初期から「ただやる」ではなく、「どうすれば上位2割に入れるか」を常に逆算して取り組むことです。
1-3:論文対策との両立スケジュール
予備試験の短答式試験は7月中旬に実施され、その約1か月半後には論文式試験が控えています。
このため、短答の勉強だけに集中しすぎると、論文対策に必要な時間が足りなくなるリスクがあります。
特に初学者の場合、短答突破後にゼロから論文を始めるのでは間に合わないため、短答と論文の並行学習が必須となります。
両立のポイントは、「学習の比重を時期ごとに変える」ことです。
学習初期(試験の半年前〜3か月前)は、短答4割・論文6割の配分が目安となります。
この段階では短答式試験の基礎知識を固めつつ、論文については答案の書き方や典型論点の整理など、基礎的なアウトプット練習を並行して行います。
直前期(試験2か月前〜本番まで)は、短答の得点力を仕上げるために短答式試験の勉強へシフトします。
この時期の論文対策は、短答の学習範囲と重なる科目を優先することで、知識の相互強化が可能になります。
例えば、商法のように条文操作が重要な科目は、短答演習でインプットした内容をそのまま論文練習に活かすことができます。
また、短答終了後から論文本番までは、論文に全集中できる貴重な期間です。
この時期に慌てないためにも、短答式試験の勉強だけで手一杯にならない計画づくりが重要です。
具体的には、平日のうち1日は論文練習の日と割り切る、朝や通勤時間は論証の理解にあてるなど、日常の中で論文対策を少しずつ積み上げておく工夫が求められます。
結局のところ、短答と論文は別々の試験ではありますが、司法試験までを見据えた一連のプロセスの一部です。
「短答突破=ゴール」ではなく、「短答突破=論文合格のスタートライン」という意識を持ち、両輪をバランスよく回すスケジュール設計が、最終的な合格への近道となります。
第2章:初学者におすすめ|過去問演習中心の学習法
短答試験で確実に得点するためには、インプットとアウトプットのバランスが重要です。
特に初学者は、基本書の通読に時間をかけすぎるよりも、過去問を軸にした学習が効果的です。
そこで、この章では、過去問演習中心の学習法が効果的な理由や具体的な学習法をご紹介します。
2-1:基本書通読より過去問先行が効率的な理由
初学者が予備試験の短答対策を始める際、つい「基本書を最初から最後まで読み切ってから問題演習をする」という学習法を選びがちです。
しかし、この方法は膨大な時間を消費する割に、知識が定着しづらいという弱点があります。
特に社会人や時間の限られた受験生にとっては、このような学習は、非効率になりやすく避けた方がいいでしょう。
短答式試験は、条文や判例の正確な知識を問う形式であり、実際の出題傾向を知ったうえで学習する方が、必要な知識を効率的に習得できます。
そのため、まずは過去問に触れ、「何がどのように問われるのか」を肌で理解することが重要です。
過去問を先に解くことで、試験に頻出する条文や論点が浮き彫りになり、学習の優先順位をつけやすくなります。
もちろん、最初は多くの問題で間違えるかもしれません。
しかし、この段階での間違いは学習の出発点であり、「何がわからないか」を明確にする貴重な機会です。
この点、基本書を一通り読んでも、自分が理解していない部分を自覚できないまま終わってしまうことも少なくありません。
過去問を先行させるもう一つの利点は、インプットとアウトプットを同時並行で行えることです。
問題演習を通して知識の抜けを補い、その場で条文や解説を確認することで、理解が深まりやすくなります。
この学習の回転速度は、基本書通読だけの場合と比べて格段に速くなります。
さらに、過去問には「解き方の型」を身につける効果もあります。
単に知識を覚えるだけでなく、設問の意図を読み取り、正解にたどり着くための思考プロセスを磨くことができます。
これは短答式試験だけでなく、その後の論文試験や司法試験全般にも直結するスキルです。
結論として、初学者が限られた時間で最短合格を目指すなら、基本書の読み込みから入るのではなく、過去問を学習の中心に据える戦略が圧倒的に効率的です。
そのうえで、必要な範囲を基本書や条文に立ち返って補強する「逆算型」の学習こそ、短答合格への近道となります。
2-2:解答時間1.5倍設定で実力向上を図る方法
予備試験の短答式試験は、膨大な量の問題を限られた時間で解くスピードと正確さが求められます。
そこで有効なのが、「解答時間を本番の1.5倍に設定して演習する」方法です。
なぜなら、試験時間は本番で決まっていますが、初学者の段階でいきなり制限時間通りに解こうとすると、焦りやミスが増え、正しい解答プロセスを身につけられないことがあるからです。
例えば、本番で1問3分かけられる試験なら、練習時には1問4分半を目安に解くイメージです。
これにより、じっくり問題文を読み、条文や判例を正確に思い出す余裕が生まれます。
この時間設定の狙いは、単なる「ゆっくり解く練習」ではなく、正しい解法手順を体に覚え込ませることです。
焦らず論点を整理し、選択肢を比較検討する習慣を初期段階で確立することで、後に時間を短縮しても正答率を維持できる基礎ができます。
また、時間を多めに取ることで、「なぜその選択肢が正しいのか」「なぜ他の選択肢が誤りなのか」を丁寧に確認できます。
この学習の精度が高まるほど、知識の定着スピードは格段に上がります。
本番を想定したタイムプレッシャーを感じる前に、知識の正確さと論理の筋道を固める期間を確保することが重要です。
この練習を一定期間続け、正答率が安定してきたら、徐々に時間を短縮して本番と同じ制限時間で解く訓練に移行します。
こうした段階的アプローチにより、単なる「スピード勝負」ではなく、スピードと精度の両立が可能になります。
実際、多くの合格者も初期段階ではこの「余裕時間設定」を採用しており、結果的に本番で時間切れに追われることなく、自信を持って解答できるようになっています。
短答式試験対策の初期は、焦らず「正確さ優先」、その後「時間短縮」という流れを意識すると効果的です。
2-3:間違い問題の定期見直しシステム構築法
短答式試験対策において最も効率の良い学習は、「間違えた問題を重点的に潰す」ことです。
正解できた問題を何度も解くより、理解が不十分だった箇所を繰り返し確認する方が、短期間で実力を底上げできます。
そのためには、「間違い問題だけを集中的に復習できる仕組み」を作ることが重要です。
具体的には、過去問演習を行う際、間違えた問題や正解しても根拠が曖昧だった問題に印をつけておきます。
これを「弱点問題リスト」としてまとめ、一定のサイクルで見直します。
復習の効果を高めるためには、見直しのタイミングも工夫が必要です。
おすすめは、翌日・3日後・1週間後・1か月後という「忘却曲線」に基づいた間隔で復習する方法です。
間違えた直後は記憶が鮮明ですが、時間が経つと忘れてしまいます。
あえて忘れかけたタイミングで再確認することで、記憶の定着度が大幅に高まります。
また、見直し時には「なぜ間違えたのか」を必ず分析しましょう。
単なる知識不足なのか、問題文の読み落としなのか、時間配分のミスなのかを明確にすることで、次に同じミスを防ぐ具体策が見えてきます。
さらに、最近はアプリやスプレッドシートを活用して間違い問題を一元管理する受験生も増えています。
紙の過去問集ではなく、デジタル化して管理することで、外出先やスキマ時間にも復習でき、効率が飛躍的に向上します。
この「弱点特化型の定期見直しシステム」を構築すれば、試験直前期に膨大な範囲を総ざらいする必要がなくなり、最後まで安定して得点できる力が身につきます。
第3章:初学者の学習設計|最短合格のリアルプラン
短答式試験突破の鍵は、無理のない学習計画と継続力です。
ここでは、科目ごとのバランス調整法や時間確保の工夫、挫折しないための管理術を解説します。
3-1:月単位の学習スケジュール|科目バランス調整法
学習計画を立てる際の基本は、短答の全科目をバランスよく回すことです。
特定の科目に偏ると、他の科目の得点が伸びず、合計点で合格ラインを割ってしまうリスクが高まります。
特に初学者は、得意・不得意の差が大きくなりやすいため、意識的にバランスを取る必要があります。
理想的なのは、1か月単位で全科目を網羅する計画を立てることです。
例えば、憲法・民法・刑法といった主要3科目は毎週必ず触れ、行政法や商法などの科目は2週間に1回集中的に学習する、というように「頻度の高低」をつけたローテーションを組みます。
こうすることで、主要科目の記憶を維持しつつ、後回しになりがちな科目も定期的にカバーできます。
また、配点や出題数に応じて学習時間を配分することも重要です。
例えば、民法は短答式試験での出題範囲が広いため、月間の学習時間を多めに設定し、逆に出題範囲の狭い科目は効率的な演習と復習でカバーする戦略が有効です。
さらに、「1か月の中間点チェック」を取り入れることで、計画のズレを早期に修正できます。
例えば、月の2週目終了時に過去問の進捗や正答率を確認し、遅れが出ていれば残り2週間で重点的に取り戻す、といった具合です。
この習慣を持つことで、最終週に慌てることなく安定したペースを維持できます。
3-2:平日2時間・休日6時間の時間捻出術
社会人にとって最大の課題は、学習時間をどう確保するかです。
平日は仕事や通勤、家庭の用事に追われ、気づけば1日の自由時間がほとんど残っていない、という人も多いでしょう。
しかし、予備試験短答に合格するためには、平日最低2時間、休日は6時間程度の勉強時間を確保することが理想です。
平日2時間を確保するための基本戦略は、「細切れ時間の積み上げ」と「優先順位の固定化」です。
例えば、通勤時間に短答過去問の一問一答アプリを解く、昼休みに判例要旨を読む、帰宅後は机に向かって演習を行うなど、時間帯ごとに「何をするか」を決めておくと迷いが減り、効率が上がります。
朝型の人であれば出勤前の1時間を活用し、夜型の人なら帰宅後の時間を集中タイムとして固定しましょう。
休日6時間の学習では、長時間のインプットとアウトプットの組み合わせが効果的です。
午前中は頭が冴えている時間帯に過去問演習や論文練習を行い、午後は復習や暗記科目の定着に充てるなど、時間帯に応じたタスクの使い分けを意識します。
また、3時間ごとに15〜20分の休憩を入れることで、集中力の低下を防げます。
さらに、家族や職場の理解を得て学習時間を確保することも重要です。
あらかじめ学習スケジュールを共有し、「この時間帯は勉強に集中する」という枠を生活の中に組み込むことで、無駄な予定の割り込みを減らせます。
計画的な時間捻出は、短答合格のための最初のハードルであり、同時に最も効果の高い投資といえるでしょう。
3-3:挫折しない目標設定と進捗管理法
予備試験の学習では、長期戦になればなるほど挫折のリスクが高まります。
特に短答式試験対策は範囲が広く、成果が見えにくいため、途中でモチベーションが下がる人も少なくありません。
そこで重要なのが、達成感を得られる小さな目標設定と、現実的な進捗管理です。
まず、目標設定は「半年後に短答模試で合格ラインを突破する」などの大きなゴールだけでなく、「今週は民法総則の過去問30問を解く」「今月中に憲法の判例集を1周する」といった短期・中期目標を併用します。
こうすることで日々の学習が成果と結びつきやすくなり、達成の積み重ねが自信になります。
進捗管理には、可視化ツールの活用が有効です。
手帳や学習アプリで学習時間や進度を記録し、週単位で振り返ることで、計画の遅れや偏りを早期に修正できます。
特に社会人は、急な残業や家庭の予定でスケジュールが崩れることもあるため、「遅れを取り戻すリカバリーデー」を月1〜2回設定しておくと安心です。
また、モチベーションの維持には、フィードバックの仕組みが欠かせません。
模試や演習問題の結果を分析し、正答率や理解度が上がっていることを数字で確認すれば、自分の成長を客観的に把握できます。
数字の改善は、自信を持って次の学習フェーズに進むための強力なエネルギーとなります。
挫折を防ぐ最大の秘訣は、「完璧を求めないこと」です。
多少の計画遅れやミスは当たり前と受け止め、継続そのものを最優先する姿勢が、最終的な合格への近道になります。
第4章:予備試験特有の対策は「ヨビロン」で学べる
予備試験の短答は、司法試験とは出題傾向が異なり、独自の対策が必要です。
その差を埋めるために、合格者が作り上げた教材「ヨビロン」が注目されています。
4-1:予備試験1桁合格者の独自ノウハウを伝授
ヨビロンは、予備試験の最上位層である「1桁順位」の合格者が、自らの学習経験と膨大なデータ分析をもとに作り上げた、おすすめの教材です。
出題傾向を徹底的に解析し、頻出論点を優先的にマスターできる構造になっています。
無駄な周辺知識を削ぎ落とし、「出るところだけ」に集中できるため、学習時間の限られた社会人や初学者でも最短ルートで得点力を伸ばせます。
また、ヨビロンで得た知識を短答式試験で活用できることはもちろん、そのまま論文で使える形に落とし込めるのが大きな特徴です。
これにより、短答と論文の二重学習による負担を大幅に軽減し、効率よく全体の得点力を底上げできます。
4-2:初見の問題でも確実に点が取れる方法がわかる
ヨビロンの最大の強みは、単なる知識の暗記にとどまらず、「初見問題でも得点できる思考力」を養える点です。
初見問題でも問題文において、何を求められているのかが分かれば、正解にたどり着くことは可能です。
この点、ヨビロンでは、解答プロセスを体系化した「思考の型」を学ぶことができます。
具体的には、問題文の読み取り方から論点の抽出、解答の方向性を決めるまでの一連の流れを、実例を交えながらトレーニングします。
これにより、過去問にない形式や応用問題に直面しても、知識を引き出し、当てはめるための道筋が明確になります。
ヨビロンを活用すれば、安定して合格ラインを超える実力が確保でき、試験本番での精神的な余裕にもつながります。
まとめ:予備試験短答対策を効率化し、最短で合格へ
予備試験短答は合格率約22%の難関であり、限られた時間と労力をどこに投資するかが勝敗を分けます。
初学者こそ、配点と出題傾向を把握し、頻出論点を優先した過去問中心の学習で得点力を高めるべきです。
さらに、短答と論文を並行し、復習システムを活用して知識を定着させることが、最短合格への近道となります。
また、社会人受験生は、平日2時間・休日6時間を確保し、月単位の科目ローテーションで効率を最大化しましょう。
加えて、ヨビロンを活用すれば、初見の問題にも対応できる実力が身につきます。
本記事を参考に、自分の状況に合った戦略とツールで、短答突破への第一歩を踏み出してください。






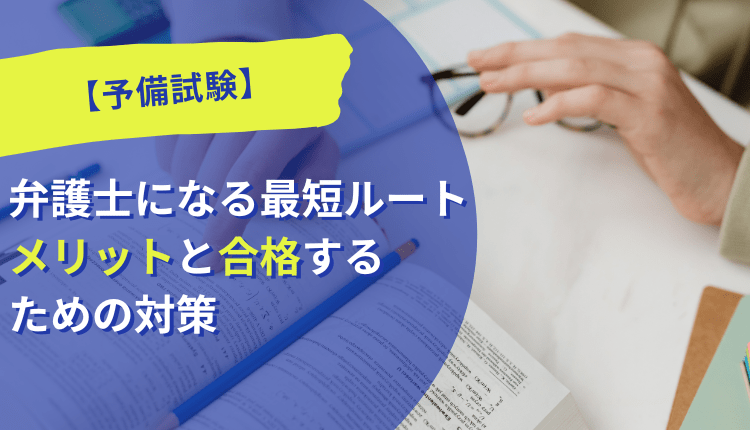
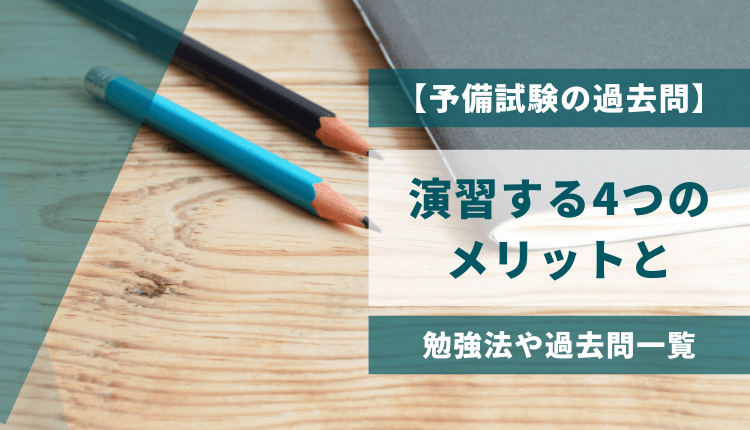
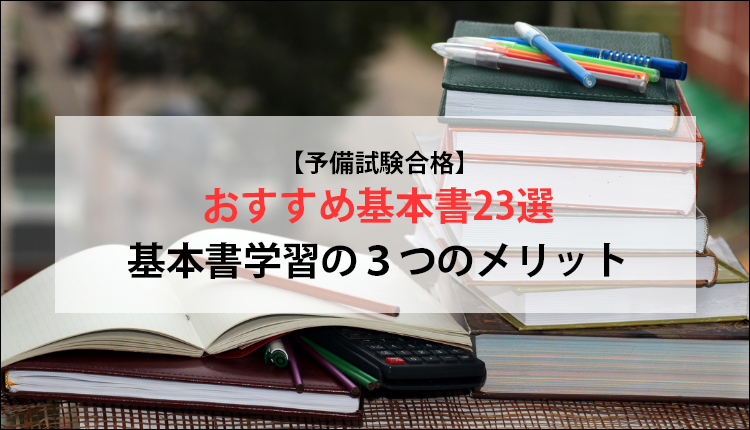
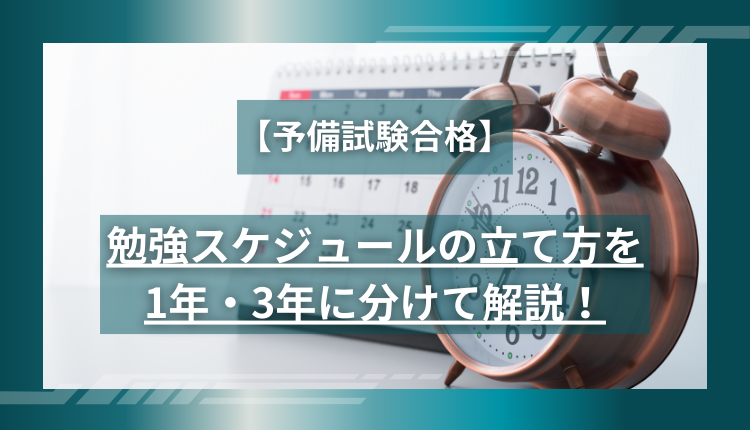
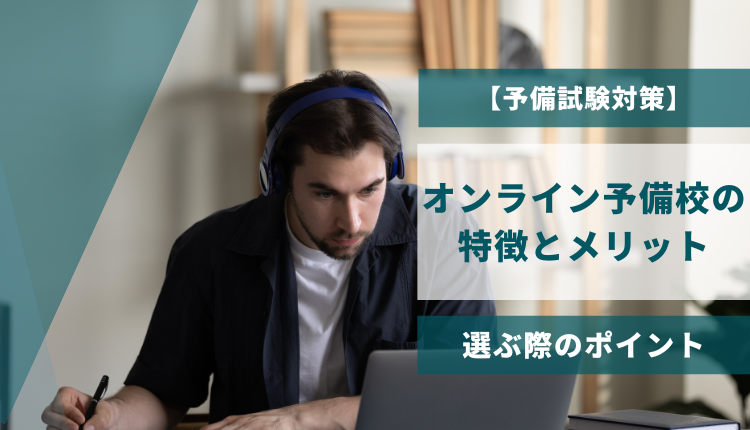
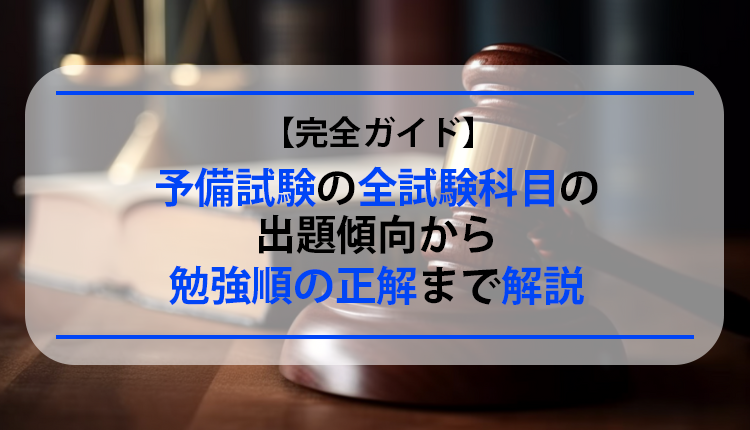

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。