【初学者必見】予備試験合格までの学習法6STEPとおすすめ入門書
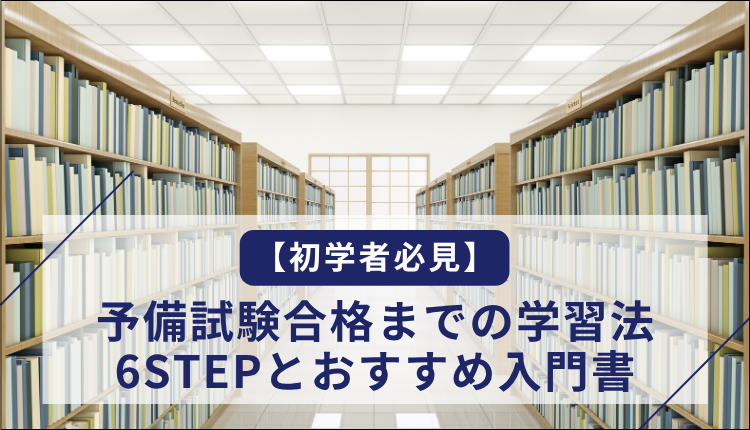
目次
この記事を読んで理解できること
- 【初学者向け】予備試験受験までの勉強スケジュール
- 初学者が予備試験合格を掴むための6STEP
- 【科目別】初学者におすすめの入門書
- 「ヨビロン」は初学者にもおすすめ
あなたは、
- 法律初学者でも予備試験に合格できるのか知りたい
- 初学者でも予備試験に合格できる勉強方法が知りたい
- 初学者におすすめの教材が知りたい
とお考えではありませんか?
予備試験は誰でも受験が可能なので、法律初学者でも受験を考えている方はいらっしゃるでしょう。
しかし、法学部出身者でも苦戦する難易度の高い試験に、初学者が本当に合格できるのか、不安に思う方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、正しい学習方法と計画的な取り組みを実践すれば、初学者でも予備試験合格は十分に可能です。
重要なのは、最初から正しい方向性で学習をスタートし、段階的に実力を積み上げることです。
この記事を読めば、初学者が予備試験合格を目指すための学習スケジュール、具体的な学習方法、科目別のおすすめの入門書が分かり、迷うことなく学習をスタートできるでしょう。
具体的には、
1章で初学者向けの予備試験受験までの勉強スケジュール
2章で初学者が予備試験合格を掴むための6STEP
3章で科目別の初学者におすすめの入門書
4章で初学者にもおすすめする「ヨビロン」
について、詳しく解説します。
初学者が今日から実践できる勉強法をご紹介するので、予備試験合格への第一歩として、ぜひ参考にしてください。
1章:【初学者向け】予備試験受験までの勉強スケジュール
一般的に、予備試験に合格するまでに必要な勉強時間は3,000~10,000時間と言われています。
特に法律初学者であれば、基礎知識の習得から実践力の養成まで十分な時間が必要です。
平均して1日5時間程度の勉強時間が確保できた場合でも、1年間で1、825時間なので、3~4年程度の学習期間が現実的なスケジュールとなります。
具体的には、
- 1年目は基礎固めと学習習慣の確立
- 2年目は過去問中心の実践演習と弱点克服
- 3年目は本試験対策の総仕上げ
という流れで進めると良いでしょう。
このように、現実的なスケジュールに基づいて着実に学習を進めることが、初学者が予備試験合格を掴むための第一歩となります。
さらに詳しい勉強スケジュールの立て方は、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
【予備試験合格】勉強スケジュールの立て方を1年・3年に分けて解説!
2章:初学者が予備試験合格を掴むための6STEP
初学者が予備試験合格を目指すなら、以下の6STEPで勉強を進めましょう。
- 【STEP1】過去問を見て出題のイメージを掴む
- 【STEP2】薄い入門書で全体像を把握する
- 【STEP3】基本書学習と過去問演習を並行して進める
- 【STEP4】過去問を繰り返し解き答案構成力を鍛える
- 【STEP5】答練や模試に参加し弱点を潰す
- 【STEP6】短答式直前は短答式対策を徹底する
それぞれ説明します。
2-1:【STEP1】過去問を見て出題のイメージを掴む
予備試験の学習を始める際は、まず過去問を見てゴールを確認しましょう。
何も分からない状態でも、最初に過去問を見ることで、必要な知識や試験での問われ方がイメージでき、その後の学習の方向性が定まります。
これは、マラソンでゴールの位置が分からないと、ペース配分ができないのと同じです。
具体的には、法務省のウェブサイトで公開されている直近の短答式と論文式の試験問題と出題の趣旨を確認してください。
また、市販の解説付き過去問集や合格者の答案例を活用して、答案のレベル感を見ておくのもおすすめです。
先に過去問を見ておくことで、自分の今の学習レベルとゴールの差を常に意識でき、モチベーションの維持にもつながります。
この後テキストを読む際にも、「これは試験でどう問われるのか」という視点を持てるので、学習効率が格段に上がります。
2-2:【STEP2】薄い入門書で全体像を把握する
ゴールのイメージがつかめたら、薄い入門書を読んで、各科目の全体像を把握することから始めましょう。
初学者がいきなり分厚い基本書を読むのはおすすめしません。
法律特有の表現や専門用語が難しく、挫折しやすいからです。
まずは入門書で「法律とはこういうもの」という感覚を掴んでから本格的な学習に進む方が、その後の理解がスムーズに進みます。
ただし、入門書を読む際は完璧に理解しようとせず、出来るだけ短時間でざっと一通り読むことを優先しましょう。
また、この段階で挫折しないためには、内容がやさしく、自分が興味を持って読み進められる入門書を選ぶことが大切です。
次の章で、科目別のおすすめ入門書を紹介するので、参考にしてください。
また、科目の学習順序については、以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも併せてご覧ください。
【完全ガイド】予備試験の全試験科目の出題傾向から勉強順の正解まで解説
2-3:【STEP3】基本書学習と過去問演習を並行して進める
入門書で全体像を把握できたら、基本書学習と過去問演習を並行して進めましょう。
基本書を全て読み切ってから過去問に取り組むと、最初の方に読んだ内容は記憶が薄れ、知識が定着せずに非効率です。
過去問で「何がどのように問われるのか」を確認しながら基本書を読むことで、必要な知識を効率的に習得できます。
進め方は、まず基本書の1つの章を読んだら、関係する条文を六法で素読し、条文の正確な文言を押さえます。
次に、その範囲の短答式過去問を解き、間違えた問題は基本書や条文を再度確認しましょう。
この流れを繰り返し行います。
さらに、早い段階から論文式過去問にも取り組んでください。
最初は、解説を読むだけでも構いません。
慣れてきたら、いきなり答案を書くのではなく、答案構成(論点を洗い出し書く順序を決める作業)を考えるところから始めましょう。
最初はなかなか答案を書けないかもしれませんが、この段階では「何を理解していないか」を明確にすることが重要です。
この方法により、基本書の通読だけでは自覚できない理解不足の部分を発見でき、記憶の定着も格段に向上します。
なお、おすすめの基本書については、以下の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
【予備試験合格】おすすめ基本書23選、基本書学習の3つのメリット
2-4:【STEP4】過去問を繰り返し解き答案構成力を鍛える
基本書を一通り終えたら、論文式の過去問を繰り返し解いて答案構成力を鍛えましょう。
短答式試験の直前期までは、短答式よりも論文式の対策を優先して取り組むことが重要です。
論文対策を徹底することで法的思考力が養われ、短答式にも自然と対応できる体系的な知識が身につくからです。
逆に、短答対策ばかりしていると表面的な知識の暗記に偏り、本質的な法的思考力が育たず、論文式試験で力を発揮できなくなります。
過去問を解く際はいきなり答案全文を書こうとするのではなく、論点の洗い出しと書く順序を決める答案構成から始め、模範解答と自分の答案構成を比較しましょう。
その後、間違えた論点や書けなかった論点は、必ず復習ノートにまとめ、該当する範囲の基本書、条文、判例を何度も読み込み理解を深めます。
過去問演習のさらに具体的なやり方については、以下の記事で解説しているので、参考にしてください。
【予備試験の過去問】演習する4つのメリットと、勉強法や過去問一覧
また、論文式試験の対策については、以下の記事でさらに詳しく解説しているので、こちらも併せてご覧ください。
【完全ガイド】予備試験論文対策|初学者のための3つの基本事項と核心技術
2-5:【STEP5】答練や模試に参加し弱点を潰す
一通り答案が書けるようになったら、予備校などが実施している答練や模試に参加し、客観的な評価を受けましょう。
そこで自分の弱点を明らかにし、それらを確実に潰していくことで、予備試験合格に向けて確実にレベルアップできます。
特に論文式試験は、自己採点では答案の質を正確に評価できないため、第三者の採点・添削を受けるのがおすすめです。
本番形式で練習することで、制限時間内で答案を書き切る力や試験独特の緊張感に対応する力も身につきます。
具体的には、年に2〜3回は模試を受験し、順位や偏差値から相対的な位置を確認しつつ、自分の答案と採点結果を丁寧に見直しましょう。
重要論点の見落としがないか、法的根拠は明確に示せているか、事実と法規範の関係が適切に論じられているかなど、自分の弱点を洗い出します。
その後、理解が不十分な部分について基本書・条文・判例を読み直し、類似問題を繰り返し解いて集中的に対策を行いましょう。
2-6:【STEP6】短答式直前は短答式対策を徹底する
ここまでは、論文対策中心の学習でしたが、短答式試験の直前期(試験2か月前~)になったら、短答式対策に集中しましょう。
短答式試験は予備試験の第一関門であり、ここを突破しなければ論文式試験に進むことができないからです。
また、短答式試験は知識の正確性が問われることも多いため、直前期の集中的な対策により得点力を大幅に向上させられます。
具体的な対策法は、短答式の過去問を繰り返し解くことです。
1周目はすべての問題を解きますが、2周目以降は理由も含めて十分に理解できていない問題だけを重点的に復習します。
そうすることで、効率的に得点力を上げることができます。
復習の際は、基本書や条文の該当箇所を再度読み込みましょう。
また、忘れかけたタイミングで見直すことを繰り返し、記憶の定着を図ることも重要です。
短答式試験の対策については、以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも併せてご覧ください。
【完全ガイド】予備試験短答対策|初学者のための3つの基本事項と最短合格法
3章:【科目別】初学者におすすめの入門書
初学者にとって、学習の始めに読む入門書選びは特に重要です。
以下では、予備試験で出題される法律基本7科目について、初学者が安心して使えるおすすめの入門書を科目別に紹介します。
3-1:憲法
- 著者:初宿正典、高橋正俊、米沢広一、棟居快行
- 出版社:有斐閣
- 頁数:280ページ(第7版)
内容紹介(出版社より):
はじめて憲法を学ぶ人に向けた入門書。小説、写真、新聞記事など具体的な素材を出発点として主要なテーマを解き、憲法の考え方を学ぶ。語りかけるようなわかりやすい叙述で読者を導く定番のテキスト。
- 著者:内山奈月、南野森
- 出版社:PHP研究所
- 頁数:256ページ
内容紹介(出版社より):
憲法を暗記しているアイドルと、気鋭の憲法学者による、1億人のための憲法学講義。投票の自由とは?有名人にプライバシーはある?
3-2:行政法
- 著者:藤田宙靖
- 出版社:有斐閣
- 頁数:326ページ
内容紹介(出版社より):
学生のときこんな話を聞いていたらはじめから行政法をもっとおもしろいと感じていただろう、という著者自身の思いを込め、抽象的でむずかしいといわれる行政法のあらましを、やさしい語り口で講義する。
- 著者:板垣勝彦
- 出版社:法律文化社
- 頁数:300ページ
内容紹介(出版社より):
コンパクトかつわかりやすい説明で、読み物として楽しく知識が身に付くテキスト。第2版では、行政法を取り巻く最新の判例・動向を反映、行政判例百選〔第8版〕・地方自治判例百選〔第5版〕に対応し、誤解されやすいポイント等の説明を補った。
3-3:民法
- 著者:道垣内弘人
- 出版社:日本経済新聞出版
- 頁数:784ページ
内容紹介(出版社より):
■■民法全体を1冊で網羅■■
「なぜそうなっているのか」を日常の言葉で徹底して解説した好評のロングセラー。財産法から親族法・相続法まで、民法全体を1冊で学ぶことができます。後のページを参照しないと理解できない従来の教科書の難点を克服し、その場で理解できるように構成を工夫しました。無理なく最後まで読み進められます。基本からしっかり理解したい初学者、資格試験受験者、再入門の社会人に最適の内容です。
- 著者: 窪田充見
- 出版社:弘文堂
- 頁数:272ページ
内容紹介(出版社より):
この本は契約法入門と題して、民法の案内もしちゃおうという少々欲張りな本です。これから民法を勉強しようかなと思っている人、本格的な勉強をする気はないけれど民法や契約のルールをちょっと知りたい人、どうぞ気軽に手に取って下さい。
3-4:会社法
- 著者:中東正文、白井正和、北川徹、福島洋尚
- 出版社:有斐閣
- 頁数:272ページ
内容紹介(出版社より):
会社法を、平易かつコンパクトに、そしてストーリーを交えながら解説するテキスト。叙述にメリハリをつけ、会社法全体をカバーしながらも重要事項は特に丁寧に説明。
- 著者:柴田和史
- 出版社:日本実業出版社
- 頁数:432ページ
内容紹介(出版社より):
株主総会、取締役会などの基本的なルールから、取締役の責任、株主有限責任の原則、ストックオプション、M&A、ポイズンピル、事業承継などまで解説。初めて学ぶ人はもちろん、より深く会社法を知りたい人が、考え方・原則をつかむために最適の入門書です。
3-5:民事訴訟法
- 著者:和田吉弘
- 出版社:商事法務
- 頁数:224ページ
内容紹介(出版社より):
絶大な支持を受ける『基礎からわかる民事訴訟法〔第2版〕』の概説書。法律事務所の職員の方、企業の法務部で訴訟を扱う方、法学部でまだ民事訴訟法を学習したことのない方などの初学者を対象に要点をおさえつつ、わかりやすく解説する。
- 著者: 越山和広
- 出版社:法律文化社
- 頁数:328ページ
内容紹介(出版社より):
令和4年民事訴訟法改正(民事訴訟手続のIT化等)に対応。法律家になるための基本的なスキルともいわれる要件事実論―当事者が裁判で証明すべき事実とは何か、原告・被告のいずれがどの事実の証明責任を負うのかなどを考える―も踏まえた事例と解説で、民事訴訟のルールだけでなく、民法と民事訴訟法の関係や訴訟の仕組みがよく分かる。
3-6:刑法
■「入門刑法学(法学教室ライブラリィ)」
- 著者:井田良
- 出版社:有斐閣
- 頁数:(総論)288ページ、(各論)290ページ
内容紹介(出版社より):
刑法学の面白さと奥深さを実感できる好評テキストの第2版。重要な法改正等や、姉妹書の『入門刑法学・各論〔第2版〕』とのクロスレファレンスにも対応した。刑法の基礎をしっかりと学びながら、中級・上級レベルまでの理解を目指す初学者必読のテキスト。
濃密な講義を聴く感覚で刑法各論の本質をつかむ、好評テキストの最新版。拘禁刑の創設や性犯罪処罰規定など、近時の重要な法改正に対応。より効率的に、より深く、「いかなる法益がどの限度で保護され、その理由はどこにあるか」を理解できる、手厚い“入門書”。
3-7:刑事訴訟法
- 著者:中川孝博
- 出版社:法律文化社
- 頁数:318ページ
内容紹介(出版社より):
アクティブラーニング型授業の新しいタイプの教科書。内容・構成・表示に工夫をこらし、初学者から司法試験の準備にも使える情報量を収載。講義動画をユーチューブにアップ、ウェブサイトにて基本的知識の理解・定着を助けるさまざまなシートを設定。反転授業、独習にも最適。
- 著者:緑大輔
- 出版社:日本評論社
- 頁数:372ページ
内容紹介(出版社より):
刑事訴訟法学習のつまずきやすいポイントをわかりやすく、丁寧に解説。基礎から応用までをフォローし、学習を強力にサポートする。
4章:「ヨビロン」は初学者にもおすすめ
初学者が効率的に予備試験合格を目指すなら、予備試験に特化した教材「ヨビロン」の活用もおすすめします。
そもそも予備試験は合格率4%前後の超難関であり、法学部で4年間学んだ者でも合格が困難な試験です。
参考書や問題集を一通りこなしていても、限られた試験時間内で、初見の問題に対応できない受験生が多いからです。
しかし「ヨビロン」は、試験本番で初見の問題にも確実に対応できる「客観的読解法」と「解法パターン」という独自のノウハウを提供しています。
「客観的読解法」は、問題文から出題者の真の意図や重要な論点を的確に見抜く技術です。
「解法パターン」は、どの論証を使うべきかを論理的に判断し、初見の問題でも迷うことなく効率的に解答する方法です。
これらは、実際に予備試験1桁順位合格を果たした講師のノウハウを体系化した「ヨビロン」独自のアプローチであり、他では決して学べません。
初学者は知識不足を補うために暗記学習に頼りがちですが、「ヨビロン」を活用することで、短期間で実践的な解答技術を身につけることが可能です。
基本的な知識習得と並行してこれらの技術を身につけることで、予備試験合格への最短ルートを歩むことができるでしょう。
まとめ:初学者が予備試験合格を目指すなら最初につまずかないことが肝心
初学者が予備試験合格を目指すなら、最初の学習方法の選択でつまずかないことが重要です。
例えば自分のレベルに合わない学習方法でスタートしてしまうと、法律への苦手意識が高まり、早期に挫折する可能性があります。
また、非効率な学習方法を選択すると、成果も感じにくく、後から誤った学習習慣を改めようとしても、膨大な時間を要してしまいます。
そのため、初学者が予備試験に向けた学習を始めるときは、特に以下の点を意識してください。
- 学習開始前に過去問を見てゴールを把握すること
- まずは薄い入門書で全体像をつかむこと
- 早期に過去問演習に取り組むこと
さらに、予備試験に特化した教材「ヨビロン」を活用すれば、1桁順位合格者のノウハウを体系的に学べるため、初学者でも効率的な学習が可能になります。
「客観的読解法」や「解法パターン」といった独自技術により、初見の問題にも対応できる実践的な解答力を短期間で身につけることができるでしょう。
今なら、以下のLINE登録により、「解法パターン」とその活用方法などを解説した動画が無料でご覧いただけます。
ぜひ、最難関試験合格への第一歩として、お役立てください。






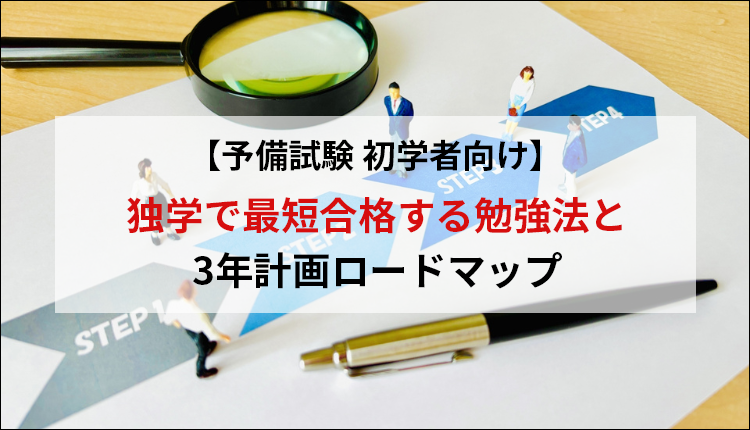
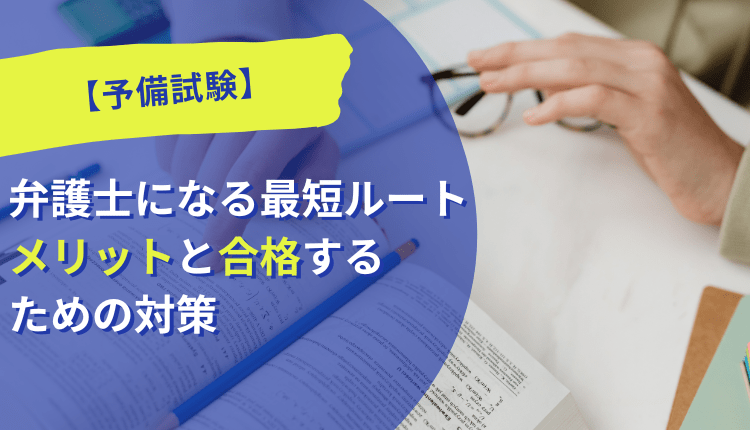
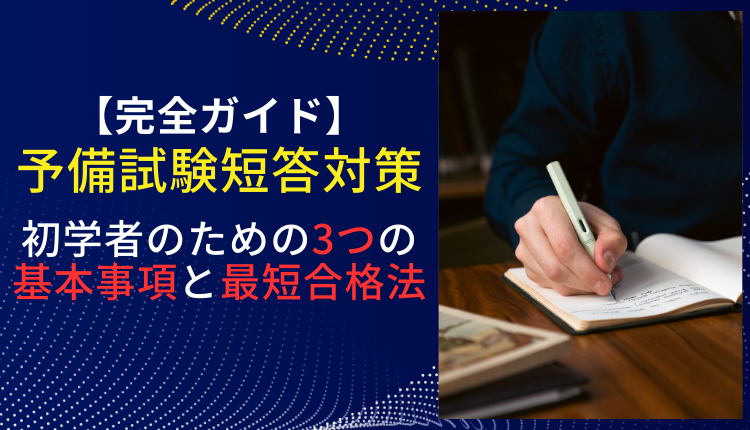
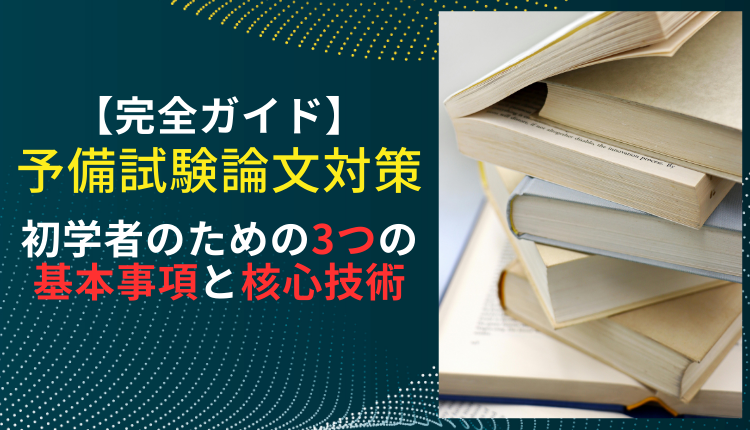
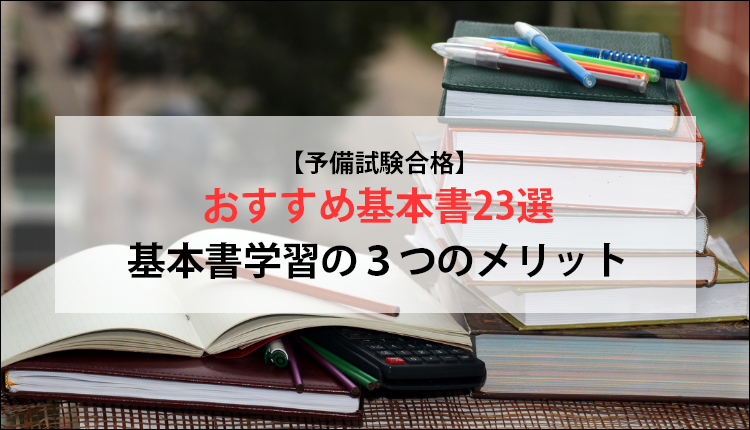
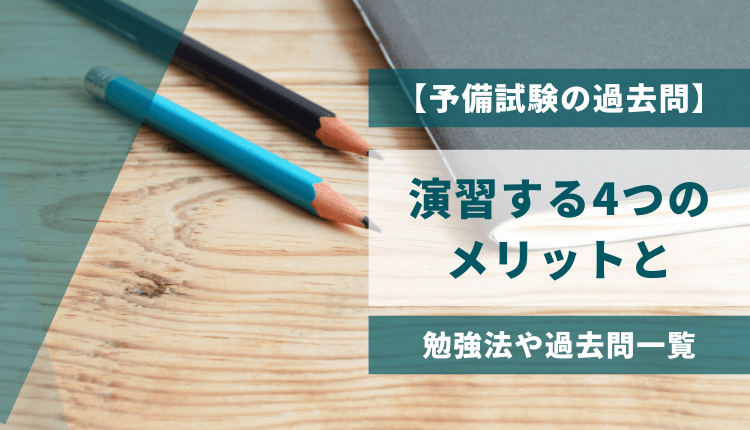

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。