【40代でも遅くない】予備試験合格への道|現実的な課題と3つの学習法
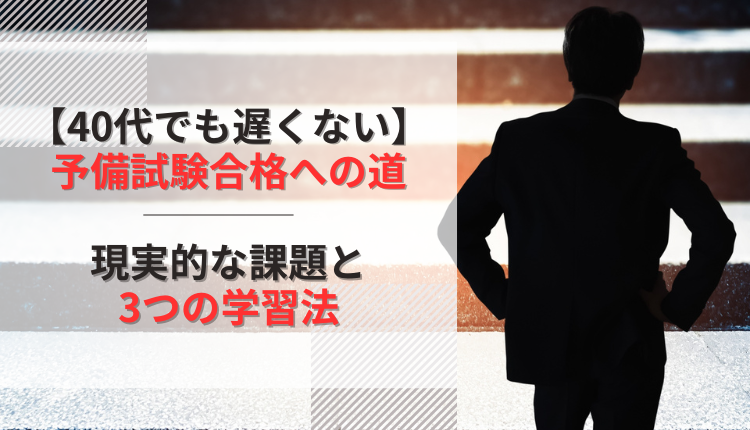
目次
この記事を読んで理解できること
- 40代でも予備試験挑戦は決して遅くない
- 40代受験生が直面する現実的な課題
- 40代からの予備試験挑戦にお勧めの学習法
あなたは、
- 40代でも予備試験に挑戦できる?
- 40代でも働きながら予備試験合格を目指したい
- 時間を有効に使って予備試験に合格する方法は?
などとお考えではありませんか?
結論から言えば、40代からの予備試験挑戦でも決して遅くありません。
40代からの予備試験受験は確かに難易度が高いものの、計画的な学習と効率的な時間管理を行うことで、合格の可能性を高められます。
令和6年の予備試験の結果では、40歳以上の合格者は最終合格者449人のうち41人と約1割を占めています。
※参照:法務省「令和6年司法試験予備試験口述試験(最終)結果」
そこでこの記事では、
1章で40代からの予備試験挑戦は決して遅くない
2章で40代受験生が直面する現実的な課題
3章で40代からの予備試験挑戦にお勧めの学習法
について詳しく解説します。
この記事を読んで、40代からの予備試験合格の難しさをしっかり認識し、有効な学習戦略と克服法を学び、目標達成のための行動を始めましょう。
1章:40代でも予備試験挑戦は決して遅くない
まずは、40代からの予備試験受験に関する重要な情報として、次の3つがあげ
られます。
- 予備試験の概要と司法試験合格への道のり
- 40代でも予備試験合格は就活で有利に働く
- 40代から弁護士を目指すメリット・デメリット
それぞれ解説します。
1-1:予備試験の概要と司法試験合格への道のり
予備試験の概要と司法試験合格までの道のりを見ていきましょう。
- 予備試験とは司法試験受験資格を得るための試験
- 予備試験の合格率約4%の実態
- 予備試験から司法試験合格までの道のり
それぞれ解説します。
1-1-1:予備試験とは司法試験受験資格を得るための試験
予備試験は、法科大学院修了程度の知識・能力を判定する試験です。
予備試験に合格すれば、法科大学院を経ずに司法試験を受験する資格が得られます。
この制度は、法科大学院への進学が難しい社会人や経済的な事情を抱える方々にも法曹への道を開くことを目的としています。
そのため40代以上の方にとっては、仕事を続けながら法曹を目指せる貴重な選択肢といえるでしょう。
また、予備試験は何歳でも挑戦できるうえ、合格すれば5年間いつでも司法試験を受験できます。
予備試験の詳しい情報は、以下の記事で解説しているので参考にしてください。
予備試験とは?その特徴や試験科目から合格率、対策の重要性を徹底解説
1-1-2:予備試験の合格率約4%の実態
予備試験の合格率は全体で約4%と、非常に厳しい現実があります。
令和6年度の予備試験では、最終合格率3.57%でした。
しかし、この数字は必ずしも40代からの挑戦が無理だということを意味するわけではありません。
令和6年の予備試験では、最終合格者数449人に対して、法科大学院生、それ以外の大学院生、大学生を除いた合格者数は162人となっています。
また、40歳以上の合格者は最終合格者449人のうち41人と約1割を占めています。
つまり、40歳以上でも合格できる可能性が十分にあるということです。
社会人としての経験と計画的な学習が組み合わさることで、合格の可能性は十分にあると言えるでしょう。
※参照:法務省「令和6年司法試験予備試験口述試験(最終)結果」
1-1-3:予備試験から司法試験合格までの道のり
予備試験に合格した後は、司法試験に挑戦することになります。
予備試験合格者の司法試験合格率は約90%と高く、多くの方が司法試験にも合格しています。
つまり予備試験で培った知識と解法テクニックは、司法試験でも大いに役立つことを示しています。
令和6年の司法試験では、法科大学院ルートの合格率が約34.8%だったのに対し、予備試験ルートの合格率は約92.8%と大きく上回っています。
一般的には、予備試験合格後、1年から2年の期間をかけて司法試験の対策を行い、合格を目指します。
40代の方でも、効率的な学習方法を採用すれば、十分に司法試験合格まで到達することが可能です。
1-2:40代でも予備試験合格は就活で有利に働く
40代で予備試験に合格し、さらに司法試験に合格した場合、就職活動においても年齢はデメリットばかりではありません。
むしろ、以下の点で有利に働くことがあります。
まず、これまでの職業経験が法律事務所でも評価されることがあります。
特に、前職で専門性を持っていた場合(金融、IT、医療、知的財産など)、その知識と法律知識を組み合わせることで、特定分野に強い弁護士として活躍できる可能性があります。
また、企業内弁護士(インハウスローヤー)としての道も開かれています。
企業は法務部門で実務経験と法律知識を兼ね備えた人材を求めており、40代のキャリアチェンジ組は貴重な存在となり得るからです。
社会人経験があることで、クライアントとのコミュニケーション能力や問題解決能力が高く評価されることも多いです。
法律知識だけでなく、実社会での経験を持つ法曹は、クライアントの問題をより深く理解できるためです。
また、予備試験合格者は、法科大学院卒業者と比較して高い確率で司法試験に合格できる点などが高く評価されます。
1-3:40代から弁護士を目指すメリット・デメリット
次に、40代から弁護士を目指すメリット・デメリットをそれぞれ解説します。
1-3-1:メリット|これまでのキャリアと専門知識を活かせる
40代から弁護士を目指す最大のメリットは、これまでのキャリアと専門知識を法律の世界で活かせる点です。
例えば、IT業界出身であれば、IT法務や知的財産権、金融業界出身であれば金融法務、医療関係者であれば医療過誤訴訟など、前職の知識を専門分野として確立しやすいです。
また、人生経験が豊富なため、クライアントの抱える問題や心情をより深く理解できるというメリットもあります。
若手弁護士にはない共感力や説得力を持つことができ、信頼関係の構築に有利です。
さらに、社会人としての人脈やネットワークを活かして、独立開業した際のクライアント獲得にも役立てることができます。
前職の同僚や取引先が最初のクライアントになるケースも少なくありません。
1-3-2:デメリット|年齢による制約と収入面
一方で、40代からの法曹キャリアには現実的な制約もあります。
まず、大手法律事務所への就職は難しい場合があります。
多くの大手事務所は若手弁護士の育成を前提としたキャリアパスを設計しているためです。
収入面では、弁護士としてのキャリアをゼロから始めるため、前職よりも収入が下がる可能性があります。
特に司法修習生時代や弁護士1~2年目は収入が限られることを覚悟する必要があります。
また、法曹資格取得までの期間(予備試験合格から司法試験合格、司法修習修了まで)は収入が大幅に減少する可能性があり、家庭を持つ40代にとっては大きな負担となることもあります。
2章:40代受験生が直面する現実的な課題
40代の社会人受験生は、学習面だけでなく様々な現実的な課題に直面します。
- 厳しい合格率の現実
- 仕事・家庭との両立における時間的制約
- 精神的プレッシャーと不安への対処
それぞれ解説します。
2-1:厳しい合格率の現実
40代以上の予備試験受験者が直面する最大の課題は、厳しい合格率です。
令和6年のデータによれば、40代以上の受験者は5,232人、そのうち合格者はわずか41人で、合格率は0.78%となっています。
※参照:法務省「令和6年司法試験予備試験口述試験(最終)結果」
この数字は非常に厳しい現実を示していますが、受験者の中には本格的な対策をせずに受験する方も含まれています。
予備試験に合格するためには、効率的かつ効果的な学習方法の採用、計画的な学習の継続、そして予備試験特有の出題傾向への対応が不可欠です。
つまり予備試験に特化した、合格のための専門的なアプローチを身につけることが重要です。
2-2:仕事・家庭との両立における時間的制約
40代の受験生にとって、仕事や家庭の責任と勉強を両立させることは大きな課題です。
フルタイムで働きながら十分な学習時間を確保することは容易ではありません。
多くの成功者は、早朝や昼休み、通勤時間などのスキマ時間を効果的に活用しています。
例えば、通勤時間に音声教材で学習する、昼休みに問題を解く、就寝前に30分でも復習するなど、日常の中に学習を組み込む工夫が必要です。
また、家族の理解と協力を得ることも重要です。
週末の数時間を集中学習の時間として確保したり、家族と学習計画を共有したりすることで、持続可能な学習環境を構築できます。
時間管理のテクニックとしては、ポモドーロ・テクニック(25分集中+5分休憩)の活用や、学習内容の優先順位付けなども効果的です。
限られた時間で最大の成果を出すために、「何を学ぶか」だけでなく「何を学ばないか」の選択も重要になります。
2-3:精神的プレッシャーと不安への対処
40代からの挑戦には精神的なプレッシャーがつきものです。
「もう歳だから」「若い人には勝てない」という不安や、家族を養いながらの挑戦による経済的なプレッシャーを感じることも少なくありません。
こうした不安への対処法として、まずは同じ境遇の仲間との交流があげられます。
オンライン上の勉強会やコミュニティに参加することで、悩みの共有や情報交換ができます。
40代以上の合格者の体験談に触れることも、モチベーション維持に役立ちます。
また、小さな目標を設定し、達成感を積み重ねていくことも大切です。
例えば、1週間で特定の科目の基本書を読み終える、過去問を5題解くなど、達成可能な目標を設定し、クリアしていくことでモチベーションを維持できます。
ストレス管理の面では、適度な運動、十分な睡眠、バランスの取れた食事など、基本的な健康管理も重要です。
学習効率を高く保つためには、心身の健康が前提となります。
3章:40代からの予備試験挑戦にお勧めの学習法
40代からの予備試験挑戦にお勧めの学習法として、次の2つがあげられます。
- 効率的な学習計画の立て方
- 予備試験に特化した論証集「ヨビロン」
それぞれ解説します。
3-1:効率的な学習計画の立て方
効率的な学習計画を進めていくためには、次の2つが重要です。
- 40代の学習特性に合わせた計画立案
- 進捗管理と定期的な計画見直し
それぞれ見ていきましょう。
3-1-1:40代の学習特性に合わせた計画立案
40代の学習者は、20代の学習者とは異なる特性を持っています。
一般的に記憶力は若い頃より低下していますが、理解力や経験に基づく判断力は高いことが多いです。
そのため、学習を進めていく中では、この特性を活かした学習計画を立てることが重要です。
具体的には、単純暗記よりも理解に重点を置く学習法が効果的です。
法律の条文や判例を闇雲に暗記するのではなく、その背景や意義、関連性を理解することで、記憶の定着度を高められます。
また、集中力の持続時間も考慮する必要があります。
長時間の学習よりも、短時間の集中学習を繰り返す方が効率的です。
例えば、1回の学習時間を45分~90分程度に設定し、複数回に分けて学習する方法が推奨されます。
学習計画の立案では、以下のポイントを押さえましょう。
- 長期目標と短期目標の設定:最終的な合格までのロードマップと、週単位・月単位の具体的な目標を設定する
- 優先順位の明確化:重要度と緊急度を考慮し、学習項目に優先順位をつける
- 継続可能な学習スケジュール:無理なく続けられる現実的な計画を立てる
- 弱点分野の把握と対策:自分の弱点を客観的に分析し、重点的に取り組む
3-1-2:進捗管理と定期的な計画見直し
しかし、合格を目指すためには、学習計画を立てただけでは不十分です。
定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を修正することが重要です。
特に40代以上の学習者は、仕事や家庭の状況が変化することも多いため、柔軟な対応が求められます。
進捗管理の方法としては、以下が効果的です。
- 学習日記やログの記録:毎日の学習内容と時間を記録する
- 定期的な自己テスト:学習した内容の理解度を確認する
- 月次の振り返り:1ヶ月の学習を振り返り、計画との乖離を分析する
- 3ヶ月ごとの計画見直し:学習の進捗状況や効果を踏まえ、計画を修正する
また、モチベーション維持のために、達成した目標を可視化することも大切です。
例えば、完了した科目や章にチェックを入れる、理解度を5段階で評価するなど、自分の成長を実感できる工夫をしましょう。
3-2:予備試験に特化した論証集「ヨビロン」
予備試験合格を目指すなら、予備試験特有の出題傾向に対応した教材を活用することが重要です。
その中でも「ヨビロン」は、予備試験に特化した論証集であり、合格を目指すための正しい対策としておすすめです。
「ヨビロン」の特徴は、予備試験1桁合格者が提唱する「客観的読解法」と「解法パターン」に基づいていることです。
この方法論は、従来の予備校で教えられている「論証パターン」の暗記とは異なるアプローチを取っています。
「客観的読解法」とは、問題文を客観的に分析し、出題者の意図を正確に読み取る技術です。
予備試験では、問題の出題趣旨が薄く、従来の方法では対応できない問題が出されることが多いため、この読解法が非常に重要になります。
「解法パターン」とは、問題に対する具体的な解答の手順を指し、初見の問題に対しても効率的に対応できる方法です。
これを身につけることで、「何を問われているか分からない」という状況に陥るリスクを減らせます。
予備試験と司法試験は出題傾向が異なるため、司法試験対策の教材だけでは十分ではありません。
予備試験特有の問題に対応するためには、予備試験に特化した教材と学習法を採用することが合格への近道となります。
まとめ:40代で予備試験合格を目指す方法
40代からの予備試験挑戦は、決して遅すぎることはありません。
むしろ、社会人としての経験や知識を活かすことで、若年層にはない強みを発揮できるでしょう。
ただし、40代の受験生にとっては非常に厳しい挑戦になるため、合格に向けては、以下の点を意識しましょう。
- 現実的な学習期間の設定:無理なく継続できる学習ペースを設定し、1~2年を目安に準備を進める
- 効率重視の学習アプローチ:「客観的読解法」や「解法パターン」など、予備試験特有の方法論を学ぶ
- 社会人経験を活かした学習:これまでの経験を法的思考に活かし、実務的な視点から法律を理解する
- 時間管理と優先順位付け:限られた時間を最大限に活用するため、重要な学習項目に集中する
40代からの挑戦には確かに困難もありますが、適切な方法と強い意志があれば、十分に合格可能性があります。
前職のキャリアと法律知識を組み合わせることで、独自の強みを持つ法曹として活躍する道が開かれるでしょう。
今日から具体的なアクションを起こし、一歩ずつ着実に前進していきましょう。






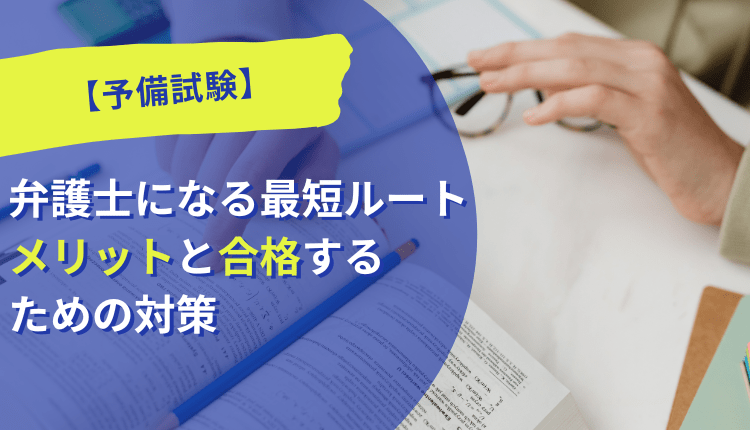
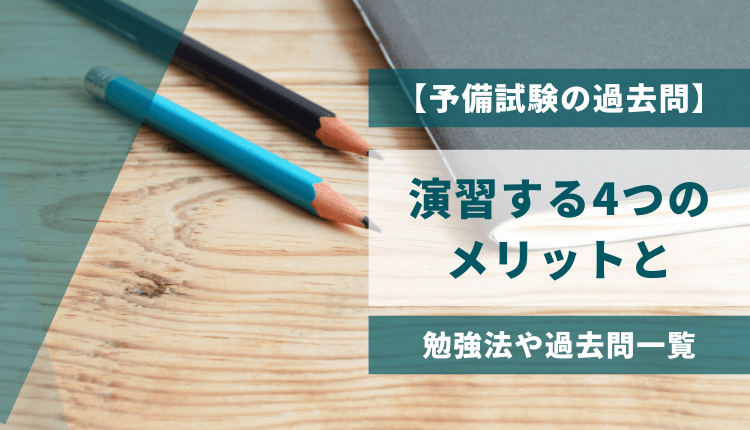

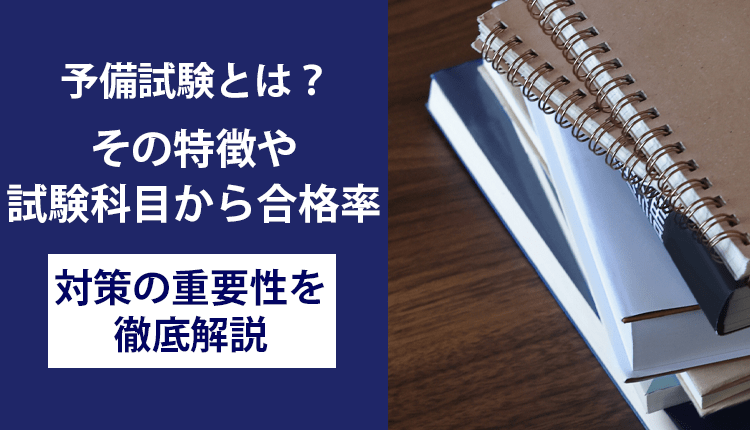
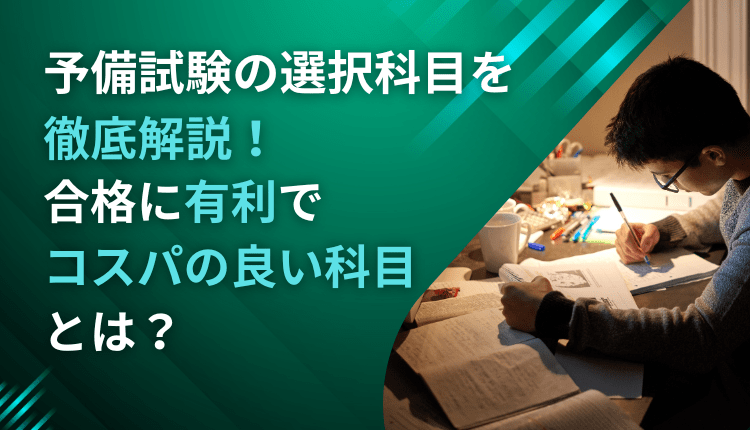
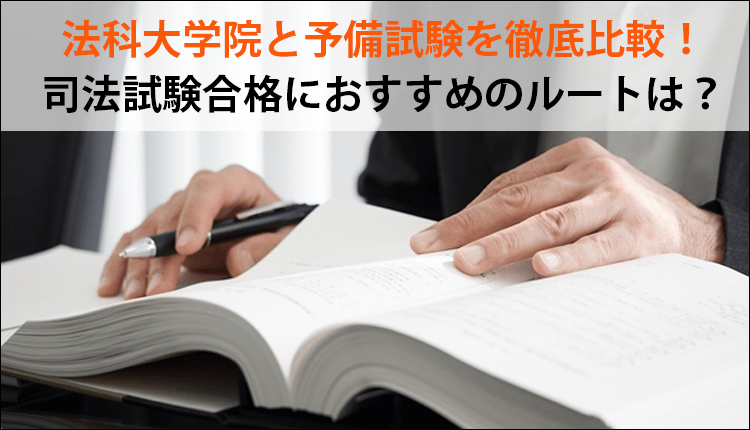

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。