【予備試験 初学者向け】おすすめの参考書20選と成果を出す5つのコツ
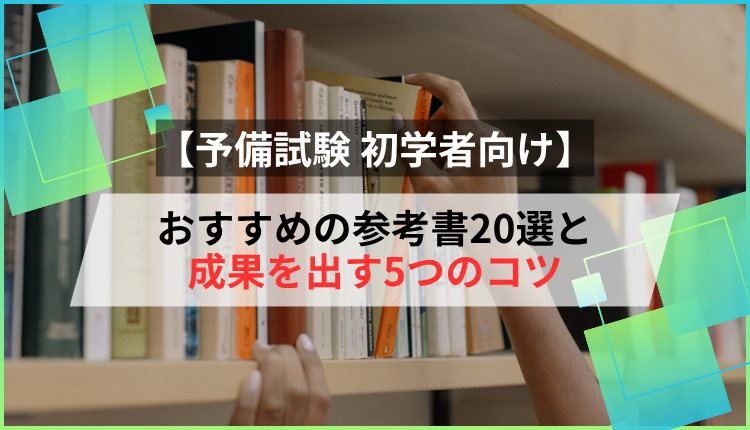
目次
この記事を読んで理解できること
- 予備試験初学者の参考書学習は3段階で進める
- 【段階別】予備試験初学者におすすめの参考書20選
- 予備試験初学者が参考書学習で成果を出す5つのコツ
- 参考書だけで不安な初学者にヨビロンをおすすめする4つの理由
あなたは、
「予備試験の勉強を始めたいけど、どの参考書を選べばいいのかわからない」
「初学者に最適な参考書の使い方や学習の進め方を知りたい」
このような悩みを抱えていませんか。
予備試験は司法試験への登竜門となる厳しい試験ですが、独学で挑戦しても十分合格を勝ち取ることが可能です。
しかし、法律を初めて学ぶ人にとっては、参考書の数が多すぎて「どれが本当に必要なのか」が分からず、最初の一歩でつまずいてしまうケースも少なくありません。
そこで、本記事では、「予備試験の受験勉強をこれから始める初学者」が、最短で成果を出すための参考書選びと学習法を徹底解説します。
まず、学習の進め方を3段階に分け、どの段階でどの種類の参考書を使えば良いかを整理した後に、各段階でおすすめの参考書20選を具体的に紹介します。
そして、参考書学習で確実に成果を出すための5つのコツをお伝えします。
さらに、参考書だけでは理解が難しいという方に向けて、予備試験上位合格者が監修するオンライン教材「ヨビロン」についてご説明します。
具体的には、
第1章では、予備試験初学者の参考書学習は3段階で進めることが良い理由
第2章では、各段階での予備試験初学者におすすめの参考書20選
第3章では、予備試験初学者が参考書学習で成果を出す5つのコツ
第4章では、参考書だけで不安な初学者にヨビロンをおすすめする4つの理由
を紹介します。
ぜひ最後までお読みいただき、効率的に合格を目指すための最強ロードマップとして、この記事を活用してください。
1章:予備試験初学者の参考書学習は3段階で進める
予備試験の学習にあたっては、いきなり難解な専門書に取り組むのではなく、「入門書→基本書→演習書」という3段階で進めることが最も効果的です。
この3段階のステップを踏むことで、法律の「全体像」→「理論」→「実践」という流れを自然に身につけることができ、短答式・論文式・口述式の全てに通用する基礎が形成されます。
ここでは、それぞれの段階での目的と学び方を具体的にご紹介します。
1-1:第1段階は入門書で法律の全体像を理解する
まず最初に手に取るべきは、「入門書」です。
入門書の目的は、
「法律とは何か」
「法の考え方とはどういうものか」
をイメージとして掴むことにあります。
予備試験は、憲法・民法・刑法・行政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法といった7科目を中心に構成されていますが、初学者がいきなり条文や判例集を読み込んでも理解が追いつきません。
そのため、まずは1冊の入門書を通じて、「法律の全体像」を俯瞰(ふかん)し、分野間のつながりをざっくりと把握することが大切です。
例えば、各科目においては、
憲法の入門書なら「各種人権や統治の概要」
民法の入門書なら「契約とは何か」「所有権とはどういう権利か」
といった身近なテーマを通じて全体を把握します。
また、刑法なら「構成要件など犯罪が成立するために必要な事項」を現実社会に照らし合わせて理解する姿勢が大切です。
この段階で重要なのは、「理解の正確さより、全体の概要やイメージを掴むこと」です。
具体的な条文や判例の細部は気にせず、まずは「こういう考え方があるんだな」と感覚的に理解するだけで十分です。
一見遠回りにも思えるかもしれませんが「木を見て森を見ず」にならないために欠かせない工程です。
1-2:第2段階は基本書で知識を体系的に深める
入門書で全体像を掴んだら、次のステップは「基本書」です。
基本書とは、各科目の法律知識を体系的に整理し、条文・判例・学説をバランス良くまとめた「学習の地図」のようなものです。
予備試験では、単なる知識の暗記ではなく、「条文を根拠にして考える力」が問われます。
基本書で条文の趣旨や論点の位置づけ、各論点の関係を体系的に理解することが、最大の関門である論文試験での得点力に直結します。
例えば、
憲法なら「表現の自由と公共の福祉」
民法なら「債権の履行と解除」
刑法なら「構成要件該当性、違法性阻却事由や故意・過失の判断基準」
といった論点を、基本書で体系的に整理しておくことが重要です。
このとき、条文の番号や判例名を丸暗記するのではなく、「なぜその結論になるのか」という理由づけを意識しながら読み進めることがポイントです。
基本書は全ページを読み込む必要はなく、最初は章末のまとめや重要論点だけを拾い読みして、概要を掴む程度でも構いません。
理解が深まってきた段階で、気になった部分を辞書のように調べる形で活用していくと効率的です。
1-3:第3段階は演習書で実践的な答案作成力を磨く
基本書で法律の理論を理解したら、次は「演習書」で実践力を養います。
予備試験の論文式では、「どのように論理を組み立てるか」が最も重要です。
演習書では、実際の事例などが紹介されており、それぞれの事例をもとに「どの条文を使うか」「どのような思考過程で検討するか」が説明されています。
演習書で学習することで、実際の出題の趣旨に沿った答案を作成する訓練ができます。
ここでのポイントは、初学者は、最初から完璧な理解や思考過程を目指す必要はないということです。
まずは「自分ならこう考える」という思考を紙に出すことから始め、演習書の説明と比較して不足している論点を確認していきましょう。
こうした繰り返しの中で、
「論点を発見する力」
「条文を当てはめる力」
「結論を導く力」
が自然と身につきます。
また、演習書を使うタイミングは、基本書を1周読み終えた後がおすすめです。
知識の土台がないまま演習に入ると混乱しますが、理論が理解できていれば、演習問題が「自分の考えを整理する練習」に変わります。
最終的には、入門書・基本書・演習書を段階的に使い分けることで、法律初学者でも無理なく予備試験の合格レベルに到達できるのです。
2章:【段階別】予備試験初学者におすすめの参考書20選
参考書選びで最も重要なのは、「どの段階で何を使うか」を明確にすることです。
多くの初学者が陥りやすい失敗は、最初から難易度の高い基本書や演習書に手を出してしまうことです。
その結果、理解が追いつかず、途中で挫折してしまうケースが非常に多く見られます。
そこでこの章では、予備試験合格者の実践例を踏まえながら、学習段階ごとに最適な参考書を紹介します。
段階を踏んで学ぶことで、無理なく知識を積み上げ、論文試験にも対応できる「法的思考力」を養うことができます。
2-1:第1段階|初学者向け入門書7科目分のおすすめ
入門書は、法律の「全体像」を理解し、初めての学習を円滑にスタートさせるための最初のステップです。
1冊あたり数日〜1週間程度で一通り読むのを目安として、完璧に理解しようとせず、「なるほど、法律ってこう考えるのか」という感覚を掴むことを目標にしましょう。
ここでは、各主要7科目(憲法・民法・刑法・行政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法)を中心に、初学者でも読みやすく、図表や事例を多く取り入れた良書を紹介します。
元最高裁判所裁判官の著者が、実務経験を踏まえて憲法全体を分かりやすく解説した一冊です。
学説と判例のバランスが良く、憲法の構造を体系的に理解できます。初めて憲法を学ぶ人でも、全体像を掴みやすい構成となっています。
民法総則の理解に必要な債権法や物権法の内容にも踏み込み、法分野のつながりを自然に学べる良書です。
豊富な具体例が掲載されており、初学者でも条文のイメージを掴みやすい構成になっていて、民法学習の第一歩に最適です。
物権法を学ぶ際に重要な「具体的なケース想定」を重視して解説した入門書です。
身近な例を用いた説明が多く、初めて法律を学ぶ大学生や初学者にも分かりやすい内容です。
理屈よりも実感として理解を深めたい人におすすめです。
抵当権など複数当事者の法律関係を扱う担保物権法が、図表を用いて丁寧に整理されています。
複雑な関係を視覚的に理解でき、苦手意識を持ちやすい初学者でもスムーズに学べます。
体系的理解と全体像の把握に優れた一冊です。
債権総論と債権各論を一冊にまとめ、全体像を俯瞰できる構成となっています。
各論から総論へと流れるように説明が展開され、具体的な事例を通して理解が深まります。
債権法を効率良く学びたい初学者に最適です。
・『入門刑法学・総論』『入門刑法学・各論』(法学教室ライブラリィ/有斐閣)
刑法の基本理論を、判例と学説の両面から丁寧に解説した入門書です。
法学部生や法科大学院生を対象とした法律雑誌である「法学教室」の人気連載「ゼロからスタート☆刑法“超”入門講義」を書籍化したもので、読みやすく、初学者が刑法の枠組みを理解するのに最適です。
商法全体をコンパクトに整理し、商法総則・商行為法・会社法を一冊で学べる構成となっています。
特に会社法の説明が充実しており、司法試験・予備試験の頻出分野の理解に役立ちます。
商法の全体像を掴みたい初学者におすすめです。
行政法を初めて学ぶ人向けに、行政手続・行政行為を身近な事例を使って説明してくれている良書です。
抽象的な概念を具体的にイメージできるよう設計されており、行政法特有の用語も自然に理解できます。
初学者の導入書として非常に優れています。
民事訴訟法の全体像を図表で整理し、手続の流れを体系的に理解できる一冊です。
章末には確認問題があり、読んだ直後に理解をチェックできます。
理論と手続の両方をバランス良く学びたい初学者に最適です。
・『コンパクト刑事訴訟法(コンパクト法学ライブラリ)』(新世社)
刑事訴訟の手続を中心に、理論・判例・実務を一体的に学べる構成となっています。
元刑事裁判官である著者が実務経験を交えて解説しており、条文の運用イメージを掴みやすい内容です。
刑事訴訟法を初めて学ぶ人に最も適した入門書です。
2-2:第2段階|初学者が使いやすい基本書7科目分のおすすめ
入門書を一通り終えたら、次は「基本書」です。
基本書は、条文・判例・学説を体系的に整理した構成が特徴です。
予備試験における論文対策に直結する、中核的な参考書として位置づけられます。
基本書は1冊に絞って使うのが原則です。
複数を並行して読むよりも、1冊を繰り返し参照し、理解を深める方が圧倒的に効果的です。
ここでは、各主要7科目(憲法・民法・刑法・行政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法)を中心に、初学者が使いやすい基本書をご紹介します。
憲法Ⅰ(総論・統治)と憲法Ⅱ(人権)で構成され、憲法の基本構造を体系的に理解できる教科書です。
判例と学説の両面から丁寧に整理されており、憲法学の基礎をしっかりと身につけたい初学者に最適です。
理論だけでなく、実際の裁判例を通じて憲法の考え方を学ぶことができるものおすすめです。
民法全体の要点を一冊に凝縮した定番テキストです。
条文数の多い民法を体系的に整理し、各分野の重要論点を明快に解説してくれています。
文章が平易で読み進めやすく、法学部生から予備試験受験生まで幅広く活用されています。
「基本刑法Ⅰ(総論)」と「基本刑法Ⅱ(各論)」の2冊で構成されています。
総論では因果関係・共犯など刑法の理論的基礎を最新判例を交えて分かりやすく解説されており、各論では、性犯罪や拘禁刑の法改正、重要判例を踏まえて内容が全面的に見直され、より明快な構成になっています。
初学者が刑法を理論と実務の両面から学べるバランスの取れた基本書です。
行政法分野の定番教科書として高い人気を誇る一冊です。
日常生活ではなじみの薄い行政手続や行政行為を、豊富な具体例とともに分かりやすく解説しています。
最新の判例や制度改正にも対応しており、初めて行政法を学ぶ人でも理解しやすい構成です。
理論と実務の双方から会社法を深く理解できる、スタンダードな基本書です。
法改正や最新の重要判例を反映し、企業法務やM&Aなどの実務トピックにも対応しています。
初学者にも読みやすい構成で、商法・会社法の中核的内容を確実に理解することができます。
刊行以来、多くの受験生・実務家から支持されている定番テキストです。
民事訴訟法の全体像を分かりやすく整理し、手続の流れを体系的に理解できる人気の基本書です。
改訂版では民法改正や最新判例に対応し、図表やチャートが多数収録されています。
複雑な訴訟手続を視覚的に学べるため、初学者でもスムーズに理解が進みます。理論と実務を両立して学びたい受験生におすすめです。
基礎から実務レベルまで対応する、法曹三者・研究者による本格的な基本書です。
豊富な図表・書式・法廷場面の再現や「基本事例」を通じて、訴訟手続の流れを具体的に理解できます。
手続と論点の関係を整理しながら、判例と学説の考え方を体系的に学べる構成となっており、刑事訴訟法を理論と実務の両面から学びたい初学者に最適です。
2-3:第3段階|初学者でも取り組める演習書のおすすめ
最後は、実践力を養うための「演習書」です。
演習書の学習では「正解を覚える」ことよりも、「どのように考えたか」を意識することが重要です。
演習書の説明と自分の思考過程を比較し、抜けている論点や論理展開を修正していくことで、確実に実践力が伸びていきます。
また、演習書で事例を検討する際には、条文や判例を使って論理的に考える習慣を身につけましょう。
ここでは、特にコアとなる3科目(憲法・民法・刑法)を中心に、初学者が使いやすい演習書をご紹介します。
問題の事例を複数の判例を用いて解説しており、「判例を使って答案を作る」感覚を養うことができます。
憲法の主要判例を多角的に分析し、相互の関係性や理論的背景を理解できる演習書です。
憲法の思考力を鍛えたい初学者におすすめの1冊です。
刑法の定番演習書として多くの受験生に支持されている一冊です。
頻出の論点を網羅し、実際の出題傾向に近い事例が多数掲載されています。
複数の論点が絡み合う事例を通じて、答案構成力と法的分析力を養うことができます。
民法の総則から親族・相続法まで、司法試験・予備試験の重要論点を幅広く網羅した演習書です。
判例をベースにした実戦的な事例が豊富に掲載されており、問題の分量も実際の試験設問に近い構成です。
3章:予備試験初学者が参考書学習で成果を出す5つのコツ
参考書をどれだけ揃えても、使い方を間違えると成果は出ません。
多くの初学者が陥るのは、「新しい本に次々手を出す」「読んだだけで満足してしまう」という学習の「迷走」です。
予備試験において重要なのは、参考書を「読み切ること」ではなく、「使いこなすこと」です。
そこで、ここでは、参考書学習で確実に成果を上げるための5つのコツを解説します。
3-1:1冊の参考書を繰り返し読み完璧にする
合格者が口を揃えて言うのが、「1冊を完璧にすれば十分」という言葉です。
初学者ほど複数の本に手を出したくなりますが、理解が浅いまま別の本を読んでも知識が定着しません。
大切なのは、1冊を何度も繰り返して読むこと。
あなた自身の「座右の1冊」を決め、1周目はざっと通読し、2周目で理解を深め、3周目以降で条文や判例を整理しながら読めば、自然と頭に残ります。
「わからない箇所をすぐに調べない」「全て理解しようとしない」こともポイントです。
わからない部分や理解できない部分があっても、まずは全体像を掴み、次の読み込みで詳細を補う方が効率的です。
一度で完璧に理解しようとすることよりも「繰り返し」を優先させることが、長期戦を勝ち抜く学び方です。
3-2:参考書は科目ごとに絞り込む
参考書は科目単位で絞り込むようにしましょう。
同じシリーズの本であっても、科目よっては、読みやすさなどが異なります。
そのため、「民法では、この参考書が読みやすかったので全科目そのシリーズにしよう」とするのではなく、「民法はこの参考書が読みやすい」「刑事訴訟法はこの参考書が自分に合っている」など科目ごとに最適な参考書を選ぶことが大切です。
また、「幅を広げる」より「理解を深める」ことが大切です。
複数の本を同時に進めると、語彙や整理軸の違いで同義概念が別物に見え、似て非なる記述の差に振り回されやすくなります。
結果として非効率となり、合格までの道のりが遠くなってしまいます。
3-3:基本書は通読より辞書的な使い方を重視する
基本書は、全てを最初から最後まで通読する必要はありません。通読にこだわると、内容が抽象的で理解が追いつかず挫折しやすくなります。
逆に、辞書のように必要な部分だけを調べる使い方の方が、効率的で定着しやすいです。
例えば、演習書で「意思表示の瑕疵」という問題が出てきたとき、民法の基本書で該当箇所を確認し、条文・判例・学説を整理します。
このように「問題を解く→基本書で理論を確認する」というサイクルを繰り返すことで、知識が「使える形」で定着します。
参考書は、予備試験に合格するためのツールとして、ゴールを見据えて使用することが重要です。
3-4:演習書の反復学習で知識の定着を図る
演習書は、参考書学習の「仕上げ段階」です。
一度理解して終わりではなく、同じ事例での思考過程などを3回以上繰り返すことが大切です。
1回目は「考え方を理解する」
2回目は「答案構成を再現してみる」
3回目で「条文を根拠に自分の言葉で書く」
ことを意識します。
このサイクルを続けることで、知識が定着し、論文式試験で自然にアウトプットできるようになります。
また、演習を重ねるうちに「この論点はよく出る」「この条文は頻出だ」といったパターンが見えてきます。
これを自分なりに整理しておくことで、試験直前の総復習にも役立ちます。
3-5:判例と条文を参考書と併せて確認する習慣をつける
予備試験では、条文を根拠にした論理的思考が問われます。
どんなに参考書を読んでも、条文そのものを理解していなければ、正しい結論を導くことはできません。
そのため、学習中は必ず「条文を開きながら読む」ことを習慣化しましょう。
特に、判例の結論や理由づけを読む際には、「この判断の根拠はどの条文なのか」を確認します。
また、参考書の本文に登場する重要判例には、付箋を貼ったり、要旨をまとめておくと便利です。
この習慣を続けることで、条文・判例・学説が頭の中で結びつき、論文試験で「使える知識」として活きてきます。
4章:参考書だけで不安な初学者にヨビロンをおすすめする4つの理由
ここまで紹介した参考書だけでも、独学で予備試験合格を目指すことは可能です。
しかし、初学者にとって最大の壁は「理解が浅いまま進んでしまうこと」です。
特に論文試験では、参考書の知識を「どう使うか」が問われるため、単なる読書では対応しきれません。
そこでおすすめしたいのが、予備試験上位合格者が監修したオンライン教材「ヨビロン」です。
「独学+ヨビロン」の組み合わせは、コストを抑えつつ、最短で成果を出す理想的な学習モデルです。
その理由を4つの観点から解説します。
4-1:講義動画が初学者の理解を強力にサポート
ヨビロンは、すべての講義がオンライン動画で提供されており、初学者でも直感的に理解できる構成になっています。
難しい条文や学説も、図解や具体例を交えて解説されるため、「読むだけでは分からなかった部分」がスッと理解できます。
また、動画講義は比較的短く区切られているため、通勤や昼休みなどのスキマ時間にも視聴可能です。
忙しい社会人や学生でも、時間を効率的に利用して学習を継続しやすいのが大きな強みです。
4-2:予備試験1桁合格者の独自ノウハウが得られる
ヨビロンの最大の魅力は、実際に予備試験で1桁順位に入った合格者の思考法や勉強法をそのまま学べる点です。
単なる知識のインプットではなく、
「どの論点を優先的に学ぶべきか」
「どのように答案構成を組み立てるか」
といった、合格に直結するノウハウが詰まっています。
初学者が最も苦労する「勉強の方向性の迷い」を解消し、限られた時間で最短距離を進むことができるのです。
4-3:初見の問題でも確実に点が取れる思考力が養える
予備試験の難しさは、「過去問と全く同じ問題が出ない」ことにあり、実際の試験の場での思考力が問われます。
そのため、条文や判例を「覚えるだけ」では限界があります。
ヨビロンでは、未知の事例にも対応できる「法的思考力」を鍛えるカリキュラムを採用しており、どんな問題でも「条文を軸に論理を組み立てる型」を自然と身につけられるため、本番でも安定した得点を取れる力が養われます。
4-4:スキマ時間でも活用できるオンライン教材
ヨビロンは、スマホ・PC・タブレットに完全対応しており、通勤電車やカフェ、寝る前の10分でもすぐに学習を再開できる仕様です。
また、進捗管理も充実しており、「今日はどこまで進めれば良いか」「どの分野を復習すべきか」が一目で分かります。
「学ぶ時間がない」「継続できない」という悩みを解決し、参考書学習をサポートする強力な味方となるでしょう。
まとめ:予備試験初学者は参考書を段階的に活用しよう
予備試験に合格するために必要なのは、才能でも特別な環境でもなく、「正しい順番で学ぶこと」です。
入門書で全体像を掴み、基本書で理論を整理し、演習書で実践力を磨く。
この3段階を踏めば、法律初学者でも確実に合格レベルに到達できます。
そして、理解が追いつかない箇所は、ヨビロンのようなオンライン教材を併用することで、知識を「使える力」へと変えていくことができます。
参考書はあなたの努力を支える最良の武器です。
「読んで終わり」ではなく、「繰り返して使う」ことで、必ず結果は出ます。
ポイントは、焦らず、段階的に進めること。
それが、法律初学者が予備試験合格へ最短で到達するための最強の学習戦略です。






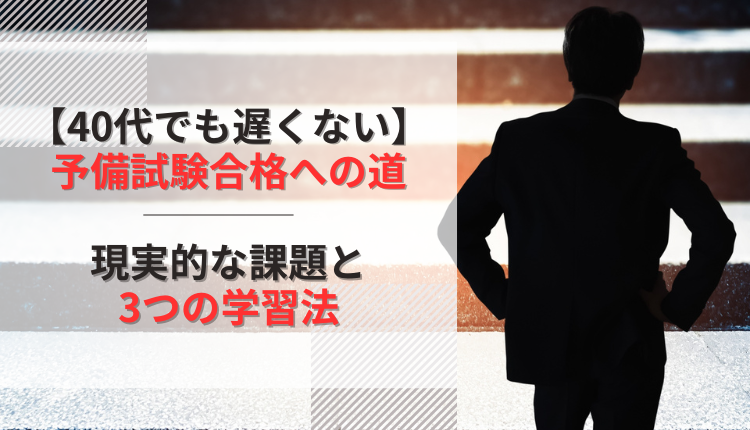
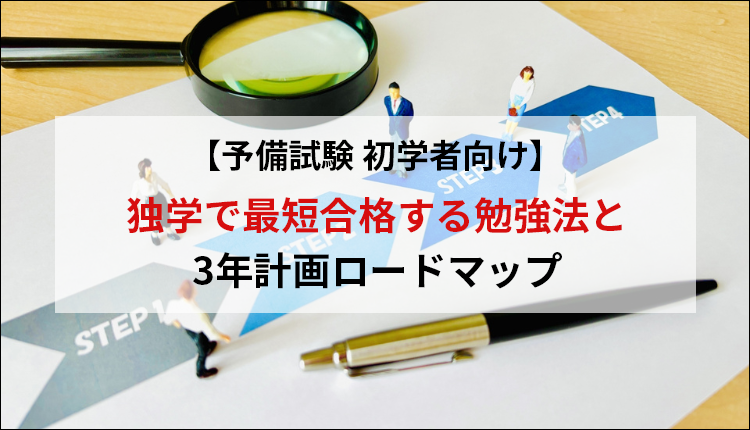
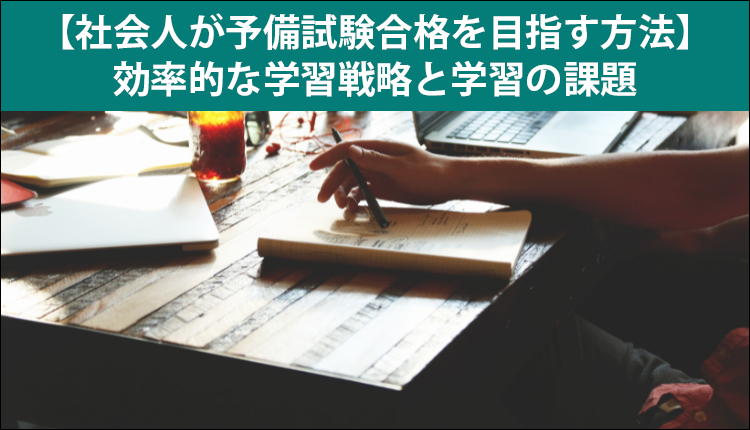
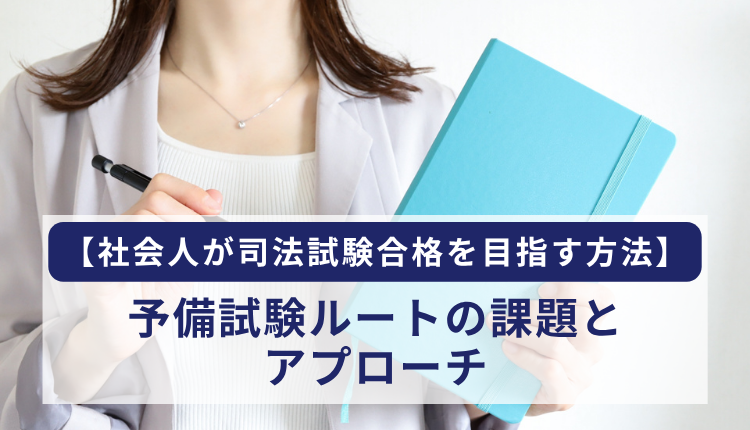
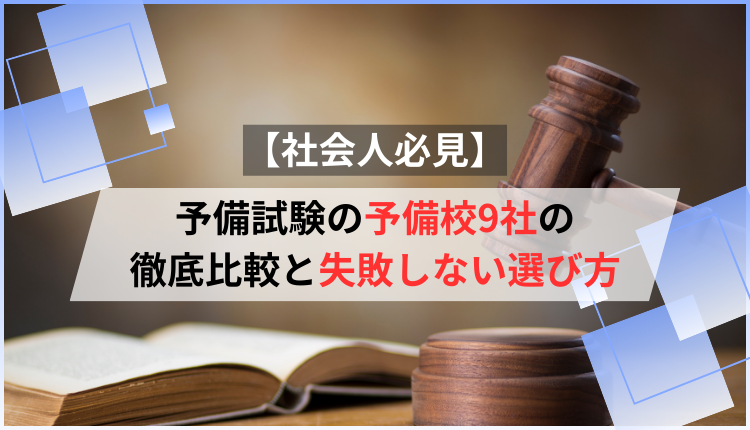
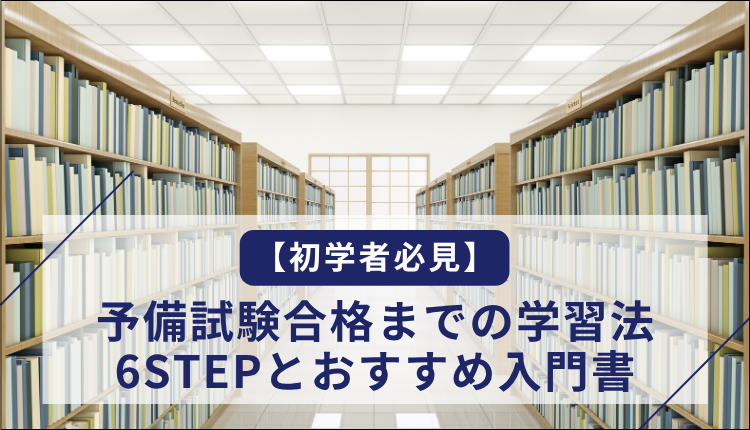

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。