【法律初学者向け】予備試験受験のメリット・デメリット|3つの対策法
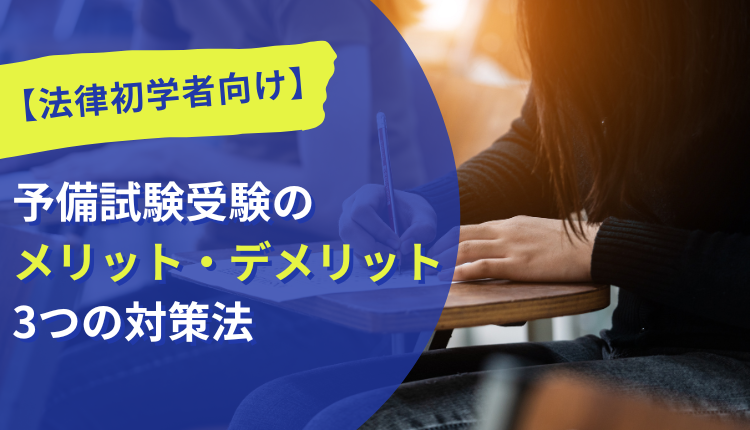
目次
この記事を読んで理解できること
- 法律初学者が予備試験を選ぶ4つのメリット
- 法律初学者が直面する予備試験の3つのデメリット
- 初学者が予備試験合格するための3つの対策法
- 予備試験合格を目指す初学者には「ヨビロン」をおすすめします
あなたは、
「法律初学者が予備試験を受験するメリットとデメリットを知りたい」
「法律知識ゼロの初学者でも予備試験に合格できる効率的な学習方法を見つけたい」
こんな悩みを抱えていませんか?
予備試験は、司法試験への登竜門として注目される一方で、合格率はわずか4%前後です。
挑戦する価値がある試験であると同時に、無計画に取り組むと挫折につながりやすい厳しい試験です。
そこで、本記事では、法律初学者が予備試験を受けるメリットとデメリットを具体的に整理し、さらに合格可能性を高めるための3つの対策法を紹介します。
最後には、予備試験合格を目指す受験生に特におすすめのオンライン教材ヨビロンについてご紹介します。
具体的には、
1章では、法律初学者が予備試験を選ぶ4つのメリット
2章では、法律初学者が直面する予備試験の3つのデメリット
3章では、初学者が予備試験に合格するための3つの対策法
4章では、予備試験合格を目指す初学者に「ヨビロン」がおすすめな理由
をご紹介します。
「予備試験に挑戦するべきか迷っている」
「効率的に合格する方法を知りたい」
という方にとって、進路を決めるうえでの道しるべとなる完全ガイドですので、ぜひ最後までお読みください。
1章:法律初学者が予備試験を選ぶ4つのメリット
予備試験は司法試験への関門であり「難関試験」として広く知られています。
しかし、法律初学者にとっては、実は大きなチャンスが隠されている試験でもあります。
ここでは、法科大学院ルートと比較したときの経済的メリット、自分のペースで学習を進められる自由度、司法試験合格に直結する圧倒的な実績、そして資格取得後の多様なキャリア展望という4つの観点から、その魅力を具体的に解説します。
1-1:法科大学院ルートより約300万円安く法曹を目指せる
司法試験を受験するルートには法科大学院を修了する「法科大学院ルート」と予備試験を合格する「予備試験ルート」があります。
法科大学院は私立であれば、年間100万〜150万円、国公立でも80万円前後の学費がかかり、3年間で合計300万〜450万円ほどの費用が必要です。
学費を奨学金でまかなえば、卒業後も長期にわたり返済を続ける必要があります。
一方、予備試験ルートでは、必要なのは受験料・参考書・模試・通信講座などの費用で、全体の出費は数十万円〜100万円程度に抑えられます。
社会人であれば働きながら受験を目指せるため、収入を得ながら挑戦できるのも大きな利点です。
「法曹資格を取りたいけれど学費がネック」という人にとって、予備試験はまさに現実的な選択肢といえます。
予備試験合格を目指すことで、費用面でのハードルが下がるため、より多くの人に法曹への扉が開かれます。
1-2:自分のペースで3,000時間の学習計画を立てられる
予備試験合格に必要な勉強時間は3,000〜10,000時間とされています。
これは1日3時間勉強しても3年以上かかる計算です。
法科大学院では授業に合わせて学習ペースが決まりますが、予備試験は自分自身で主体的に決められます。
つまり、社会人や子育て中の人でもライフスタイルに合わせて計画を柔軟に組めるということです。
例えば、社会人受験生の場合には、通勤電車で短答式の演習、昼休みに判例確認、帰宅後は論文構成練習といった形で自由に学習計画を立てられます。
こうした学習スタイルの自由さがあると、学習を「生活に組み込む」ことが可能になるのです。
結果として無理なく学習を継続でき、独学でも長期的に取り組む土台が築けるでしょう。
1-3:司法試験合格率98%の最短ルート
予備試験の合格者は司法試験に進むことができますが、その合格率は、年度によっては98%前後という驚異的な数字です。
これは、予備試験が司法試験と同等レベルの知識と実力を要求しているため、予備試験を突破できれば司法試験でも十分戦える力が身についているからです。
言い換えれば、予備試験を突破する過程そのものが、司法試験に直結する総合力を養成することになりますので、予備試験の学習を進めれば、同時に司法試験合格のための学習も進めることができるということです。
こうした効率の良さが、司法試験での合格率が非常に高い(年度によっては約98%)という実績につながっています。
以上から、予備試験合格は、司法試験合格にほぼ直結する「最短ルート」といえます。
時間やコストを最小限に抑えて法曹を目指したい人にとって、予備試験は極めて合理的な選択肢です。
1-4:幅広いキャリア選択が可能
予備試験合格は、単に司法試験受験資格を得るだけではありません。
合格自体が大きな実績となり、幅広いキャリアの選択肢を得ることになります。
例えば、以下のような活用方法があります。
- 企業法務部での活躍(M&A・コンプライアンス・契約交渉など)
- 官公庁・自治体での法律知識を活かした政策立案
- 大学院進学による学術研究や教育分野への進出
特に企業法務分野では「予備試験合格」の肩書だけでも高く評価され、転職市場で有利に働くこともあります。
つまり予備試験は、法曹を目指すだけでなく「法律を軸にした幅広いキャリア」を選べる大きなチャンスを与えてくれるということです。
2章:法律初学者が直面する予備試験の3つのデメリット
予備試験には、以上のように多くのメリットがありますが、当然ながら「甘くはない」現実も存在します。
特に法律初学者が独学で挑む場合、合格率の低さ、論文対策の難しさ、そして長期的なモチベーション維持といった壁に直面しやすいのが特徴です。
ここでは、その代表的な3つのデメリットを具体的に解説します。
2-1:合格率4%で法律知識ゼロからは難易度が極めて高い
予備試験の最終合格率はわずか約4%です。
司法試験の合格率(40%前後)と比較すると、いかに狭き門であるかが分かります。
この合格率の低さは、単に受験生の努力不足ではなく「試験範囲の膨大さ」と「要求される思考力の高さ」に起因しています。
法律初学者は基礎知識ゼロから出発するため、学習初期の負担が特に重く、最初の1〜2年で挫折する人も少なくありません。
さらに、予備試験は短答・論文・口述の三段階で構成されており、それぞれに合格基準が設けられています。
いずれか一段階でも基準未達となると不合格になるため、全体を通して安定した実力が不可欠です。
独学では「自分の勉強方法が本当に正しいのか」という不安を抱えながら進めることになるため、この合格率の低さが心理的なプレッシャーとしてのしかかります。
2-2:論文試験対策で独学の限界を感じやすい
予備試験の最大の関門は論文式試験です。
短答は知識を問う選択問題であり、演習を重ねれば得点を伸ばせますが、論文は「知識をどう使うか」が問われる試験です。
初学者が独学でつまずきやすいのは、次のようなポイントです。
- 論点の抽出ができない:「どこが問題なのか」を見つける力が弱い
- 答案構成ができない:知識があっても整理できず、論理展開が飛躍する
- 客観的なフィードバックがない:自分の答案がどの程度通用するか分からない
特に「書き方」を誤解したまま演習を続けると、何十枚答案を書いても得点につながらないという悪循環に陥りがちです。
予備校や添削サービスを利用せず独学で挑む場合、この「改善点を自分で見つけられない」という弱点が致命傷となることも少なくありません。
2-3:長期学習でのモチベーション管理が難しい
予備試験は短期間で結果を出せる試験ではなく、一般的に3〜4年の長期戦となります。
勉強時間も数千時間単位で必要なため、日常生活の中で継続的に学習を積み重ねる覚悟が不可欠です。
しかし、長期的に勉強を続ける中で必ず直面するのが「モチベーションの低下」です。
特に初学者の場合、以下のような要因がモチベーションの低下に影響しています。
- 学習初期の専門用語の難しさに心が折れる
- 論文答案が全く書けず、自信を失う
- 仕事や家庭との両立ができず、計画が崩れる
- 周囲の人が先に合格して焦りを感じる
こうした状況が重なると「自分には無理かもしれない」と感じてしまうのは自然なことです。
特に独学者は孤独になりやすく、支え合える仲間や相談できる指導者がいないため、精神的に追い込まれるケースもあります。
3章:初学者が予備試験合格するための3つの対策法
メリットとデメリットを理解したうえで、重要なのは「では初学者がどのようにして合格可能性を高めればよいのか」という具体的な戦略です。
予備試験は決して生半可な努力で突破できる試験ではありませんが、適切な計画と工夫を重ねれば独学でも十分に合格を目指すことができます。
ここでは、特に効果的とされる3つの対策法について詳しく解説します。
3-1:基礎から積み上げる段階的学習計画の立て方
予備試験に挑戦するうえで最初に直面する壁は、学習範囲の広さと専門用語の多さです。
初学者は、この壁を一気に乗り越えようとすると必ず挫折してしまいます。
そこで有効なのが、段階を踏んだ学習計画を立てることです。
最初の一年は憲法や民法、刑法といった基本3科目に集中し、条文をしっかり読み込み、理解し、基礎を丁寧に積み上げることが大切です。
その後に、行政法や商法、民事訴訟法、刑事訴訟法といった周辺科目を徐々に広げ、二年目以降には論文式の過去問演習に重点を置くようにすると、基礎力と応用力を無理なく養うことができます。
段階的に積み重ねていく計画を立てれば、焦りや不安に流されることなく、着実に学習を前に進めることができます。
3-2:予備校・通信講座で論文対策の弱点を補強
独学の大きな弱点は、論文式試験における「書き方」の習得が難しい点です。
論文試験では、知識を知っているだけでは通用せず、それを答案としてどう表現するかが合否を分けます。
しかし自分で答案を書いてみても、正しい方向に進んでいるのか、どこを改善すべきなのかが分からなければ、効率的に合格ラインに近づくことはできません。
この弱点を補う方法として効果的なのが、予備校や通信講座の活用です。
添削指導や模擬試験を受けることで、客観的な評価を受けながら改善点を把握でき、自己流を修正し合格答案に近づけることが可能になります。
特に近年はオンライン教材や通信型講座が充実しており、場所や時間に縛られずに指導を受けられるため、仕事や学業と並行して学習を進める人にとって大きな助けとなるでしょう。
独学を軸にしつつも、要所で外部の教材や講座を取り入れることで、効率性と正確性を兼ね備えた論文対策が実現できるのです。
3-3:合格者コミュニティなどでモチベーション維持
予備試験の学習は長期戦であり、孤独に取り組むほど精神的に消耗してしまいます。
学習を継続するうえで大切なのは、同じ目標を持つ仲間や先輩とのつながりを持つことです。
合格者コミュニティや学習サークルに参加すれば、自分と同じように苦しみながら努力している人の存在を知り、孤独感を和らげることができます。
また、先に合格した人の体験談を聞けば、合格に必要な学習時間や方法がより具体的にイメージでき、自分の学習に活かすことも可能です。
さらに、定期的に学習状況を共有することで「自分もやらなければ」という良い意味でのプレッシャーが働き、モチベーションを維持しやすくなります。
予備試験は個人の努力がものをいう試験ではありますが、孤独に戦う必要はありません。
支え合う環境を持つことで、長期戦を最後まで走り切るモチベーションが維持できるでしょう。
4章:予備試験合格を目指す初学者には「ヨビロン」をおすすめします
初学者でも予備試験に挑戦することは可能ですが、限られた時間で効率的に合格を目指すためには、正しい教材を選ぶことが極めて重要です。
特に初学者の場合には、学習の方向性を誤れば、数千時間の努力が報われない危険性さえあります。
ここで紹介するヨビロンは、法律初学者が独学で合格を目指す際に大きな助けとなるオンライン教材です。
予備試験1桁合格者のノウハウを凝縮し、論文試験に必要な思考力を養成しつつ、スキマ時間を活かして学べるよう設計されています。
以下では、その具体的な特徴とメリットを詳しく見ていきましょう。
4-1:予備試験1桁合格者の独自ノウハウが得られる
ヨビロンの最大の魅力は、机上の理論ではなく「実際に予備試験を突破した合格者のノウハウ」を体系的に学べる点です。
合格経験者が、どの論点を優先して学習したのか、どのように答案を構成したのかといった実戦的知識が詰め込まれており、独学者が最もつまずきやすい部分を補う設計になっています。
初学者はしばしば「何から学習を始めれば良いのか」「どの知識を重点的に深めればよいのか」といった迷いに陥りますが、ヨビロンを活用すれば、重要度や出題頻度に基づいて効率よく学習を進めることができるでしょう。
これは、ただ分厚い基本書を闇雲に読み進めるのとは全く異なり、合格に直結する学習を可能にしてくれます。
4-2:初見の問題でも確実に点が取れる思考力が養える
予備試験の最大の特徴は、過去問をなぞるだけでは通用しない点にあります。
毎年、新しい論点や事例が出題されるため、暗記だけに頼った学習では必ず限界が訪れます。
そこでポイントになるのが「初見の問題でも条文や判例を手掛かりに論理的に解答を組み立てる力」です。
この点、ヨビロンは、法的思考力を徹底的に鍛えるカリキュラムを備えています。
具体的には、条文を基礎に置きつつ、判例の理由付けや学説の位置づけを組み合わせて出題者の意図に沿った答案を作る訓練を重視しています。
これにより、試験本番で未知の問題に出会っても、条文から論点を導き、論理的に展開して結論を示す「型」を自然と身につけられるのです。
これは初学者に不足しがちな部分であり、合否を左右する極めて重要な要素といえるでしょう。
4-3:スキマ時間でも活用できるオンライン教材
法律初学者が独学で予備試験に挑戦する場合、もう一つの大きな課題は「まとまった勉強時間を確保できない」という点です。
社会人であれば、仕事の合間などの隙間時間を効率よく学習に当てる必要があります。
また、学生であれば授業との両立が必要となり、勉強時間は常に制約されます。
ヨビロンはオンライン教材であるため、スマホやタブレットからいつでもアクセス可能で、通勤電車の中や昼休み、就寝前の短時間でも学習を進めることができます。
これにより、日常のスキマ時間を積み重ねて数百時間単位の学習を確保できるため、独学の最大の弱点を補うことができるのです。
さらに、進捗管理機能や復習リマインド機能が備わっているため、「今日はどこまで進めればよいか」「次に復習すべき分野はどこか」といった判断に迷うこともありません。
ヨビロンは、合格者のノウハウ、思考力養成、スキマ時間活用という3つの強みを兼ね備えた、理想的な教材です。
ヨビロンは、単なる情報の羅列ではなく、実際に合格へ導くための仕組みが整っているため、法律初学者でも安心して学習を進めることができます。
独学で予備試験に挑戦するのであれば、ヨビロンを取り入れることは効率性と合格可能性を大幅に高める最善の選択肢といえるでしょう。
まとめ:法律初学者は自分に合った学習スタイルでメリットを最大化しよう
予備試験は、司法試験の受験資格を得るための関門として位置づけられ、その難易度は日本の資格試験の中でも突出しています。
合格率はわずか4%前後であり、短答・論文・口述のすべてを突破しなければならないことから、法律初学者にとっては非常に高いハードルに映るでしょう。
しかし一方で、予備試験ルートを選択することは、法科大学院ルートよりも圧倒的に低コストで挑戦でき、最短ルートで法曹を目指せ、キャリア選択にも有利であるという大きなメリットを兼ね備えています。
たしかに、極めて低い合格率や論文試験対策の難しさ、そして長期学習を支えるモチベーション維持の困難さはあります。
しかし、基礎から積み上げる学習計画の立て方、予備校や通信講座の効果的な活用法、そして合格者コミュニティを通じたモチベーション維持を工夫することでこれらのデメリットを解消させることが可能です。
そのうえで、予備試験の上位合格者が作成したヨビロンのような教材は非常に効果的です。
重要なのは、「正しい方向性を持った努力」を継続することです。
数千時間という学習量は一見途方もなく思えるかもしれませんが、日々の積み重ねがやがて大きな成果となり、難関突破への力となります。
これから予備試験に挑もうとするあなたも、まずは一歩を踏み出すことから始めてみてください。
その一歩が未来の法曹としてのキャリアにつながる第一歩となります。






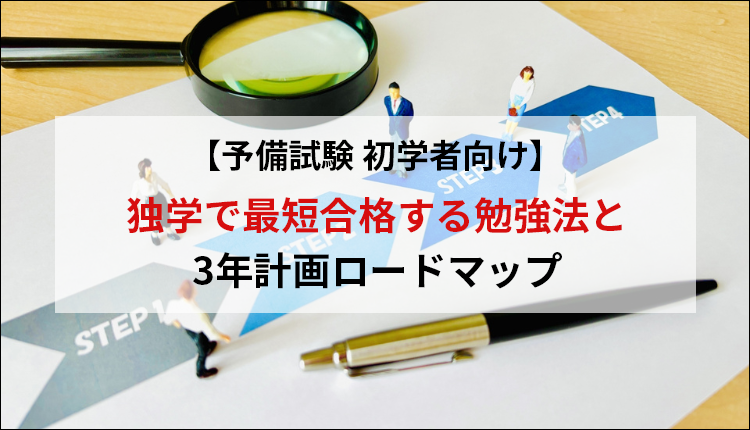

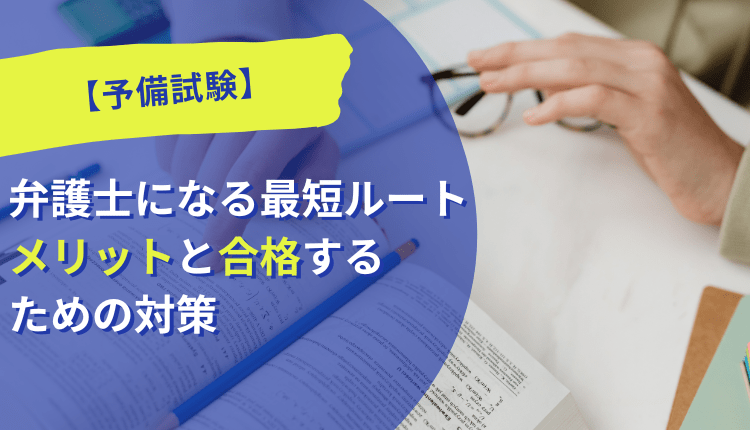
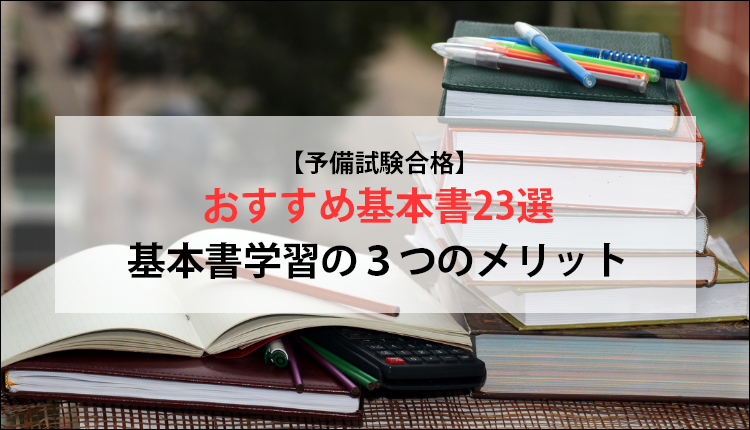
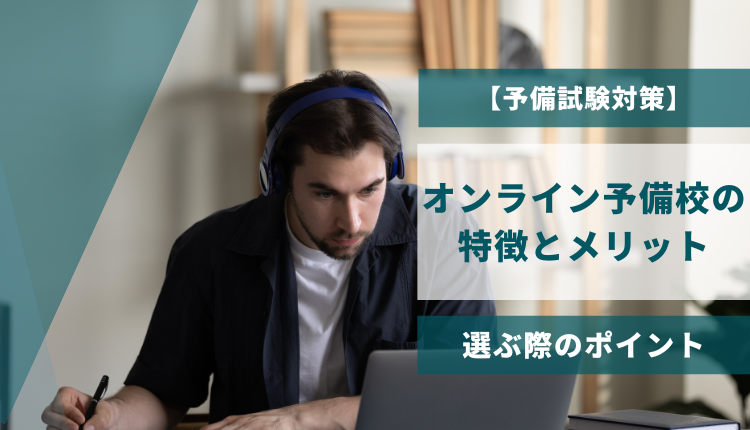
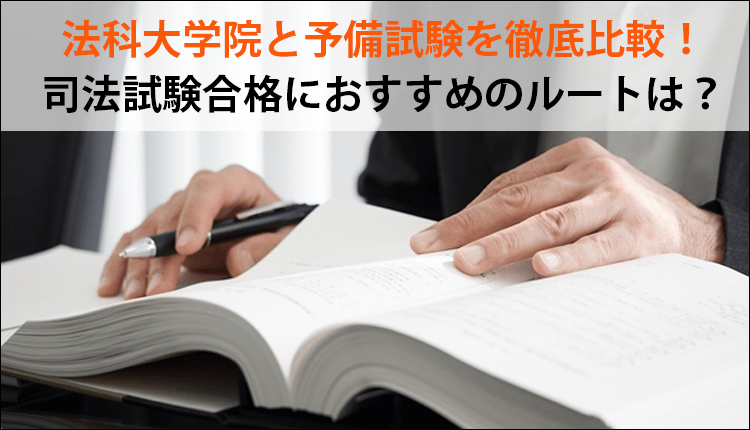

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。