【保存版】予備試験×アプリ活用術|通勤10分で差がつく隙間時間勉強ロードマップ
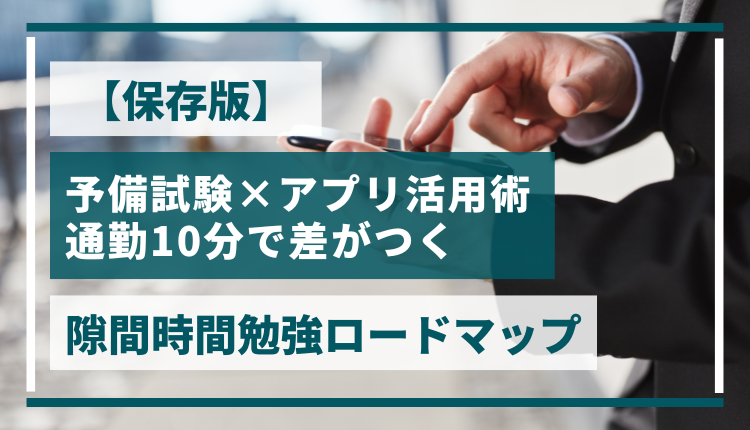
目次
この記事を読んで理解できること
- 予備試験対策|アプリ学習の効果とメリット
- 予備試験対策におすすめアプリ5選
- 目的別予備試験アプリの選び方
- アプリ学習で合格を勝ち取る実践方法
あなたは、
「予備試験に挑戦するにあたって、おすすめの勉強アプリを知りたい。」
「アプリを使った実践的な学習方法を知りたい。」
こんな悩みを抱えていませんか。
予備試験は司法試験への関門であり、短答・論文・口述と複数の試験を突破しなければなりません。
その中でも学習時間をどれだけ確保できるかが最大の課題です。
この点、スマートフォンやタブレットに対応した学習アプリを取り入れることで、従来なら「何となく過ごしていた時間」を得点力に直結させることが可能になります。
例えば、通勤や通学の電車の中の10分、昼休みの30分、就寝前の15分といった細切れ時間が、積み重なれば膨大な学習量となり、合格の可能性を飛躍的に高めます。
そこで、本記事では、アプリを活用した予備試験対策の効果とメリット、おすすめアプリ5選、目的別の選び方、さらには具体的な実践方法まで徹底解説します。
具体的には、
1章では、予備試験対策におけるアプリ学習の効果とメリット
2章では、予備試験対策におすすめなアプリとその内容
3章では、目的別予備試験アプリの選び方
4章では、アプリ学習で合格を勝ち取る実践方法
を紹介します。
この記事を読んでいただき、アプリ学習の可能性を理解することで、あなたの勉強法は一段と効率的になり、合格までのロードマップが明確になるはずです。
第1章:予備試験対策|アプリ学習の効果とメリット
予備試験は学習範囲が広く、勉強量も膨大です。
そのため「時間が足りない」という悩みは多くの受験生が直面します。
この点、アプリを活用すれば、その悩みを解消し、効率的に得点力を伸ばすことができます。
ここでは、アプリ学習の効果と3つのメリットを掘り下げて解説します。
1-1:隙間時間活用に最適|学習時間が拡大
予備試験に合格するには、年間で1,000〜1,500時間程度の学習が必要とされます。
忙しい受験生がこれだけの時間を確保するのは簡単ではありません。
そこで威力を発揮するのが「アプリ学習」です。
スマホアプリを活用すれば、場所を選ばず学習できるため、通勤や通学の電車の中、昼休み、カフェ、さらには寝る前のベッドの中でも問題演習や暗記が可能です。
従来なら何となく過ごしていた時間を、知識習得に変えられるのは大きなメリットです。
例えば、毎日30分の隙間時間をアプリ学習に充てると、年間で180時間の学習が積み上がります。
これは短答過去問を複数回できるほどの時間に相当します。
つまり、アプリは「学習時間を創り出す装置」として、忙しい受験生にとって欠かせない存在です。
1-2:間違い問題自動抽出で復習効率が向上
学習において最も重要なのは「間違えた問題をいかに効率よく潰すか」です。
紙の教材では、間違いに印をつけ、自分でリスト化し、何度も解き直す必要がありました。
しかし、アプリなら、正答率や解答履歴を自動的に記録し、間違えた問題だけを集中的に復習できる仕組みが備わっています。
例えば、「間違えた問題が自動で翌日に再登場し、1週間後、1か月後に再出題される」といった復習サイクル機能を持つアプリもあります。
これにより、忘却曲線を踏まえた効率的な復習が可能となり、記憶が長期的に定着します。
特に予備試験短答は範囲が広く、復習なしではあっという間に忘れてしまいます。
この点、アプリによる自動管理機能を活用すれば、膨大な範囲を効率よく回転させることができ、弱点補強に集中できます。
1-3:使いやすさで学習継続率が向上
予備試験合格の最大の敵は「挫折」です。
範囲が広く長期戦になるため、途中でモチベーションを失う受験生も少なくありません。
ここで役立つのが「使いやすさ」に優れた学習アプリです。
直感的な操作性やゲーミフィケーション機能(レベルアップ表示・達成バッジなど)が備わっていれば、学習そのものが「楽しみ」に変わります。
また、正答率や学習時間がグラフ化され、成長を可視化できる点も魅力です。努力の蓄積を数字で確認できれば、学習継続率は飛躍的に高まります。
つまり、アプリは単なる「教材」ではなく、「勉強を続けるための仕組み」を提供してくれる存在です。
第2章:予備試験対策におすすめアプリ5選
予備試験の学習アプリは数多く存在しますが、それぞれに強みと特徴があります。
短答式対策に特化したものから、論文式に役立つもの、さらには集中力を管理するツールまで幅広く揃っています。
ここでは、実際に利用者からの評価も高い5つのアプリを取り上げ、具体的な使用例を交えながらご紹介します。
自分に合ったアプリを選び、日常の学習効率を飛躍的に高めましょう。
2-1:資格スクエア「短答攻略クエスト」の特徴と活用法
資格スクエアの「短答攻略クエスト」は、司法試験や予備試験の短答式試験に特化したアプリです。
弁護士や司法試験上位合格者が監修したもので、1000問以上を無料で利用できます。
そして、最大の魅力は「ゲーム感覚で学べる」点にあります。
通常の過去問演習は単調になりがちですが、正答数に応じてレベルアップし、一定レベルに達すると無料で問題が解放されるなど、本アプリではレベルアップすることで次のステージへ進む仕組みがあり、モチベーションを維持しやすい工夫がされています。
また、学習結果は可視化・数値化されるため、問題を解くたびにスコアが表示され、正答率や分野ごとの理解度がグラフ化されるため、自分の弱点を視覚的に確認できます。
例えば「憲法は正答率70%、刑法は50%」と表示されれば、刑法の復習を優先する、といった学習サイクルを自然に作れます。
忙しい受験生や勉強に飽きやすい受験生には特におすすめのアプリです。
「楽しく継続できること」が最大の効果といえるでしょう。
2-2:辰已「肢別アプリ」で1問1答を効率化
辰已法律研究所が提供する「肢別アプリ」は、短答対策の王道教材「肢別本」をスマホに完全移植したものです。
1問ごとに○×形式で解答でき、短答に必要な正確な知識を積み上げるのに最適です。
特徴は、数千問に及ぶ過去問をいつでも持ち歩ける点です。
紙の肢別本は分厚く持ち運びが大変ですが、アプリならスマホ1台で全てカバーできます。
また、学習済みの問題数(OK問題、要注意問題、不確実問題等)や達成率、学習率などが一覧でき、さまざまな出題設定をすることも可能です。
収録問題をリスト表示で一覧できるほか、キーワード(1語)での問題検索も可能なので、特定のテーマを集中的に学習したいときにはこのような機能は効果的です。
例えば、昼休みの15分で「憲法だけ20問」と範囲を絞って演習したり、寝る前に「昨日間違えた問題だけ」を復習する、といった柔軟な活用ができます。
試験直前期には、チェックが付いた問題だけを繰り返すことで、知識の穴を徹底的に潰せます。
短答式の基礎固めを徹底したい人にとって必携のアプリといえるでしょう。
2-3:スタディング司法試験講座の学習管理機能
スタディング司法試験講座は、人気の資格予備校のスタディングが提供しているアプリで、オフライン再生に対応しており、どこにいても動画講義を視聴でき、アプリ1つで「動画講義+問題演習+学習管理」が完結する総合型学習システムです。
講義動画はもちろん、WEBテキスト・問題集・暗記ツールもスマホ1つでOKです。
スタディングアプリはオフライン再生にも対応しているため、場所を選ばず使用することができます。
AI実力スコア機能も備わっており、現在のあなたの実力をリアルタイムで確認できます。
具体的には「あなたが今、試験を受けた場合に、何点取れるのか?」を、AIを使って予測しますので学習のペース配分など学習管理に効果的です。
また、学習フローの機能があり、動画講座を視聴したらすぐ問題を解くという手順が明確に示されており、インプット&アウトプット学習がしっかりできるフローが用意されています。
さらに、スタディングで学習した時間や進捗状況が自動的に集計され、わかりやすいグラフと数値で表示されるため、日々学習を進める中で、現在の科目別・単元別の実力をリアルタイムで把握できます。
例えば、通勤中に倍速講義を視聴し、帰宅後にその講義に対応する問題を解く、といった一連の流れをアプリ内で完結できます。
さらに、復習のタイミングも自動通知されるため、「どの教材をどの順番で復習するか」と迷う時間を大幅に削減できます。
独学に不安がある人や、効率的に全体像を把握したい人にとって、まさに「オンライン予備校」として機能するアプリです。
2-4:anki barで論証暗記を自動化
「anki bar(アンキバー)」は、忘却曲線理論を応用したフラッシュカードアプリで「司法試験・予備試験専用の論証作成・学習支援アプリ」です。
忘却曲線に基づいたテスト機能で効率的に論証を記憶できることが特徴で、論証の作成から知識の定着まで支援してくれます。
普段作成している論証集と同じ感覚で、見出しと本文を入力するというシンプルな操作で使用することができます。
また、論証集やテキストの画像を読み取ると文字化してくれ、あとはカスタマイズすると自分なりの論証を作成することができ、手間を省き、効率的に論証を作成できるようになっている点が、ユーザーにも特に好評です。
例えば、アプリを活用することで、通勤中に論証カードを10枚だけ確認し、夜にもう一度確認する、といったサイクルが自然に回ります。
これにより、紙の論証集を何度も開く手間がなくなり、知識が長期記憶として定着します。
2-5:集中アプリでポモドーロ学習を実践
学習効率を上げるのは知識の習得だけではありません。
「集中力の維持」も合否を分ける大きな要素です。
ここで役立つのが、ポモドーロ・テクニックをサポートする集中アプリです。
具体的には、25分勉強+5分休憩のサイクルを自動で管理し、休憩時間になると通知で知らせてくれます。
さらに、スマホの通知を遮断する機能を備えたアプリなら、SNSやメールの誘惑を遮断し、学習だけに集中できます。
例えば、自宅学習中に「2時間でポモドーロを4回」設定すれば、休憩を挟みつつ8割以上の集中度で学習できます。
また、学習時間のログも記録されるため、例えば、「今日は3時間集中できた」と振り返りが可能です。
独学で「集中力が続かない」「ついスマホを触ってしまう」という人にとって、まさに救世主となるアプリです。
第3章:目的別予備試験アプリの選び方
予備試験対策に役立つアプリは多種多様ですが、全てを手当たり次第に使ってしまうと逆に非効率になります。
大切なのは、「自分の目的に合ったアプリを選ぶ」ことです。
ここでは、短答対策・論文対策・総合対策という3つの目的別に最適なアプリの選び方を解説します。
どのアプリを優先するべきか迷っている方は、この章を参考にして自分の学習環境に最もフィットするツールを見つけてください。
3-1:短答対策重視なら過去問演習機能
短答式試験は、合格に向けた最初の大きな関門です。
そのため、まず短答突破を目指す人にとっては「過去問演習機能」が充実したアプリを選ぶことが必須です。
例えば、辰已の「肢別アプリ」や資格スクエアの「短答攻略クエスト」は、過去数十年分の問題を効率的に演習できる仕組みを備えています。
これらのアプリでは「科目別・分野別に絞り込み」「正答率の低い問題だけ再出題」といった機能があるため、闇雲に全範囲を復習するよりも短期間で得点力を伸ばすことが可能です。
例えば、朝の通勤電車で10分だけ「憲法の人権分野を演習」、夜寝る前に「刑法の間違えた問題だけを復習」といった形で、効率よく反復学習を繰り返せます。
短答は知識の広さと正確さが勝負ですが、限られた時間で合格ラインを突破するためには「どの論点を優先するか」を自動で整理してくれるアプリが最適解です。
3-2:論文対策なら論証管理と暗記機能
論文式試験では、知識を覚えるだけでなく、それを答案に落とし込む「応用力」と「表現力」が求められます。
そのため、論文対策に重点を置く人は「論証カード機能」や「暗記支援機能」を持つアプリを選ぶと効果的です。
例えば「anki bar」のようなフラッシュカードアプリは、自分で論証パターンを登録でき、忘却曲線に基づいた自動復習スケジュールで繰り返し確認できます。
これにより、論証の定型文が自然に口をついて出るようになり、答案を書くスピードと精度が飛躍的に高まります。
さらに、アプリ上で自分専用の論証集を作っておけば、通勤中や昼休みなどのスキマ時間に論文対策を進められます。
紙の論証集を持ち歩かなくてもよいため、荷物が減り、心理的な負担も軽くなる点も見逃せません。
特に初学者は「条文や判例は覚えているのに、答案に書けない」という壁に直面しがちですが、この種のアプリを活用することで「使える知識」に変換する訓練ができます。
3-3:総合対策なら講義視聴と問題演習
短答・論文の両方を一気に対策したい場合は、「講義視聴+問題演習」が一体化したアプリを選ぶのがベストです。
「スタディング司法試験講座」のように講義動画を倍速で視聴できるようなアプリであれば、移動中でも効率よくインプットできます。
その直後に関連する問題演習を解くことで、「講義で学んだ内容をその場で定着」させることが可能です。
さらに、学習進捗が自動で記録され、残りの学習時間と進度が数値化されるため、自己管理が苦手な人でも安心です。
例えば、「平日の朝に30分の講義を倍速で視聴し、昼休みにその範囲の問題演習をスマホで解く、夜は自宅で間違えた部分の復習に充てる」こうしたサイクルを1週間回せば、知識のインプットとアウトプットの両方をスムーズに進められます。
また、予備試験アプリなどの教材を選ぶにあたって、最重要なのは、信頼のおけるものかという点です。
ここまで紹介したアプリはいずれも強力なツールですが、実際に予備試験1桁で合格した合格者が作った「ヨビロン」もぜひ活用したいい学習ツールの1つです。
ヨビロンは、業界唯一の「予備試験合格者が100%作った論証集」です。
特に、予備試験合格者が直接関わって作成した「論文の型」を学ぶことで、体系的な指導を受けられる点が魅力です。
つまり、アプリ学習の「隙間時間の強み」と、ヨビロンの「全体像を把握できる安心感」を組み合わせれば、効率と精度を両立した最強の学習環境が完成します。
第4章:アプリ学習で合格を勝ち取る実践方法
アプリを導入するだけで、合格に直結するわけではありません。
重要なのは「どのようにアプリを学習サイクルに組み込むか」です。
ここでは、スキマ時間を最大限活用する1日のスケジュール設計、アプリと従来型テキストの併用法、そして学習進捗を可視化して合格までのロードマップを描く方法について解説します。
日々の小さな工夫が積み重なり、大きな成果につながります。
4-1:1日30分の隙間時間学習スケジュール
忙しい受験生に共通する悩みは「まとまった学習時間が取れない」ことです。
だからこそ、スキマ時間を活用できるアプリ学習は強力な武器になります。
例えば、通勤・通学の電車内では 短答過去問アプリで5問演習、昼休みには 論証カードを5つ確認、就寝前には 判例解説動画を1本視聴 といったように、1回あたり10分程度の学習を積み重ねるだけで、1日合計30分以上の「プラス学習時間」を確保できます。
この「細切れ学習」の最大のメリットは、集中力が途切れにくい点です。
30分まとめて机に向かうのは難しくても、5〜10分なら意外と続けられます。
しかも、忘却曲線の理論に基づき、複数回に分けて学習した方が記憶の定着率は高いことが知られています。
実際、合格者の多くも「通勤や通学の電車の中が最大の勉強時間だった」「昼休みを演習タイムに固定した」と振り返っています。
日常生活のすき間を学習に変える習慣こそ、継続の原動力になります。
4-2:アプリとテキストの効果的な併用法
アプリは便利ですが、弱点もあります。
それは「体系的に学習内容を整理しにくい」点です。
どうしても画面上で問題を解くだけでは、知識が断片的に蓄積されやすいです。
そこで重要になるのが アプリ+テキストの併用です。
具体的には、アプリで問題を解いた後に「間違えた問題の根拠条文や解説をテキストで確認する」流れを徹底します。
これにより、アプリ学習で得た「点の知識」がテキストによって「面の知識」に広がり、理解が一段と深まります。
また、論文対策では「アプリで論証暗記」+「テキストや講義で答案例確認」という使い分けが有効です。
アプリはスピード暗記に強く、テキストは論理展開の全体像を学ぶのに適しています。
両者を役割分担させることで、効率的かつバランスの取れた学習が可能になります。
例えば、通勤中はアプリで論証フレーズを確認、帰宅後はそのフレーズを答案で実際に使う練習をする。
こうした二段構えの学習法は、単なる暗記ではなく「使える知識」へと昇華させる最短ルートです。
4-3:学習進捗管理で合格までのロードマップ
学習の継続において最大の敵は「自分がどこまで進んでいるか分からない」という不安です。
そこで役立つのが、アプリの進捗管理機能です。
多くの学習アプリには「正答率の推移」「学習時間の累計」「未学習分野のリスト化」といった機能が搭載されています。
例えば、スタディングの学習管理画面では「今週は憲法を3時間学習、正答率は70%→80%に上昇」といったデータが自動で可視化されます。
これにより、「やれば伸びる」という実感を得やすく、モチベーション維持に直結します。
さらに、この進捗データをもとに「月末までに民法を1周」「試験2か月前には短答全科目の正答率80%を達成」といったロードマップを立てると、学習全体の見通しが格段にクリアになります。
合格者の多くも「アプリの学習記録を週末に見返し、翌週の計画を修正した」と語っています。
学習の可視化は、「正しい方向に進んでいる」という安心感を与えてくれます。
まとめ:予備試験対策|アプリで隙間時間を最大活用
予備試験は短答・論文・口述の三段階から成り立ちますが、そのスタートラインである短答式試験を突破するためには、日々の学習をいかに継続できるかが最大のカギとなります。
そしてその継続を支える武器が「アプリ学習」です。
アプリを使えば、これまで勉強時間に変えられなかった通勤や通学の時間帯、昼休みや就寝前といった細切れ時間を有効活用できます。
たとえ一日で合計30分でも、1か月積み重ねれば約15時間、半年で90時間以上の大きな差となり、合格可能性を大きく高めます。
また、アプリは「間違い問題の自動抽出」「復習のリマインド機能」「学習進捗の可視化」といった仕組みを備えているため、独学で陥りやすい「自己流の非効率さ」や「計画倒れ」を防いでくれます。
さらに、テキストと併用することで体系的理解と即応力の両立が可能となり、「知識を覚える」だけでなく「知識を使える」力へと転換できます。
もちろん、アプリだけに頼るのではなく、自分の学習スタイルに合わせて柔軟に組み合わせることが重要です。
過去問演習や論文答案練習と併用しながら、アプリを「学習効率を最大化する補助ツール」として位置づけると、最短合格に向けた道筋が格段に明確になります。
予備試験の合格者の多くが口をそろえて言うのは、「隙間時間の使い方で合否は変わる」という事実です。
もし今、「時間がないから勉強できない」と感じているなら、それは「時間がない」のではなく「時間を見つけていない」だけかもしれません。
今日からスマホに学習アプリを1つインストールし、まずは10分から始めてみましょう。
その小さな一歩が積み重なったとき、あなたの知識は確実に合格レベルへと近づいていきます。
本記事を参考に、あなたの生活リズムに合ったアプリ学習を実践し、合格という大きな成果を勝ち取りましょう。






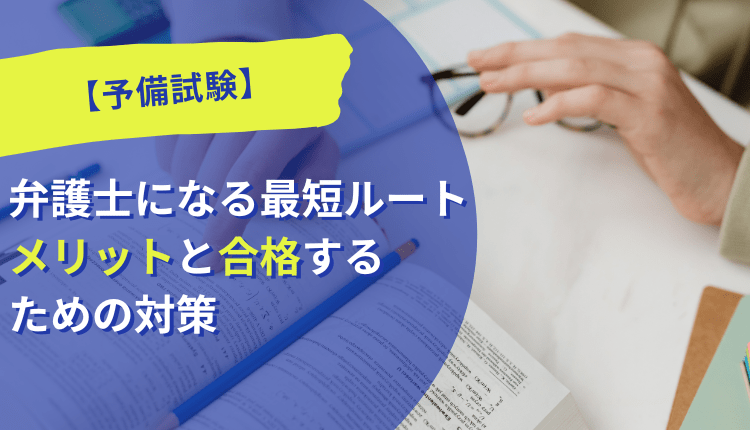
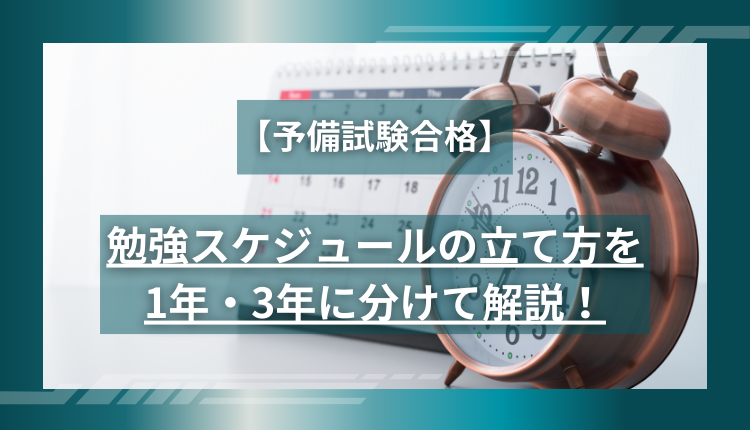
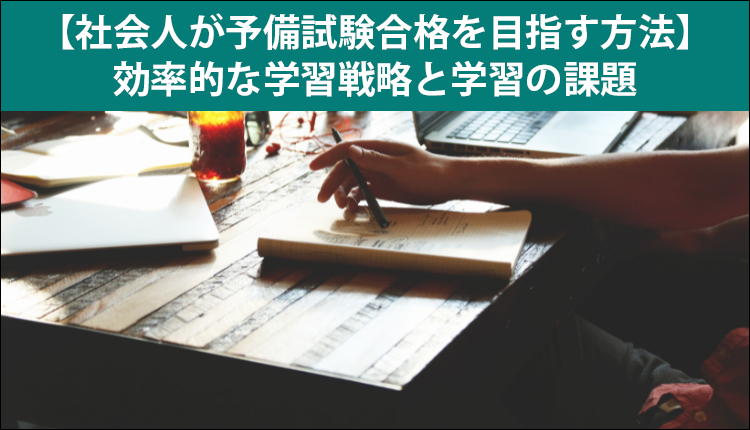
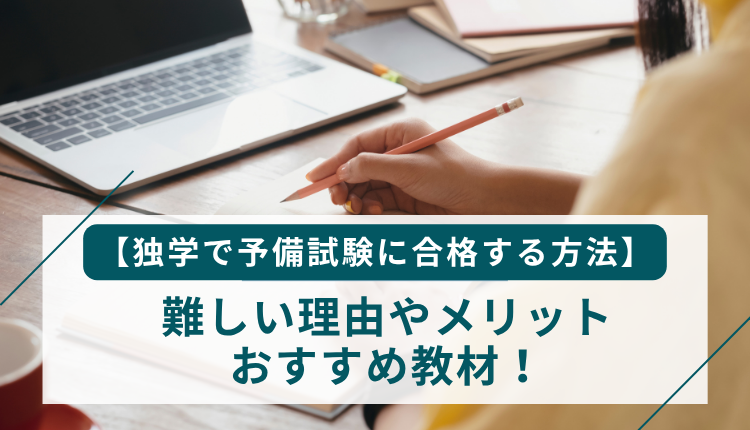
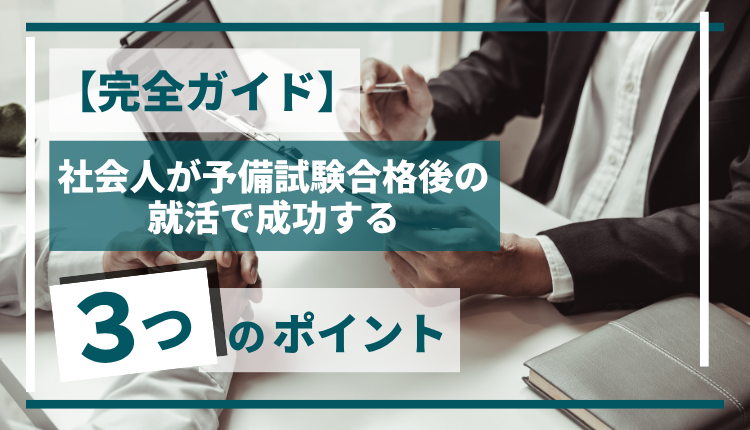
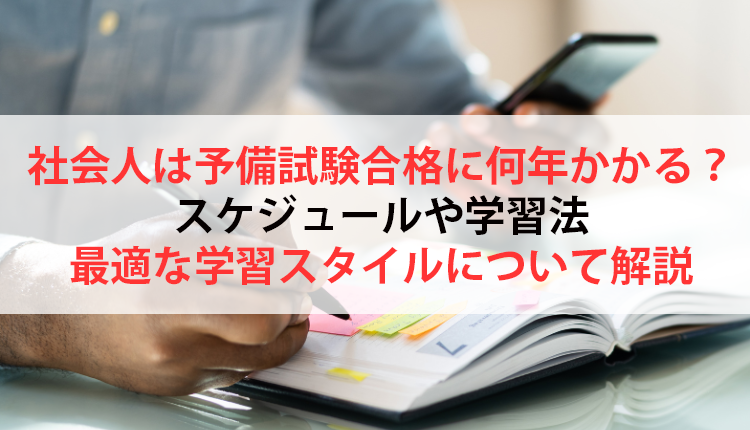

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。