【独学で予備試験に合格する方法】難しい理由やメリット、おすすめ教材!
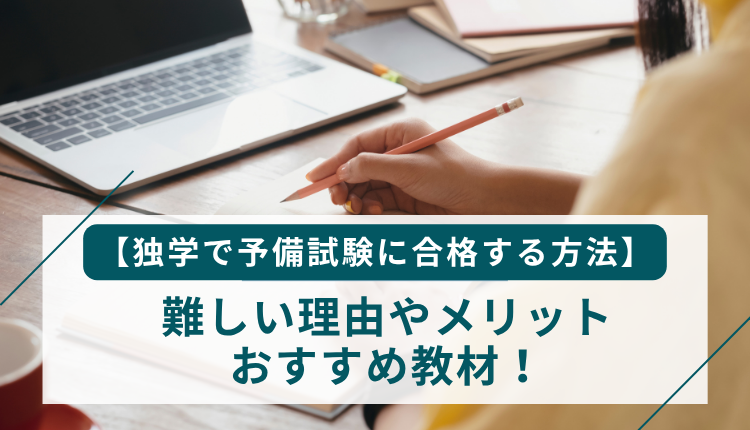
目次
この記事を読んで理解できること
- 予備試験は独学での挑戦が難しい理由4つ
- 予備試験に独学で挑戦する3つのメリット
- 予備試験合格を独学で成功させる方法4つ
- 予備試験に合格するためには「ヨビロン」をおすすめします
あなたは、
- 独学で司法試験予備試験に合格できるかどうかを知りたい
- 独学で司法試験予備試験に合格するのが難しい理由を確かめたい
- 独学で司法試験予備試験を突破できる方法があれば実践したい
とお考えではありませんか?
予備試験はたしかに難易度が高く、独学で突破するのは至難の業です。
しかし、独学でも予備試験を突破できる方法はありますので、初期の段階から実践していけば、合格も夢ではありません。
本記事を読めば、独学での予備試験合格が難しい理由や独学のメリット、独学で予備試験合格を勝ち取る方法も知ることができます。
具体的には、
1章で予備試験は独学での挑戦が難しい理由4つ
2章で予備試験に独学で挑戦する3つのメリット
3章で予備試験合格を独学で成功させる方法4つ
4章で予備試験に合格するための必携本
について、詳しく説明していきます。
1章:予備試験は独学での挑戦が難しい理由4つ
独学で予備試験合格を目指せないかと考えている方も多いと思いますが、以下4つの理由で、独学での挑戦は難しいといわれています。
- 法律の条文や判例を理解することが難しい
- 論文式試験の攻略が難しい
- 教材選びや情報の取得が難しい
- 長期間の自己管理が難しい
以下、順を追って解説します。
1-1:法律の条文や判例を理解することが難しい
司法試験予備試験は、憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法ほかと、学ぶべき法律が多岐に渡る試験です。
独学でありがちなのは、すべての法律の条文や判例を覚えようと考え、一つひとつ丁寧に理解しようと時間をかけすぎてしまうことです。
しかし、法律を学び始めると条文数や判例の文章量が多く、しかも、カットしていい不要な部分など一切ないことにも気づくと思います。
また、条文中には独特な言い回し(「信義に従い誠実に」など)が散見できるほか、意味や内容をしっかり覚えなければ混同してしまう専門用語(「成年後見人」「保佐人」「補助人」など)も少なくありません。
1-2:論文式試験の攻略が難しい
司法試験予備試験は「短答式試験→論文式試験→口述試験」と3つの試験をクリアする必要がある試験です。
令和6年予備試験の論文式試験では、採点対象者2617人中、合格したのは462人で、合格率は17.65%となっています。
短答式試験をクリアした優秀な方でも論文式試験で落とされてしまうのは、いくら法律の知識があっても、法的思考力と答案構成力がないと判断されるからです。
法的思考力とは、ある問題(事実)を解消するために、必要な法律は何かを考え解決策を見出す力で、弁護士・検察官・裁判官・法務職に就くと日々、求められるものです。
法的思考力を高めるためには、正しい法律の知識はもとより、問題の本質や争点は何かを見抜く分析力と、矛盾を生じさせずに筋道を立てていく論理的思考力も必要不可欠です。
また、答案構成力とは、論じるべき要素を削ることなく、簡潔にわかりやすく答案を最後まで書き終えるために必要な構成を作る力です。
論文式試験の時間・答案用紙にも限りがあります。
不合格の理由になりえる「途中答案」で試験を不意にしないためにも、答案構成力を磨かなければなりません。
法的思考力と答案構成力は、実際に頭と手を動かして、場数を踏む以外に強化する術がありません。
そのため、できるかぎり早期の論文式試験対策をスタートさせることが望ましいのです。
また、論文式試験には「正解」がなく、独学では、添削を受ける機会もないに等しいです。
そのため、自分が論文式試験に合格できるレベルかどうかをセルフチェックできず、手応えも感じにくいでしょう。
1-3:教材選びや情報の取得が難しい
特に法学未修者が独学で予備試験合格を目指す場合、教材選びに難航するでしょう。
ネットで購入する方もいると思いますが、「ページ数」「価格」「口コミでの評価」などの形式的な情報だけで判断してはいけません。
分厚くても、高くても、多くの受験生に支持されていても、その教材が必ずしも、自分に合っているとは限らないからです。
手間や時間はかかりますが、図書館や書店に足を運んで実際に中身を見て、理解できそうか、使えそうかを判断することをおすすめします。
また、法科大学院や予備校に通っていれば、試験に関連する最新の情報などを容易に取得することができます。
情報収集と提供を行う専任の職員スタッフを設けるなど体制を整えているためです。
1-4:長期間の自己管理が難しい
司法試験予備試験合格に必要な勉強量の目安は、3,000時間~10,000時間といわれており、1~3年は予備試験に向けて、学習していくことになります。
前もって学習計画を立てて勉強していくと思うのですが、学校や仕事、家庭の事情で思うように進まない時期も出てくるでしょう。
- 学習計画通りに進まない場合は計画の見直しや調整を行う
- 学校や仕事などで忙しい場合はスキマ時間を見つけて勉強する
上記のような自己管理も簡単なようで、実行に移すのは難しいのです。
逆に言えば自分を律して、環境を言い訳にせず、着実に学習していける方でなければ司法試験予備試験を通過できないということです。
以上4つの理由が、独学での合格をさらに難しくしており、ひとりで勉強していくのは不利といえます。
独学では苦労するかもしれないと感じた方が、予備校や法科大学院で学ぶ選択をしているのでしょう。
2章:予備試験に独学で挑戦する3つのメリット
独学で予備試験に挑戦するのは至難の業ですが、悪いことばかりではなく、いいこともあります。
- 費用を大幅に削減できる
- 自分のペースで学習計画を調整できる
- 自分に合った教材を選べる
ここでは、上記3項目について、詳細を説明していきます。
2-1:費用を大幅に削減できる
法科大学院や予備校に通うと、相当の学費を負担することになりますが、独学であれば六法全書・基本書・参考書・問題集といった書籍代だけとなり、予備試験を受験するための費用を劇的に削減することが可能です。
法科大学院や予備校で勉強すると決めた場合は入学前に、まとまったお金を用意して一括払いもしくはクレジット分割払い、ローンを組むことになりますが、独学の場合は都度、必要となった書籍を購入すればよく、手持ちの現金と相談しながらムリなく学習できます。
2-2:自分のペースで学習計画を調整できる
法科大学院や予備校は、決まった時間に通う必要があり、講義も学校主導で進んでいきますが、独学なら大学やアルバイト・仕事のスキマ時間、平日夜・休日など自分で決めた時間帯に、学習を進めていけます。
法科大学院や予備校では、一人ひとりの理解力や習熟度など一切考慮されることなく講義が進んでいくため、勉強に付いて行けず挫折し、受験を断念する方も少なくありません。
しかし、独学では、理解力や習熟度に合わせて、自分が勉強しやすいように、計画を見直したり、調整したりができます。
2-3:自分に合った教材を選べる
学生時代、学校指定の教科書や辞書、先生がおすすめした参考書ではわかりにくいと感じ、自分で中身を見て参考書や問題集を買った経験が一度はあると思います。
法科大学院の教授が薦める基本書や、予備校が制作した予備試験対策テキストは、たしかに効率よく学習できるように作り込まれていますが、必ずしも自分に合うとは言いきれません。
独学では、使い始めて失敗したと後悔することもあるかもしれませんが、自由に教材を選ぶことができ、自分に合う教材を見つけ出すことができるはずです。
3章:予備試験合格を独学で成功させる方法4つ
なるべく費用を安く抑えたい、自分のペースでムリなく勉強したいといった理由で、独学による予備試験合格を目指すなら、次の4つの方法を意識して、勉強していくようにします。
- 論文式試験の対策を重視し出題傾向を把握する
- 過去問演習に早期に取り組み答案作成技術を高める
- 条文・判例・基本書をしっかり読み込む
- 効率的な学習スケジュールでモチベーションを維持する
3-1:方法①論文式試験の対策を重視し出題傾向を把握する
予備試験で最も重要な試験は、論文式試験です。
これまで予備試験に合格してきた方は、短文式試験対策もほどほどに、早い段階で論文式試験対策にシフトし、多くの時間をかけて、本番に挑んでいます。
その理由は、論文式試験では「途中答案」を出した多くの方が不合格となっているからです。
途中答案とは、最後まできちんと書けなかった論文を指します。
通常、大前提→小前提→結論という「法的三段論法」を用いて論文を作成していきますので、結論を書けなかった場合は「不合格」となりえると考えるのが自然です。
試験時間中に問題を読解し、これまで蓄積してきた条文・判例などのデータを掘り起こして、答案の構成を作り、論文を最後まで書き終えるためには、先に述べたように場数を踏むしかありません。
まずは短答式試験をクリアしなければ論文式試験に進めないため、インプット中心の勉強に傾倒したい気持ちも理解できますが、できる限り早い段階から過去問演習に取り組むことで、出題傾向を把握することができるようになります。
3-2:方法②過去問演習に早期に取り組み答案作成技術を高める
条文や判例をすべて読み込み終え、過去問演習は2年目あたりから始めようと思っている方もいると思いますが、論文式試験を見据え、ある程度、見切り発車的に過去問演習に取り組まれたほうが有益です。
過去問演習には、論文式試験の出題傾向の把握のほか、時間配分の予行練習、知識定着を早める、法的思考力と答案構成力の強化、今の自分の知識レベルを俯瞰できるといった効果があります。
極論、条文や判例については試験本番前日までに正答できるレベルに到達すればよく、論文式試験突破を勝ち取るために必要な時間配分を体得し、多くの時間をかけて法的思考力・答案構成力を磨き上げ、答案作成技術を高めていくことが、何よりも大切なのです。
3-3:方法③条文・判例・基本書をしっかり読み込む
条文は法律の本質を、判例は問題解決のためにどう法律を適用したかを、そして基本書は条文の解釈を示したものですので、しっかりと読み込むことで予備試験合格率も高まります。
しかし民法だけでも1000を超える条文を一つひとつ、判例や基本書を隅々まで丁寧に読み込もうとすると、かなりの時間がかかります。
そこで、過去問演習と並行して、解答・解説に紐づけられた条文・判例をしっかりと読み込むようにすればムダがなく、出題傾向に沿って基本書もマスターしていけば、効率的な学習が実現できます。
3-4:方法④効率的な学習スケジュールでモチベーションを維持する
モチベーション(やる気)が最も下がりやすいのは、学習計画と実際が大きくかけ離れ、遅れていることに気がついた時です。
学校や仕事、家庭の事情で思うように勉強ができないのは仕方ありませんが、それを理由に受験を断念するのは避けたいところです。
やる気が起こらず勉強できない問題は実は、やる気に関係なく勉強できるように持っていくことで解決します。それが「習慣化」です。
「22時から机に座って勉強する」と時間や場所を固定して、勉強を習慣化してしまえば、モチベーションに左右されなくなります。
また、時間よりも大切なのは、勉強量です。
2時間で10ページ進めるところを、1時間で10ページ進めるようにすれば、1時間余計に睡眠などに充てられます。
2時間じっと座って勉強しないといけないと思うか、1時間で10ページ終わったら眠れると思うか、どちらがモチベーションが維持しやすいかは明白なはずです。
4章:予備試験に合格するためには「ヨビロン」をおすすめします
独学を始めて、最初につまずきやすいのが、教材選びです。
「図書館や書店で吟味してみたけれど、どの教材が自分に合っているかが正直わからない」
「高価な教材を購入したものの、使いこなせなかったので、これ以上失敗したくない」
と思っている方もいるでしょう。
そこで、予備試験合格を目指す全ての方に
- 予備試験特有の出題傾向に対応している
- 過去問演習だけでは補えない知識を効率よく学べる
- 自分のペースで学習を進められる
といった特徴を持つ、「ヨビロン」をおすすめします。
4-1:ヨビロンは予備試験特有の出題傾向に対応している
予備試験と司法試験は、どちらも弁護士・検察官・裁判官を志す方の試験ですが、出題傾向が異なります。
司法試験向けの教材では、予備試験合格は勝ち取れません。
予備試験は司法試験と比べ、出題趣旨が薄い問題が出されることが多く、ヨビロンの著者(予備試験1桁合格者)が編み出した「客観的読解法」と「解法パターン」を体得することで、予備試験を突破できる可能性が高まります。
4-2:ヨビロンは過去問演習だけでは補えない知識を効率よく学べる
過去問演習では、過去問や模範解答を通じて、出題傾向や関連する条文・判例の再確認と、法的思考力と答案構成力を強化することが可能です。
しかし、論文式試験で本当に必要なのは、戦略です。
独学の方でも初見の問題に慌てずに、焦らずに対応できるようにするには、問題の考え方のパターンをしっかりと学ぶ必要があります。
それを可能としたのが、問題の考え方のパターンを体系化したヨビロンです。
そのほか予備試験の出題傾向も同書で学べるため、効率よく勉強できます。
4-3:ヨビロンは自分のペースで学習を進められる
ヨビロンは、テキスト形式の論証集ですので、スキマ時間や決まった時間に自分のペースでムリなく読み進めることが可能です。
また公式LINEで、『判例の射程』『目的手段審査判例まとめ』「生存権」の一般的解法、解法を使った過去問解説動画「生存権」といった特典も受け取れ、独学をこの先、進めていくのに有効なヒントもたくさん見出せるでしょう。
まとめ:予備試験に独学で合格する方法
適切な教材や情報を受け取れる環境にある法科大学院や予備校ではなく、独学を選んだ場合でも、以下5つを心得て、勉強していくことで、予備試験合格を目指すことが可能です。
- 論文式試験の対策を重視し出題傾向を把握する
- 過去問演習に早期に取り組み答案作成技術を高める
- 条文・判例・基本書をしっかり読み込む
- 効率的な学習スケジュールでモチベーションを維持する
- ヨビロンで「客観的読解法」と「解法パターン」を体得する
独学を始めたばかりで不安な気持ちになったとき、教材選びに悩んだときは、予備試験の1桁合格を果たした専門講師が作成した教材「ヨビロン」をぜひ、スターターキットのひとつとして使ってみてください!






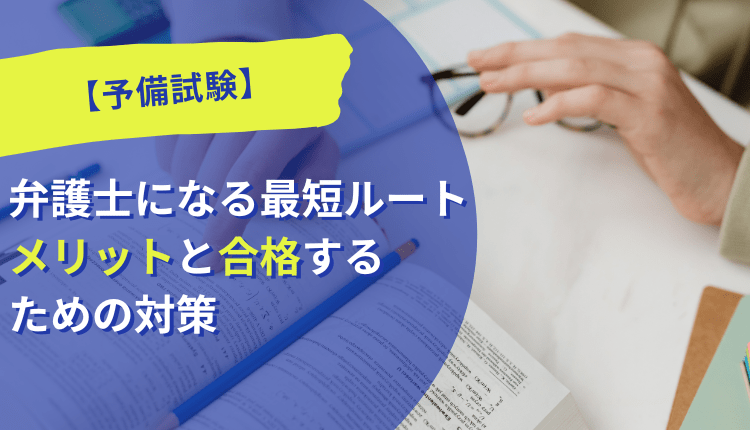

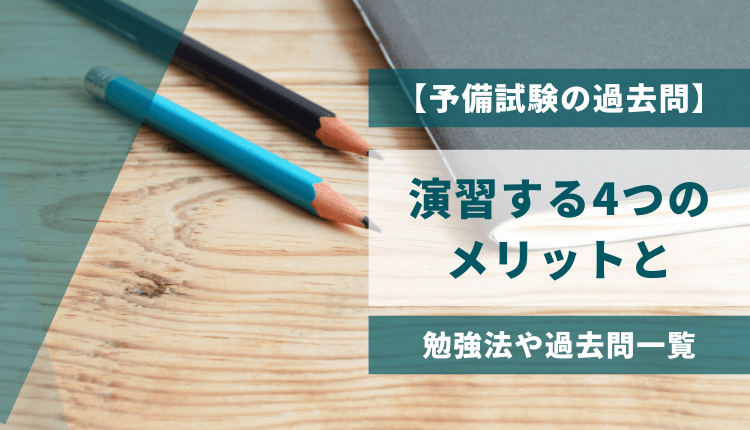
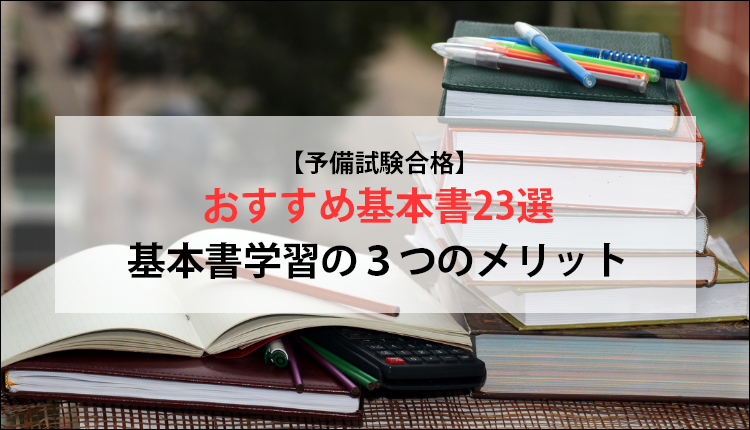
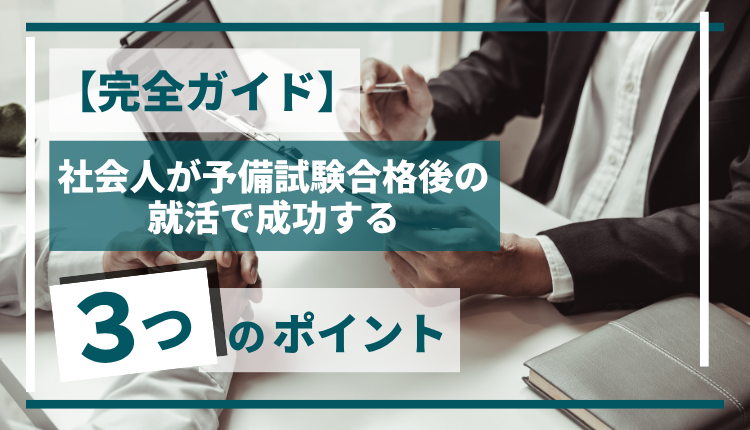
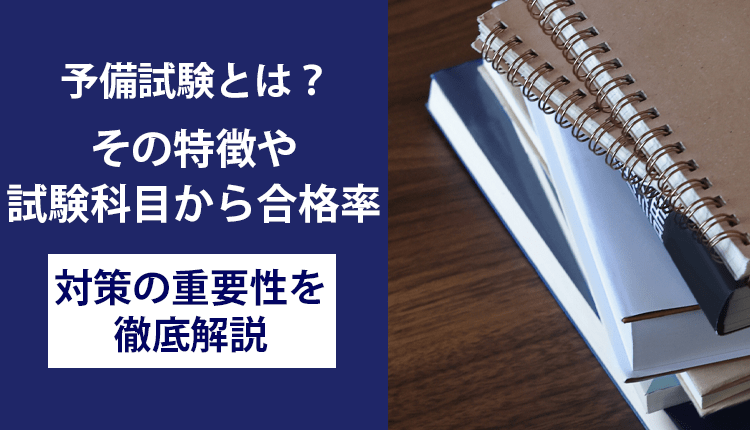
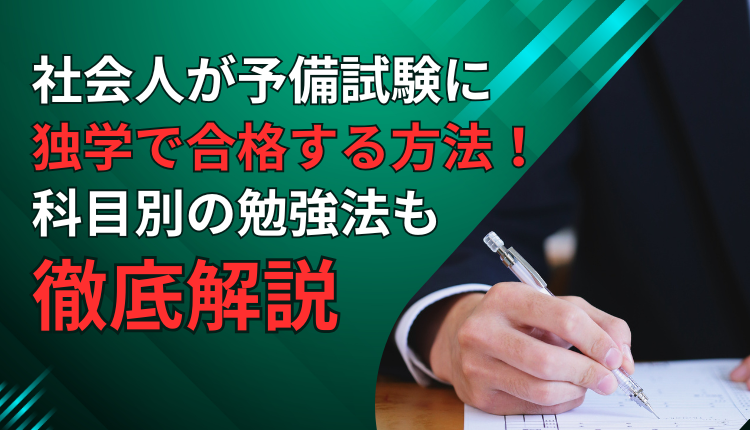

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。