【司法試験】オンライン予備校のメリット・デメリット、選ぶポイント6つ
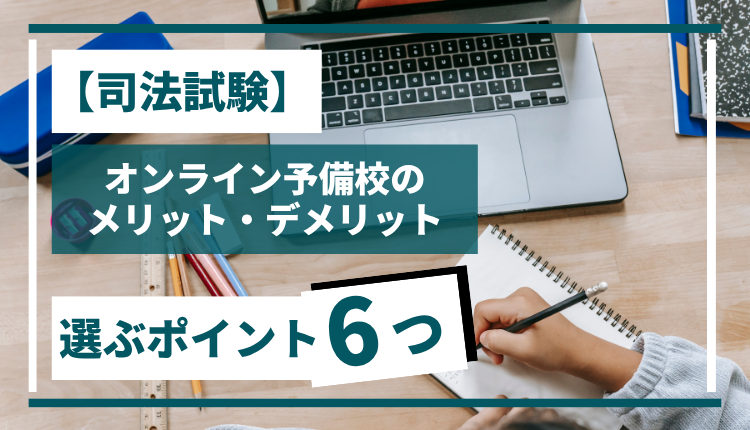
目次
この記事を読んで理解できること
- 司法試験対策|オンライン予備校の基礎知識
- オンライン予備校の4つのメリット
- オンライン予備校のデメリット
- 効果的なオンライン学習の進め方
- オンライン予備校を選ぶポイント
あなたは、
- 司法試験予備校のオンライン講座のことや従来型予備校との違いを知りたい
- オンライン予備校で学習するメリットやデメリットを知りたい
- オンライン予備校における効果的な学習の進め方について知りたい
とお考えではありませんか?
スマートフォンの普及、インターネット(Wi-Fi)環境の安定、働き方やライフスタイルの多様化に伴い、オンライン予備校が台頭し、多くの司法試験合格を目指す人たちから注目を集めています。
従来型予備校ではなく司法試験のオンライン予備校を選択することは、予備試験や司法試験において有利に働くのでしょうか?
本記事を読めば、オンライン予備校とは、自分に合いそうか、学校や仕事と両立できそうか、効率的なオンライン学習方法についても知ることができます。
具体的には、
1章でオンライン予備校の基礎知識
2章でオンライン予備校のメリット
3章でオンライン予備校のデメリット
4章で効果的なオンライン学習の進め方
5章でオンライン予備校を選ぶポイント
について、詳しく説明していきます。
1章:司法試験対策|オンライン予備校の基礎知識
実際にオンライン予備校に入学してから試験日当日まで、どのような受験生活を送ることになるのでしょう?
本章では、司法試験のオンライン予備校とは、従来型予備校との違いの2点について、お伝えしていくことにします。
1-1:司法試験のオンライン予備校とは
司法試験のオンライン予備校は、法曹(弁護士など)を目指す方が、インターネット環境下において、お手持ちのパソコンもしくはスマートフォンを使って講義を受け、自習していくことが可能な資格スクールです。
感染症の流行と対策が必要不可欠だったことや、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視する人たちが増えたことで、ここ近年、スクーリング授業よりも、オンライン学習のニーズが高くなっています。
1-2:司法試験に向けて従来型予備校との違い
校舎に教室、机とイスが用意されている従来型の予備校とは異なり、オンライン予備校においては自宅・自室が校舎・教室となります。
そのため、通学が必要なのが従来型予備校、通学が不要なのがオンライン予備校と言い換えることも可能です。
また、下表のとおり、学習アプローチなどが、大きく異なっています。
|
従来型予備校 |
オンライン予備校 |
|
|
学習アプローチ |
予備校主導 |
受講生主体 |
|
教材提供方法 |
主に紙ベース |
主にデジタル |
|
指導体制 |
対面で直接 |
オンライン |
2章:オンライン予備校の4つのメリット
司法試験のオンライン予備校に通うことで、以下4つのメリットを享受できます。
- 時間の有効活用と学習の柔軟性
- 経済的なコスト削減効果
- デジタル教材による効率的な学習方法
- 通学時間の削減と学習時間の確保
具体的にはどういうことか、本章で詳しく見ていくことにしましょう。
2-1:時間の有効活用と学習の柔軟性
オンライン予備校の最大のメリットは、司法試験合格に向けてスキマ時間に自分のペースで勉強を進めていける点です。
昼夜問わず自宅・自室で自由に学習でき、時間だけではなく、実は学習進捗状況(習熟度)にもとらわれることがありませんので、とても柔軟なのです。
従来型の予備校は、多くの受講生に対し、時間割・カリキュラムどおりに待ったなしで講義を行っていくため、遅刻・欠席が許されません。
そのため受講生は、プレッシャーを感じやすいです。
また講義内容を理解できず、勉強についていけなくなり、途中で挫折する受講生も少なくありません。
しかしオンライン予備校であれば、理解できなかった単元は、理解できるようになるまで講義を動画で見返すことが可能で、理解できてから次の単元に進めばよく、自分のペースでムリすることなく勉強を継続していけるわけです。
社会人など、なかなか時間がとれない方は、オンライン予備校のほうが合っているでしょう。
2-2:経済的なコスト削減効果
オンライン予備校を検討する場合、スクールや講座の選択肢は比較的豊富で、価格も予算に応じて選ぶことができます。
また、交通費や食事代といった通学費用も、自宅・自室での学習ならコストカットが可能です。
2-3:デジタル教材による効率的な学習方法
書籍(紙)の教材は相当の嵩(かさ)と重みがあり、図書館や喫茶店などに出向き勉強するにしても、すべての教材をカバンに入れて持ち歩くのはほぼ不可能です。
しかしデジタル教材なら、スマートフォンやノートパソコン、クラウドに格納することもできます。
そのため、端末やWi-Fiさえあれば、時間や場所を問わず情報を引っ張り出して、その日の気分で学習範囲を決めて、効率よく勉強することが可能なのです。
図書館や喫茶店のほか通勤列車、駅のホーム、銀行や病院の待ち時間など、余すところなく有効活用できます。
2-4:通学時間の削減と学習時間の確保
オンライン予備校なら、通学時間を丸々カットして、勉強することができます。
お住まいのエリアにより変わりますが、教室まで片道30~60分かけて通学する場合を考えてみてください。
通学に1日あたり1~2時間かけていたところを、自宅・自室での学習にすべて置き換えることが可能なのです。
3章:オンライン予備校のデメリット
司法試験のオンライン予備校には、次の3つのデメリットがあり、事前に把握しておくと対策が立てやすいです。
- モチベーション維持が難しい
- 質問やフィードバックにタイムラグが生じることも
- 教材の補完と最新情報の更新が必要
上記3つについて、対策も交え説明していきます。
3-1:モチベーション維持が難しい
従来型の予備校とは異なり、周囲の人たちや、雑音を気にすることなく黙々と学習できるのが、オンライン予備校の最大の魅力です。
しかし、自宅・自室にこもってひとりで勉強していくため、孤独を感じやすいでしょう。
ライバルの進捗状況が見えないことからひとり不安に陥りやすく、モチベーションをいかにして保つかが、課題になりがちです。
オンライン予備校によっては、同じ講座の受講生と交流できたり、講師や司法試験合格者に質問を出すことも可能だったりしますので、制度を活用して孤独感や不安の払しょくを図りましょう。
3-2:質問やフィードバックにタイムラグが生じることも
オンラインという特性上、講師や司法試験合格者に質問を送っても、その内容や時間帯、相手方の状況により、すぐに回答やフィードバックが返ってこない場合があります。
「タイムラグが生じるもの」と割り切り、わからないところや不明点が出てきたら早々と質問を送り、回答が来るのを待ちましょう。
3-3:教材の補完と最新情報の更新が必要
選択したスクールや講座によっては、最新版の教材ではない、書籍がよかったのにデジタル教材しか用意されていないケースもありえます。
そのため、法改正や最新判例に関する書籍や、自分に合う市販のテキストをネットや書店で取り寄せ、アップデートしていかなければなりません。
各校、教材については、公式サイトなどで解説していたり受講相談もできたりしますので、事前に問い合わせて確認するようにしましょう。
4章:効果的なオンライン学習の進め方
司法試験のオンライン予備校に通う以上、自宅・自室での学習を効果的にしたいと思うのは、合格を目指す受講生として、当たり前のことです。
本章では計画、管理、ツールという3つの視点で解説していくことにします。
4-1:学習計画の立て方
試験日を着地点(ゴール)として、逆算しながら月、週ごとに目標を立てていき、各日、どの単元を学習していくかを、時間割に落とし込んでいくようにします。
学生は学校とアルバイト、社会人は仕事や家庭との兼ね合いを考え、勉強に充てられる時間を書き出して、毎日の時間割を作成していくといいです。
なお、司法試験本番まで年単位で学習していくことになりますので、短期間で多くの知識を詰め込もうとするよりも、少しだけ時間を置いてから復習する「分散学習方略」を採用することで、知識の長期定着効果が見込めます。
4-2:進捗管理の方法
進捗管理はできれば週、月ごとに、日記やログで振り返るほか、理解度・習熟度の見える化を目的に、定期的にテストや答練を実施して、自ら採点するようにします。
目標と成果に乖離が見られるなら、状況に合わせて都度、計画を見直し、調整も行います。
できていない点を深刻に受け止めるのは大切なことですが、モチベーションが下がらないように、目標を達成できた項目については自分で自分を積極的にプラス評価してあげるようにしてください。
4-3:オンライン学習ツールの使いこなし方
オンライン予備校に入校して、プラットフォームにログインしたら、初期の段階で動画視聴や教材ページだけではなく、リンク先すべてにアクセスするようにします。
どのようなコンテンツを利用できるのか、学習に役立ちそうなツールはあるのかを把握して、まずは気軽にすべて試してみることが大切です。
試していくうちに、使いこなせるようになるでしょう。
しかしながらオンライン予備校側が、受講生のことを考えてプラットフォームを設計しているはずですので、想定もしくは推奨している使いこなし方があるはずです。
公式サイトの記載や、交付されたハンドブックがあれば、しっかりと読み込み、必要に応じて質問したり、個別指導を申し込んだりして確認するようにします。
5章:オンライン予備校を選ぶポイント
司法試験のオンライン予備校選びは合否を左右するといえ、例えば友人や知人に教えてもらったからといって、自分で詳細をよく確認しないまま安易に入校申し込みをするのはおすすめできません。
あとから相性がよくないと判った場合、強い後悔の念が残るからです。
最後に、予備校選びの勘どころを6つ、ご紹介していきますので、自分の目で各校、各講座を吟味するようにしましょう。
5-1:カリキュラムの充実度
司法試験のオンライン予備校のカリキュラムの充実度については、予備試験や司法試験に特化している点はもちろん、その多様性にも着目するようにします。
まずは、試験日までに強化しておきたい項目(論文対策や過去問演習など)が含まれているかを見ます。
そして、講義のかたち、教材の種類が多様にある講座を選ぶと安心です。
受講料は決して安くはありませんので、特に講義・教材が自分に合わないものしか利用できず、他の選択肢がなかった場合は、試験日までにベストな状態をつくりあげることが難しくなります。
そんな場合、合格を目指す以上背に腹は代えられないため、別の講座も受けようと決断すると思いますが、その分、費用がかかることになります。
そのため、オンライン予備校選びは、失敗が許されません。
動画のほか音声コンテンツもある、オンデマンドだけではなくライブ配信もある、デジタルだけではなくアナログ(テキストや問題集)も充実しているなど、多彩な選択肢が用意されている講座を選べば、スクール・講座とのミスマッチを起こさずに済みます。
5-2:受講料とコストパフォーマンス
受講料が明記されているか、特にカリキュラムの充実度、講師の質、学習サポート体制について、費用と内容のバランスが適切かなどをチェックしましょう。
まずは、受講料に含まれる項目と含まれない項目について、オンライン予備校の公式サイトなどで細かく確認するようにします。
事前確認をしっかりと行うことで、余計な出費を防げます。
また、不明な点は直接、予備校に問い合わせるようにしましょう。
5-3:合格実績
各校の合格者数や、合格占有率を確認しましょう。
オンライン予備校に通う目的はもちろん司法試験に合格するためですので、予備校を選ぶ段階で、実際の受講生の中から合格者がどのくらい出ているのかに着目すべきです。
合格実績を公表していない予備校もありますが、まずは各校、合格者の数を確認します。
そして合格者占有率(その予備校での合格者/司法試験合格者全体数)があれば確認し、占有率が高い予備校なら、講義・教材・サポートなど信頼していいものと考えます。
また、公式サイトだけではなくネット上(SNSなど)の口コミや評判を見て、学習の成果や実際のサポート体制についての情報を集め、裏付け材料にするといいでしょう。
5-4:学習サポート体制
質問、添削、個別指導、カウンセリングについてチェック・比較しましょう。
わからないところや不明点をオンライン上で講師や司法試験合格者に直接、質問できるか、論文の答案の添削を行ってくれるかも確認し、回数制限がある場合、その回数を超える可能性があるかも検討します。
学習に関する個別指導(マンツーマン)や、個別カウンセリングを実施しているかも、オンライン予備校選びの大きな判断材料とすべきです。
5-5:講師の質
講師の質は予備校の公式サイトや、公表されている講師の経歴、受講生の声、口コミなどから見極めましょう。
また最低限、司法試験合格という経歴を持つ講師陣から、学びたいと思うのが通常ですので、各校、現役弁護士、司法試験合格者が講師としてどのくらい在籍しているのかも必ずチェックします。
なかには、これまで合格者を多数、輩出しているカリスマ講師や、司法試験対策本を出版している講師、有名法律事務所に在籍している講師、弁護士法人の経営を行っている講師もいて、スクール側も大々的に紹介しています。
このように経歴がしっかりとしていて、なおかつ受講生からも支持されている講師がいる予備校なら、高い専門性やクオリティが期待でき、安心して講座に申し込めます。
講師全員の講義を確認できるわけではありませんが、予備校がYouTubeで人気講師の講義を無料公開しているケースもありますので、動画を検索して視聴してみるのもおすすめです。
ちなみに、ヨビロンの講師は、予備試験1桁合格という誇るべき成績を収めており、講師のクオリティは最高ランクと言いきれます。
5-6:学習環境の整備
オンラインプラットフォームや、自宅・自室での快適な学習が可能かを確認します。
オンライン予備校では、それぞれオリジナルのプラットフォームを用意していて、そこから日々の学習管理や動画視聴などができるようになっており、プラットフォームとの相性も合否を左右するといえます。
プラットフォームについては、公式サイトを確認するほか、受講相談でどのようなものか説明を求めてみるのもいいでしょう。
学習環境は、プラットフォームというハードだけではなく、ソフトも重要です。
教材のほか、個別指導や個別カウンセリングといったサポートがしっかりと整備されていれば、自宅・自室での学習環境は快適なものになるでしょう。
以上、6つの項目を吟味して、後悔のないスクール・講座選びをしてください。
まとめ:司法試験に向けたオンライン予備校の利用法
司法試験のオンライン予備校を利用するにあたり、プラットフォーム上にあるコンテンツはすべて確認して、有益なものは使いこなせるようになりましょう。
自宅・自室だけではなく、図書館、喫茶店、通勤列車など場所を選ばず、スキマ時間を見つけて動画やデジタル教材に目を通すようにします。
講師や司法試験合格者に質問を次々と投げかけ、不明点をなくす心がけと、個別指導やカウンセリングを積極的に利用し、孤独感や不安を払しょくする姿勢が大切です。
そしてモチベーションの維持と、分散学習方略をとることを忘れることなく、予備試験合格そして司法試験合格を自らの手で勝ち取りましょう。







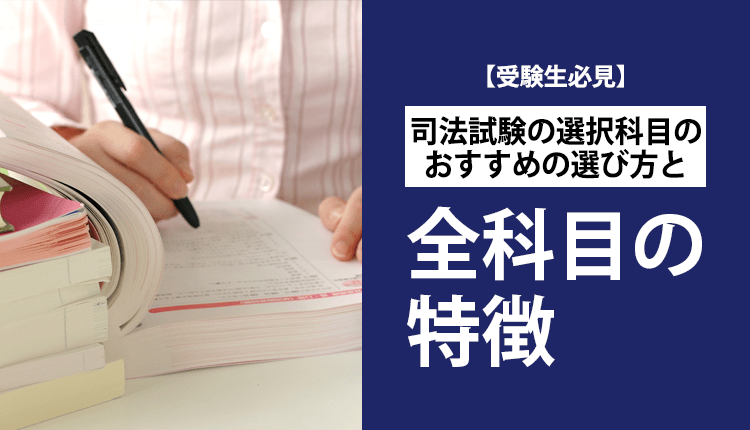


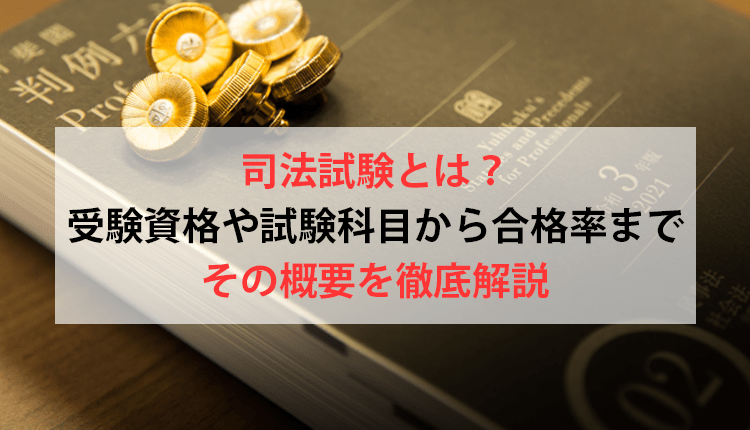
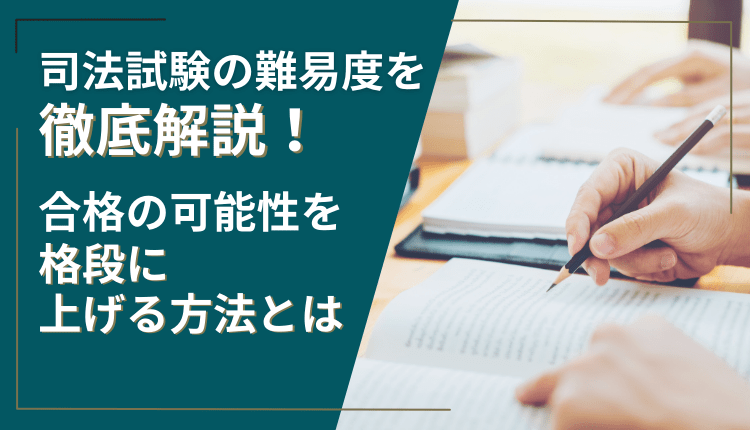

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。